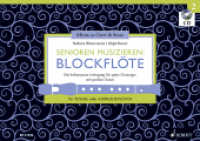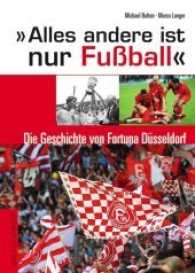内容説明
メディアにヘイトスピーチやフェイク・ニュースがあふれ、「右傾化」が懸念される現代日本。「歴史修正主義(歴史否定論)」の言説に対する批判は、なぜそれを支持する人たちに届かないのか。
歴史修正主義を支持する人たちの「知の枠組み」を問うために、歴史を否定する言説の「内容」ではなく、「どこで・どのように語られたのか」という「形式」に着目する。現代の「原画」としての1990年代の保守言説を、アマチュアリズムと参加型文化の視点からあぶり出す。
「論破」の源流にある歴史ディベートと自己啓発書、読者を巻き込んだ保守論壇誌、「慰安婦」問題とマンガ、〈性奴隷〉と朝日新聞社バッシング――コンテンツと消費者の循環によって形成される歴史修正主義の文化と、それを支えるサブカルチャーやメディアの関係に斬り込む社会学の成果。
******************
酒井隆史さん(大阪府立大学)、推薦!
なぜ、かくも荒唐無稽、かくも反事実的、かくも不誠実にみえるのに、歴史修正主義は猛威をふるうのか? いま、事実とはなんなのか? 真理とはなんなのか?
真理や事実の意味変容と右傾化がどう関係しているのか?
「バカ」といって相手をおとしめれば状況は変わるという「反知性主義」批判を超えて、本書は、現代日本の右翼イデオロギーを知性の形式として分析するよう呼びかける。キーはサブカルチャーである。わたしたちは、本書によってはじめて、この現代を席巻する異様なイデオロギーの核心をつかみかけている。この本は、ついに現代によみがえった一級の「日本イデオロギー論」である。
目次
はじめに
序 章 なぜ「メディア」を問うのか
1 保守言説の広がり
2 これまでの調査研究でわかっていること
3 本書の対象――歴史修正主義と一九九〇年代
4 「何が語られたか」ではなく「どこで/どのようにして語られたか」
5 本書のアプローチ――コンバージェンス文化
6 本書の構成
第1章 歴史修正主義を取り巻く政治とメディア体制──アマチュアリズムとメディア市場
1 歴史修正主義の特徴
2 歴史修正主義はどこで/誰が展開しているのか
3 教科書をめぐる政治運動と右派メディア知識人
4 歴史修正主義をめぐるメディア市場
第2章 「歴史」を「ディベート」する──教育学と自己啓発メディア
1 「自由主義史観」と「ディベート」
2 「歴史」を「ディベート」する
3 メディアでのディベート表現の展開
第3章 「保守論壇」の変容と読者の教育──顕在化する論壇への参加者
1 「論壇」の輪郭と「論壇」の問い直し
2 読者の「教育」――読者コーナーのメディア論
第4章 「慰安婦」問題とマンガ──『新・ゴーマニズム宣言』のメディア論
1 これまで小林よしのりはどう語られてきたか――先行研究と本書のアプローチの違い
2 「慰安婦」問題を否定する保守言説の構築とそのメディア特性
3 「読者」の扱いと言説空間の構築
第5章 メディア間対立を作る形式──〈性奴隷〉と新聞言説をめぐって
1 〈性奴隷〉の初出をめぐって
2 主要新聞報道で〈sex slaves〉はどのように用いられたか
3 批判の「形式」へのこだわり
終 章 コンバージェンス文化の萌芽と現代──アマチュアリズムの行方
1 コンバージェンス文化の萌芽
2 コンバージェンス文化の現在
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ろくせい@やまもとかねよし
おさむ
小鈴
さとうしん
ドラマチックガス
-
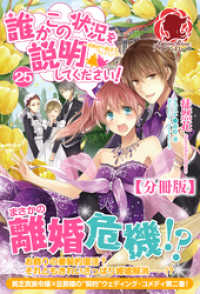
- 電子書籍
- 【分冊版】誰かこの状況を説明してくださ…
-
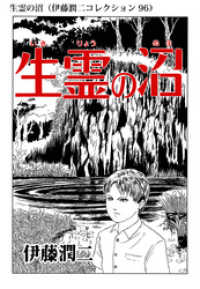
- 電子書籍
- 生霊の沼(伊藤潤二コレクション 96)…