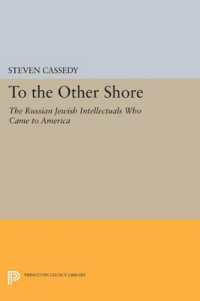内容説明
“自然は寂しい、しかし人の手が加わると暖かくなる”と、宮本常一は言う。けやき、茶、桜、杉、くぬぎなどの木々がおりなす武蔵野の風景は自然の風物ではなく、人々が一本一本植えることによって作り出されたものである。こうした武蔵野の第二自然形成の歴史に象徴される日本人の自然への対し方をはじめ、衣食住・こころのありようと森林花木とのかかわりをめぐる諸篇を収録する。柳宗民氏との対談も収載。解説=西山妙
目次
日本人と自然
山の自然
マツと日本人
花と民俗
風景をつくるこころ
-
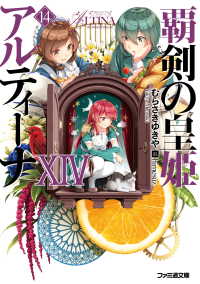
- 電子書籍
- 覇剣の皇姫アルティーナXIV ファミ通…