内容説明
戸田城聖の後を継ぎ、創価学会第三代会長となった山本伸一の峻厳な「弟子の道」が綴られている。日蓮大聖人の仏法のヒューマニズムの光をかかげて、世界を舞台に繰り広げられる民衆凱歌の大河小説。
<各章の概要>
【仏法西還】1961年(昭和36年)「躍進の年」の1月、伸一は、九州の三総支部、両国支部の結成大会出席など、多忙ななか、インド、東南アジア訪問を予定していた。1月28日、仏法西還の平和旅へ。香港では東南アジア初の地区を結成。次の目的地・セイロン(スリランカ)に向かう直前まで激励は続いた。
【月氏】セイロンへの機中、伸一は将来、アジアに総支部を結成する考えを明かす。仏法誕生の国・インド。伸一の思いは、ガンジーの思想と行動へ。2月4日、ブッダガヤで東洋広布の碑などの埋納を無事、終了。戸田が見守ってくれているような晴天だった。
【仏陀】伸一は、精神の大国・インドの源流である釈尊に思いをはせる。生老病死の解決を決意して修行し、生命の永遠の法を悟った釈尊。彼は、身分の差別なく人々を蘇生させた。提婆達多の反逆も乗り越え、死の寸前まで法を説いた偉大な生涯だった。
【平和の光】伸一らはビルマ(ミャンマー)へ。そこは長兄の戦死と、インパール作戦の舞台だった。伸一の回想は、戦中の思想統制から、牧口会長の殉難、世界平和への構想へと。タイ、カンボジアを経て香港に戻った伸一は、アジア各地に地区を結成。東洋広布は大きく開かれた。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
コウメ
39
内容は、釈迦の内容で以前「インドの歴史」で釈迦の生涯はある程度知っていたので復習できた。今回は「提婆達多」という元釈迦の弟子で後に裏切り、釈迦の組織を分裂させ離反させようとした人物の生涯を学んだ/「宿業を転換する中で大切なのは、死を迎えた時の心であり境涯」というワードが凄く響いた。2020/09/04
コウメ
21
歴史を見ても、どれほど優れた思想や宗教であっても、個人や国家を完全に救いきれなかった現実に目を向けるべきだという視点に深く共感した。信仰の対象次第で人生の幸福・不幸は根本から左右されるため、何を信じるかは極めて重要である。また、民族の復興には哲学が不可欠であり、それは観念論にとどまらず実践を伴うことで初めて力を持つ。さらに、苦悩は心の問題ではなく、生命の状態の反映であり、苦しい表情や感情の根底には「苦しんでいる生命」があると説く視点が印象深かった。2026/02/01
コウメ
21
人は死後、生命が宇宙に溶け込むが、宿業は消えず来世にも続く。恨みを抱えたまま死ねば、来世も同じ苦しみを繰り返す。逆に、幸福な境涯を確立し喜びの中で人生を終えれば、来世も幸福へと続く。現代の思想は現世のみに目を向け、生命の本質を見ていない。死をどう迎えるかが、人生の意味を決定し、生き方を導く。『いかに生きるか』の答えは『いかに死ぬか』を考えることにある。構想を持ち、それを現実にどう実現するかを考え、向上の意欲を持ち続けることが重要。2025/03/16
コウメ
19
信仰は行動と努力を伴ってこそ意味がある。誠実な行動と地道な努力が成功を築く。指導者は組織を私物化せず、献身的にメンバーの成長を支えることが重要。信義を守り、誠実に生きることで社会的な信用を得られる。試練や逆境を乗り越えることで真の成長がある。青年こそ未来を築く存在であり、学び続け、リーダーシップを発揮することが使命。苦しい時こそ信念を持ち努力することで、未来を切り開く力となる。2025/02/27
みゃーこ
12
仏陀の章良かった2022/04/24
-

- 電子書籍
- あいつを殺してあの子と埋めた 【分冊版…
-
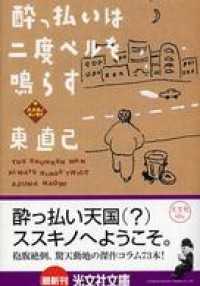
- 電子書籍
- 酔っ払いは二度ベルを鳴らす - ススキ…






