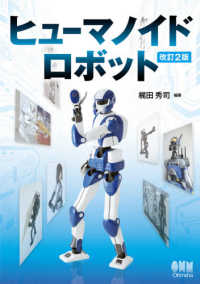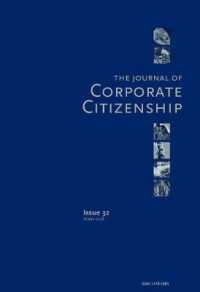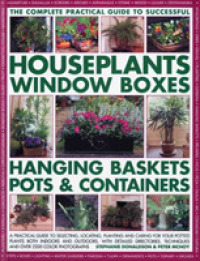内容説明
演劇を通して「対話」を学べば、違いを乗り越え、ゆるやかにつながれる
日常的な話し言葉を用いた「静かな演劇」で、日本演劇の潮流を変えた平田オリザ。日本語の特性やコミュニケーションのあり方を徹底的に分析してきた同氏がたどり着いた「他者と世界を理解する」方法としての演劇とは。役割に応じて「演じ分ける」存在である人間にとって、演劇はその起源から実社会におけるコミュニケーションと切り離せないものだった。多様化が加速し、疫病や戦争で人びとの分断も進む社会のなかで、「ともに生きる」ためにはどうすればいいのか。フィクションの設定を借りて自由に台詞を考え演じる「演劇ワークショップ」は、ことばへの意識を高め、異なる価値観を理解し、仲間とともに新しい価値を創り出す充実感を体験する有効な手段のひとつ。教育現場からも熱い注目を浴びている実践例をはじめ、演劇の可能性をさまざまな視点から検証した異色の演劇入門。
*本電子書籍をご購入された方は、本書の「『転校生が来る』台本」をNHK出版サイトからダウンロードできます。詳しくは書籍内の説明ページをご参照ください。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
110
多くを語らずとも通じ合えるハイコンテクストの社会で使われてきた日本語には、欧米のような論理的な会話が不自然に感じられる。しかし、多様な文化が存在する社会では対話が必要となる。対話とは、異なる価値観を持った人との対等な関係でのすり合わせである。子どもたちへの演劇教育を通じて、世界を見る解像度を上げることを目指している。著者の目指す演劇は、現象学的還元論に基づくもの。芸術文化観光専門職大学を開校し、著者が育てたいと望んでいる「楽しく共同体を作れる人」は、豊岡のある但馬地域で幾人も生まれることであろう。2022/08/08
三井剛一
15
海外では学校教育に演劇が取り入れられてるのに驚き。 役柄、演者、裏方含めコンテクストのズレをすり合わせていく過程は対話の学びになりそう。 異なる価値観・文化的背景を持つ人達と対話し、合意形成するためには、異なる価値観を恐れず表出し、認め合うことが大事。日本のお国柄で対等な関係が築きにくいが所以、対話も意識的に取り組まないと難しそう。同意せずとも、相手の気持ちをおもんぱかり共感できる人が多い世の中になるように。2024/04/19
どりーむとら 本を読むことでよりよく生きたい
8
これからを「ともにいきるために」は対話の力を培っていくことが大切であること、そのためには相手の価値観との違いを把握しておくことが大切であることなどが改めて認識できました。平田オリザさんは、自分が他の国の人たちと共に、演劇を作り出した経験や、笠岡の学校で演劇教育を行ったことなどを基に分かりやすく解説してくれていた。ゴミ当番のことについての説明もよく私の腑に落ちた。物事には絶対的な正解がないものもある。職場でも、親戚との付き合いでも、地域との付き合いにおいてもこの本で読んだことを参考にして生きていきたい。2023/07/02
Aby
5
コミュニケーションの助けとしての演劇.現在の学校教育(国語)における「演劇」の位置づけが,私には新しい.昭和に育った身としては,学芸会で「笠地蔵」とかやらされた意味が全然分かっていなかった.これからは,こういう教育を受けた子たちが社会に出ていくのだな.2024/03/24
papipapipapeace
5
対話したい!といつも願っていますが 職場で努力しなければ!2022/11/30