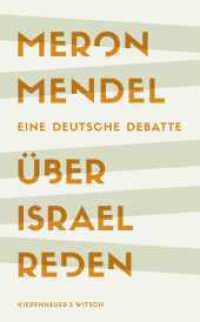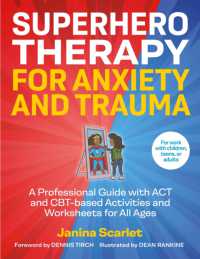- ホーム
- > 電子書籍
- > 趣味・生活(食/料理)
内容説明
その道40年、集大成にして入門の書。
私たちの一番身近にある「料理」。生きていくうえで欠かせないからこそ、毎日の食事を作ることにプレッシャーや負担を感じてしまう。しかし、料理の「そもそも」を知り、暮らしの意義と構造を知ることができれば、要領よく、力を抜いて「ちゃんとできる」ようになる。日本人は料理を、どのように捉えてきたのか。古来より受け継がれてきた美意識や自然観、西洋との比較などを通して私たちと料理との関係性をひもとく。料理を通して見えてくる「持続可能なしあわせ」「心地よく生きていくための道筋」とは何か。NHK「きょうの料理」でもおなじみの著者が、いまの日本の料理のあり方を考え抜いた末に提示する、料理と暮らしの新しいきほん。
-

- 電子書籍
- あなたの後悔なんて知りません【タテヨミ…
-

- 電子書籍
- あなたの後悔なんて知りません【タテヨミ…