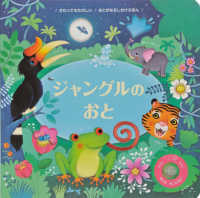内容説明
人が元気に喜びをもって生きていく、そのために必要なことは何か
哲学という営みが誕生して2500年、哲学者は、どのように「しあわせ」を見出してきたのか。ソクラテスの「対話」、ハイデガーの「可能性」、ニーチェの「永遠回帰」……。哲学者が時代ごとに考え抜いた思想の「エッセンス」から、人がしあわせに生きるために必要な考え方を提示する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
102
著者は東京医大で哲学を教える教授。極端に個別化し生きにくい現代に「人が元気に喜びをもって生きていく、そのために必要な条件は何か?」という問いを立て、哲学的に考えていく。承認と自由を得るために生きることが人間にとって必要であり、そのためには言葉で対話をして想いを受け止めあう関係をつくり育てることが重要である。ルソー・ハイデガー・フッサール・ヘーゲル・ニーチェの基本的な考え方を踏まえつつ、現代のわれわれの生き方に落とし込む。しあわせってどう自分の物語を生きるかの変え方次第。バタイユ・行岡哲男の著作に興味でた。2021/08/03
pirokichi
25
認知症の母は、多分「いま・ここ」しかないので(ほんと?)、その時々で怒ったり笑ったりしているのだと思う。切ないが、母が笑う時間が多くなるように、私も母と接する時には笑うようにしたいと思う。母を介護している父は、将来に何の楽しみもなく、生きていてもつまらないといつも嘆いている。本書が伝えたい内容とズレているのかもしれないが、私は本書を読んで、父の話をもっと丁寧に聴こうと思った。そして、父に対して攻撃的でなく誠実に話そうと思った。帰省して戻ったばかりなので何を読んでも両親のことを重ねてしまう。対話が大切。2025/08/25
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
24
【1回目】ヘーゲル、バタイユ、ニーチェなどの説を引きながら、私たちがふだん使っているのと地続きの日本語で「しあわせ」を味わうための哲学的思考のススメを説いている。方法としての「哲学対話」「批評」も開示されていて、応用もしやすいのではないか。最後は、しあわせを汲み出す「意思」の重要さに行き着いたと読んだ。平易な口調ながら、今ひとつピンとくるものがなく、もう一度読むべきか迷うところ。2021/07/09
肉尊
20
しあわせとは何かというテーマを様々な哲学者を引き合いに出して解説する一冊。人間は自己承認欲求や安全基地を求める動物で、協調が大切だとか、様々な問いかけを行いなさいって話は分かるんだけど、綺麗事ばかりで頭に残らない話が多い(バタイユ以外)人間ってどんなに幸福な状況にあっても不安を感じてしまう、根源的不安があるわけで、それは死の問題とも重なり合う部分があると思う。かつて渋谷氏が幸せとは環境の変化だと説いたが、砂漠で喉を潤すが如く、もっと強烈なアプローチが欲しかったかな。2021/09/21
ほし
18
自分は西研さんの著書をきっかけに哲学に興味を持つようになったのですが、この一冊は西研さんの様々な本の中でも最も簡潔に西研さんの思想のエッセンスが纏められているのではないでしょうか。現象学の視点から、体験に根ざした対話をすることを西研さんは重視します。そのような対話をする関係から存在の承認が生まれ、他者と自己の理解が深まり、自分の物語が再構築されることで自分の軸ができ、自由になれる。存在の承認から自由な活動が生まれ、やがて評価的承認へと繋がっていく。承認と自由の視点から、人間にとっての喜びを描く一冊です。2022/07/11