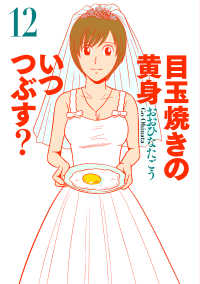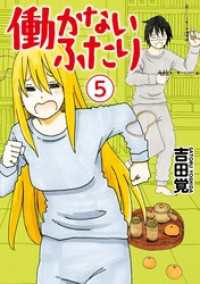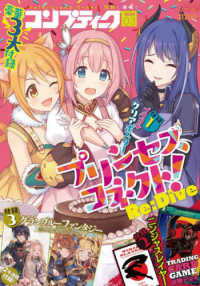内容説明
覚醒した薩摩、目覚めなかった長州。
世に言う「八月十八日の政変」で京を追われた長州は失地回復を狙って出兵を行なうも、会津・薩摩連合軍の前に敗走する。この「禁門(蛤御門)の変」以降、長州と薩摩は犬猿の仲となるが、その後、坂本龍馬の仲介で「薩長同盟」が成立。やがて両藩は明治維新を成し遂げるために協力して大きな力を発揮した――。
以上はよく知られた歴史的事実であるが、じつは禁門の変以前の薩長の関係は大変良好であった。策士・久坂玄瑞の働きにより、すでに「薩長同盟」は実質的に成立していた、と言っても過言では無い状態だったのである。
では、友好だった両藩が、「八月十八日の政変」「禁門の変」へと突き進み互いに憎しみあい敵対するようになったのはなぜなのか?
そこには、兄・島津斉彬に対するコンプレックスを抱えた“バカ殿”久光を国父に戴き、生麦事件や薩英戦争を引き起こしながらも「攘夷」の無謀さに目覚めた薩摩と、“そうせい侯”毛利敬親が藩内の「小攘夷」派を抑えきれず、ついには「朝敵」の汚名を着ることにまでなってしまった長州との決定的な違いがあった。
【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





行雲斎の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
山本真一郎
36
読了。このシリーズも気が付けば20巻目。幕末に突入してからは3冊目となる。文久2年(1862)〜元治元年(1864)にかけての約3年間、恐らく幕末史の中で最も激動の期間だと個人的には思っている。前半は薩摩藩、後半は長州藩に筆が費やされた印象だが、顕著に目立っていたのは矢張り西郷隆盛と高杉晋作だと思う。勝海舟、坂本龍馬、島津久光等はすっかり引き立て役になった感すらある。また反対に悪い意味で印象に残ったのが長州藩の狂信者ぶりであり、これが現代まで引き継がれているのかと想像すると空恐ろしくなる。続刊が楽しみだ。2017/06/30
金吾
32
大攘夷と小攘夷の話は面白かったです。暴走状態の長州がよく伝わりました。結果が見えている人間でも止められず、責任も取れない公卿が暴走を後押しする構造は日本の弱点の一つなのかなと思います。2025/09/25
ソラ
30
小攘夷という短絡的な視点しか持たない人物がほとんどであるなか、勝海舟の視点は当時の社会情勢を考えると本当に稀有なことであることがわかる。長州は高杉晋作という傑物を排出したけれども「長州的観念論」というリアリズムの無い狂信的な考え方には吐き気がする。亡国の考え方だよなぁ。2017/05/07
yamatoshiuruhashi
21
遂に高杉晋作登場。幕末のファナティックな「攘夷」と「佐幕」の本質を解きほぐしていく。西郷隆盛がどれほど島津久光に嫌われたか、その島津久光とはどういう立場だったのか。長州はどう動いていたのか。本シリーズにはいつも驚かされるような歴史解釈があったが、本巻ではさほどの新解釈はないように思われる。しかし年ごとに起こった事柄の相関関係を説明していく手法でこの動乱期の理解がより進む。2017/04/27
templecity
19
アヘン戦争で負けた中国は衛生観念が無く全く不潔で、川にはし尿や死体などもそのまま流れてくる始末。飲水も汚れた水の上澄みを飲むというような清水が流れる日本人から見ると信じられなかったようだ。薩長では欧米と大砲を撃ち合う戦争があったが、射程距離で勝る欧米の砲には勝てなかった。それでも彼らからすると中国に比べ、品質技術力は驚きの対象だったようだ。内戦の無い太平の世で技術力が磨かれた素養があったと言うことだろう。(続きあり) 2020/02/28