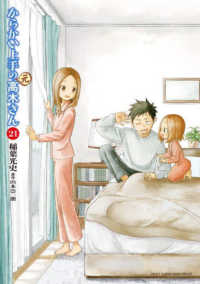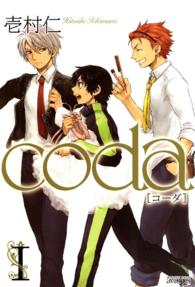内容説明
【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。
701(大宝元)年、大宝律令制定という制度改革によって、多くの制度が一気に切り替えられた。文字や時間を使いこなし、年号や暦の使用、戸籍の作成、官僚機構の整備など、国を統治するしくみが機能しはじめる。行政機関ができると、そこでは文書を作成する役人が働くようになるが、その姿は現代のサラリーマンと変わらない。庶民には税が課され、道路や都の整備などの労役や兵役にも動員された。一方、高齢者や障害者の介護などの福祉制度もこの時代につくられていた。国家が立ち上がり、変わりゆく時代に立ち会った人々の姿を通して、現代につながる歴史を生き生きと描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
14
この日本史の全集は、新しい発見の成果などを取り入れておりしかも文字が大きく私のような年寄りには大変ありがたい本です。その代わりに電車の中や寝転んで読むというわけにはいかないのですが。飛鳥時代、奈良時代が中心ですが、朝鮮や中国とのかかわりを丹念に書かれていて今までの全集とは少し違う感じがしています。2014/06/19
そり
10
百済と新羅&唐の戦いに介入して敗北する日本勢。それがきっかけだったのか、日本は唐から社会のシステム導入を画策する。導入の為、唐へ向かう長期留学生、この時の期間なんと20年。覚悟がすごかったろうな。その甲斐あって文字が現れ、時間の概念が現れ庶民の生活は一変。なんだかなにもかも支配されるようになる。強制労働に強制借金、当然逃亡するものも続出。必死に真似てるのはいいがシステムの限界は考えなかったのか。昔の人間より現代の人間の方が倫理観は進歩したように思う。古墳を破壊して都を建てたりと、もうめちゃくちゃである。2013/06/27
kenitirokikuti
5
図書館にて。中公の日本の歴史シリーズでは2古代国家の成立と3奈良の都にあたる。次巻が述べているのだが、奈良の都に関する知見は発掘史料によって更新が進んでいるが、平安京はそうではない、と。長安の春やあさきゆめみじのイメージがいまだ支配的である▲奈良の地方官人による木簡に論語や千字文の練習書きがある、との話は聞いていたが、多くは冒頭1行目のみらしい。筆づかいの練習なんだなァー2021/09/25
へたれのけい
4
明治以前に外国(唐)から文化を必死で取り入れていたのが飛鳥奈良か。面白そうな時代だ。でも、この時代は殆ど知らないんだよなぁ。2017/10/07
鐵太郎
4
なかば意図的に、政治事件や政争の話はほとんど取り上げていません。時代を象徴するものが政治的な動乱であった時代もあるけれど、この約400年間は違うのではないか、という。そう筆者は、あの白村江の戦いですら、政治的な視点で捉えているとは言えないのです。朝鮮諸国の文化の継承から中国本土の価値基準を模倣する体制へ変化し、同時に日本の世界観が大きく変わった過去を著者は、それによって日本人の暮らしや社会の仕組みがどのように変遷していった様子のみで描いています。なるほど、これは面白い。2008/05/17
-
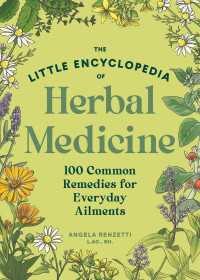
- 洋書電子書籍
- The Little Encyclop…