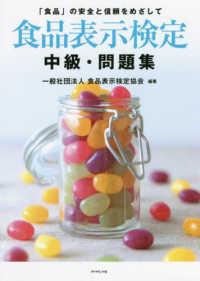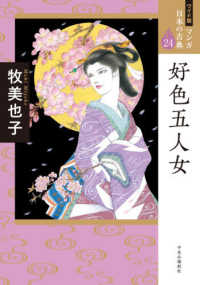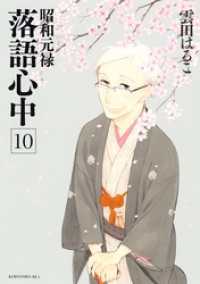内容説明
【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。
文化は、衣食住をはじめ暮らし全般にかかわる。本書では、現在の我々の文化の源流を江戸時代に求め、日本独自の文化がどのように形成されたかを解明する。俳諧・歌舞伎・浮世絵といった江戸時代に花開いた文化も、日本の古典と中国の文化が不可分に結びつきつつ創造された日本独自の文化である。こうした独自の文化の創造の過程を、まず庶民がどのような暮らしをしていたのか明らかにし、次に文化の享受者である庶民の視点に立って文化全般をみていくという画期的な方法論による日本文化史である。長い平和の世の中で、庶民が享受し親しむことが出来た文化を鮮やかに描きだし、今に続く日本文化の源を描いた1冊である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
37
「日本の歴史」全16巻の別巻「日本文化の原型」です。江戸時代における庶民の生活文化ということで、士農工商、住まい、絵画、読み書き能力、文具、出版社、貸本屋、食文化、着るもの、狂言などの愉しみ、旅へのいざないなどについての論考がわかりやすく説明されています。最後には「ごんぎつね」についての話があり楽しみました。2015/03/01
へたれのけい
4
新鮮な切り口、読みやすさに配慮した構成、すてきな全集でした。2019/03/27
印度 洋一郎
4
日本文化を、作り手では無く、受容する側、使う側から考察した刺激的な一冊。いわゆる日本人の伝統的な生活といわれているものが、19世紀に入って出現し、一気に広まったものであることを解説している。家の構造の変化とか、教育、文房具、衣服、食事、娯楽など多岐にわたる視点からの分析はとても面白い。2009/11/26
かわのふゆき
2
iPhoneをいじって本を読む時間が奪われている。この本は、作者が「チマチマした研究」と自ら評しているが、江戸の世を生きた人々の息吹が伝わる良書だと思う。2010/05/05
kozawa
2
問題提起の姿勢はシリーズ一貫しているなぁ。やはり読んでいて面白い。近世民衆文化はまだまだ研究の余地あり。2009/10/19