内容説明
文化を,すでにそこに在り,固有の内容を含むものとして眼差す我々の視線の背後には,いかなる政治学が内包されているのか.単なる文化の実証主義的な研究を超えて,それを「問題化」することは,何を意味するのか.「対象」としての文化から,「問題」としての文化へ.近代におけるこの概念の存立そのものを問い返す.
目次
目 次
はじめに
Ⅰ 文化を問題化する
Ⅱ 文化を読みなおす
第 1 章 サブカルチュラルなアイデンティティ
第 2 章 抗争の場としてのメディア
第 3 章 グローバル/ローカルな日常の政治学へ
Ⅲ 基本文献案内
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イリエ
9
グローバル化のなかで生じているものは、ハンチントンのいう文明の衝突よりも複雑で、固有の文化そのものの重層的な分裂だという。社会、政治を分析する草の根ガイドの本って感じ。2017/07/11
おおかみ
9
英国カルチュラル・スタディーズの系譜を概観。いかなる過程で文化が問題化されてきたのかを知ることで、カルスタのエッセンスを理解できる。ページ数が少ないだけに濃密で、あまり読みやすくはなかった。とにかくエッセンスを把握することはできたので、「基本文献案内」を参考に次の書に移りたい。2010/08/18
SQT
4
cs理論史。もっと日常や文化は重層的なんだよって感じで過去の議論がレビューされる。特に指摘されるのは、その文化やらなんやらの歴史的背景が捨象されているのでは(かつての宗主国と植民地という関係とか)ってのと、メディアとか送り手側からの発信を盲目にオーディエンスが受信してるみたいになってるよ(もっといろんな読み方をオーディエンスはしているよ)っての。ただまぁそのどちらもをクリアした作品というのはなかなか難しいっぽい(というかエスノグラフィーとかだとすべての要素を実際に見れるとは限らないから?)2018/02/05
瀬希瑞 世季子
2
抽象的で分かりにくい記述も多いが、それは我々が生きている文化、社会そのものが抽象的で分かりにくいものだということを意味している。ここで行われているのは世界を簡単なものと捉えることへの抵抗。2021/11/06
古戸圭一朗
1
今現在でも「カルスタ」という揶揄を込めた言及をされるカルチュラル・スタディーズは、決してお手軽な「文化研究」ではなく、従来とは異なった形で「文化」を捉えようとした試みであった。その軌跡を示すため、主に英国のカルチュラル・スタディーズがどのように発展してきたか、すなわち先達の視点を批判的に乗り越え、文化をめぐる知を深化させてきたかを概観している。ただ、100頁強の小著に、さまざまな理論が圧縮されているため、正直理解が及ばなかったという感じである。2019/12/27
-

- 電子書籍
- 名人【タテヨミ】第65話 piccom…
-

- 電子書籍
- 名人【タテヨミ】第64話 piccom…
-

- 電子書籍
- 【単話版】余命半年と宣告されたので、死…
-
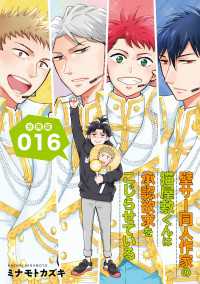
- 電子書籍
- 壁サー同人作家の猫屋敷くんは承認欲求を…
-

- 電子書籍
- CLUTCH Magazine Vol…




