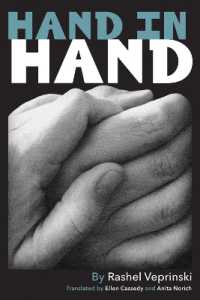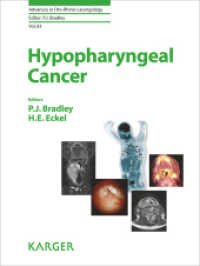内容説明
※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なる場合や掲載されないページ、付録が含まれない場合がございます。予めご了承下さい。
既に290号を超える長い歴史の「RM LIBRARY」から、過去の傑作巻を2~3冊分まとめて復刻する「RM Re-Library(アールエム リ・ライブラリー)」。シリーズ34巻目は、RMライブラリー第153巻「京成青電ものがたり」および154巻「京成赤電ものがたり(共に石本祐吉 著)」を復刻いたします。この2冊は連番であることからもわかる通り、刊行当時に同時制作されたものですので、合本とすることでより便利な一冊となると言えるでしょう。
京成電鉄の歴史は1912(大正元)年の開業から始まります。本書「青電」編では、その黎明期の車両の解説から始まり、昭和10年代に当時なりの「京成タイプ」を確立した200・210形を経て、戦後の本格電車2100形へと至る流れを詳解。「青電」という言葉の由来となった濃淡2色のブルー系塗分けは、1952(昭和27)年のクハ2000形2017・2018が初めて竣工時からこの塗色となり、在来車に波及したものです。また「青電」編では塗色こそ茶色系ながら特急車の系譜となる1500形、1600形「開運号」も紹介。特に後者が新車として津田沼の国鉄線から京成第二工場へ搬入されるという貴重なシーンは必見となっています。
後半となる「赤電」編は、1958(昭和33)年に、京成・京急・東京都との三者乗り入れ協定によって統一された規格に則った最初の系列・3000形から始まります。もっとも、この3000形の登場時は青電色をまとっていたことは今では見過ごされがちな事実。またこの時点では京成の軌間は1372mmであり、乗り入れを控えて1435mmへと大規模な改軌工事が1959(昭和34)年に行われ、この模様も本書ではたっぷり収録しています。実に54日間という計画で、路線の営業を止めずに実施された世紀の大工事、このタイミングだからこそ実現したものという感慨も得られます。最初から1435mm軌間で登場した3050形が初めて「赤電」塗色をまとって登場し、それは3000形にも遡って波及。その後3000系一族は大量に増備されましたが、1970年代半ば以降はステンレス車が台頭し、現在は全車廃車となっています(本書は最後の数編成が現役という時点で執筆され、時制はそのままとなっています)。
著者の長年の交友関係から得られた黎明期などの貴重な写真・資料・証言などを駆使した一冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えすてい
えすてい