内容説明
子供を「教育的に意味のある行動をさせる」のは、教師の大切な仕事である。本書は全体を大きく二つに分けてある。前半は子供を動かす原理編、後半は子供を動かす実践編というように構成した。
次のようにたった三つの原則を貫けばよい。
第一原則 やることを示せ
第二原則 やり方を決めろ
第三原則 最後までやり通せ
子供を動かす法則を身に付けてこそ、子供に自由を与えられるのである。(「まえがき」より)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまネギ子
2
面白かった。具体的に書いてあって参考になった。教師だけでなく、人の上にたつ立場の人や会議や司会進行などにも、役立つ内容だと思う。 2019/04/04
げんこつオニオン
1
大学を卒業し、半月後に教壇に立ち子供を動かす、早春に読んだ。読んで本当によかった。冗談抜きに、1年目から今までずっと、この本に助けられている。 どの世界にも、不易と流行がある。筆者の向山洋一は、20世紀末に大流行をつくった。教育技術の法則化運動。冷ややかな目で見た人、熱くのめり込んだ人もいただろう。私はTOSSに入っているわけでもないが、子供を動かす法則は不易にすべきだと強く思う。この本を知らない、理解できない人は残念だ。そんな嘆きは保留して、向山氏の子供理解、文章表現の豊かさと分かりやすさは一読である。2023/03/20
田中彰英
1
山本五十六、カーネギー、徳川家康、吉田松陰など、人を動かすことに長けていた歴史の賢者から学ぶ。コテンラジオ、聞こう。2024/11/03
コハル
1
子どものことを見落としてないと思い込むな、見落としていると(きちんと見れていないと)思え。自分への戒めです。来年度から担任を持つことになります。小学生ではなく高校生相手ですが、よりごまかしが効かなくなります。一方でより助けてくれる場面もあるはず。子どもたちを信じて、敵ではないということも忘れずに。味方につけられるよう、自分も時間を守り学ぶべきところは学ばせていただきます。2024/01/24
s n
1
「最後の行動を示す」ことによって、一人一人の子供は、その時間枠を自由に使うことが許され、かつ、自分なりに工夫・対応できるようになる。/誰がよくて誰がわるいのかを、どこがわるくてどのようにすればよいかを、はっきりさせてやることが大切。2023/07/25
-
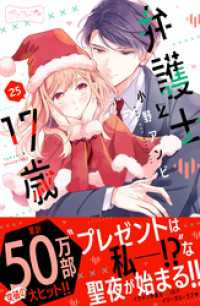
- 電子書籍
- 弁護士と17歳 ベツフレプチ(25)
-
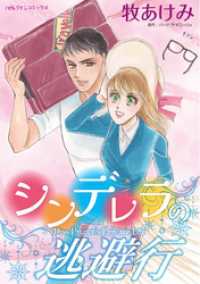
- 電子書籍
- シンデレラの逃避行【分冊】 10巻 ハ…
-
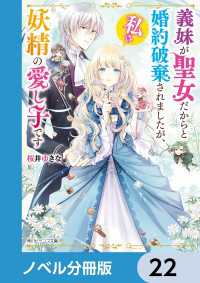
- 電子書籍
- 義妹が聖女だからと婚約破棄されましたが…
-

- 電子書籍
- 消えた記憶と愛の証【分冊】 5巻 ハー…





