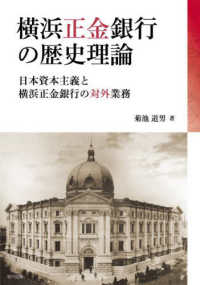内容説明
情報化,グローバル化が加速するメディア社会.公議輿論の足場として歴史的教養の重要性はますます高まっている.こうした現実の課題に対して,「大きな物語」が失われたあと,これまでの歴史学は充分に応えてきただろうか.公共性の歴史学という視点から,理性的な討議を可能にする枠組みとして21世紀歴史学を展望する.
目次
目 次
はじめに──余は如何にしてメディア史家になりしか
一、歴史学ゼミナールの誕生──歴史学はどのように生れたのか
教訓的歴史から歴史研究へ/大学の歴史学/フンボルト理念と歴史学ゼミナール/史料実証主義と情報リテラシー/言語論的転回とカルチュラル・スタディーズ/ランケの「国民史=世界史」/複製技術時代の文化史/メディア史の理念型
二、接眼レンズを替えて見る──歴史学を学ぶ意味とは何か
社会史が輝いていた頃/世界システムとメディア史/あなたは大衆ですか?──歴史を見る立ち位置/接眼レンズ(一)「宣伝」──社会主義宣伝としての「ナチ宣伝」/接眼レンズ(二)「公共性」──歴史家論争とファシスト的公共性/ベルリンの壁崩壊と街頭公共性/接眼レンズ(三)「国民化」──「大衆の国民化」の射程/ナショナリズムは国民主義である/ 「ナショナリズム」の現代化
三、歴史学の公共性──歴史学は社会の役に立つのか
趣味の歴史と大衆の趣味/国民大衆雑誌の公共性/戦時出版バブルの「発見」/言論弾圧という記憶の再審/ 「鈴木庫三日記」を読む/終戦記念日、「記憶の五五年体制」への挑戦/八月一五日に終わった戦争?/ 「記憶の五五年体制」と終戦記念日の成立/歴史の共有は可能か?──対話可能な歴史へ
四、メディア史が抱え込む未来──歴史学の未来はどうなるのか
メディア史の発展段階論/進歩史観と情報様式/メディア史の可能性/広告媒体の動員体制/マス・コミュニケーションはプロパガンダ/ 「世論の輿論化」の未来へ
五、歴史学を学ぶために何を読むべきか
「読む歴史」のために/ 「書く歴史」のために
おわりに──「ため息の歴史家」になりたい
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
politics
柳田
かろりめいと
ぽん教授(非実在系)