内容説明
日本の近代国家形成期において、和歌・短歌といった文化的な営みはナショナリティの確立にどう影響したのか。天皇巡幸、御歌所、歌道奨励会、教育学・心理学知との接合、題詠と歌会、愛国百人一首といった素材から和歌・短歌の近代と政治性を明らかにする。
目次
まえがき
序章 課題と方法
1 「国家装置」としての和歌・短歌
2 「近代短歌」研究から和歌・短歌の「近代」研究へ
3 本書の構成
第1章 天皇巡幸を「よむ」こと――『埋木廼花(ルビ:うもれぎのはな)』編纂の意味
1 編纂の経緯
2 「歌献りけむ人々」とは誰か
3 「未開」のみちのくと天皇という「光」
4 高崎正風註釈の諸問題
5 巡幸を「よむ」ことの広がり――まとめにかえて
第2章 「嗟歎(ルビ:ナゲキ)の声音(ルビ:コヱ)」の政治――高崎正風の歌論とその諸活動の検討
1 「まことの歌」の欠落
2 官僚・社会活動家としての営為
3 「御製」の発見
4 「君臣の情誼を繋げる」メディア
5 高崎正風を批評するために――おわりにかえて
第3章 明治天皇「御製」のポリティクス
1 一八七〇年代
2 一八九〇年代初頭
3 日露戦争前後期
4 アジア・太平洋戦争期へ
5 「心」に作用する「御製」――まとめとして
第4章 「旧派」の行方――大日本歌道奨励会の形成から衰退まで
1 本書での「旧派」の概念
2 会の設立と「詠進」システムの改編
3 会の組織とその特質
4 会員分布・会員網形成の要因
5 会員をつなぎとめる――教育・娯楽・出版
6 「旧派」の退場――おわりにかえて
第5章 「よむ」ことと心理学――「児童研究」誌における詩歌への期待
1 「心理」の抽出
2 「心理」へのすり込み
3 死ぬことを教える和歌
附記――心理学と「近代短歌」の接続可能性について
第6章 「和歌革新」前後――題詠と賀歌の変容
1 新題歌とその限界
2 新・旧題詠の差異
3 「本意(ルビ:ほい)」とは何か
4 題詠の継承と「自己」の析出
5 「国民」の賀歌
附記――「国民詩」としての短歌
第7章 歌会における「自己」表現の試行――「アララギ」派歌人たちの題詠
1 明治末期の「新しい運動」
2 視覚の「写生」を超える
3 身体と内面の「発見」
4 根岸派「伝統」への抗い
第8章 「芸術」と国家への理路――佐佐木信綱とその和歌観の変遷
1 「詠歌論」の主張
2 実益性の主張
3 「芸術」と「国家」への理路
第9章 つくられる“愛国”とその受容――「愛国百人一首」(一九四二年)をめぐって
1 バリエーションの分化と様々な受容
2 異種百人一首との比較
3 変容する“愛国”
4 おわりにかえて
附記――同時代的な戦争短歌について
第10章 誰が「ヒロシマ」を詠みうるか?
1 「御製」碑の論理――どのように忘却するか
2 原爆詠の表象と「合同」――どのように記憶するか
3 問われる原爆体験の真正性
4 「原爆詠」を超えるもの
5 誰が「ヒロシマ」を詠みうるか――おわりにかえて
初出一覧
あとがき
歌人・団体名索引
研究者索引
事項索引
感想・レビュー
-
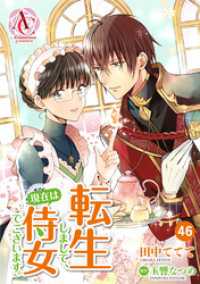
- 電子書籍
- 【分冊版】転生しまして、現在は侍女でご…




