内容説明
歴史には時代の流れを決定づけたターニングポイントがあり、それが起こった原因を探っていくことで「日本が来た道」が見えてくる。なぜ、明治期の日本は急速な近代化を実現できたのか。大日本帝国憲法発布(1889年)→明治十四年の政変(1881年)→内務省設立(1873年)→岩倉使節団の米欧派遣(1871年)の指導者の“信念”に裏打ちされた政策を見る。
■著作権上の契約により、印刷版に掲載されている図版は、掲載しておりません。
-

- 電子書籍
- 君に一生を捧げる【タテヨミ】第104話…
-
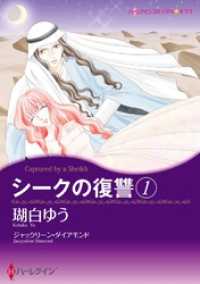
- 電子書籍
- シークの復讐 1【分冊】 2巻 ハーレ…
-
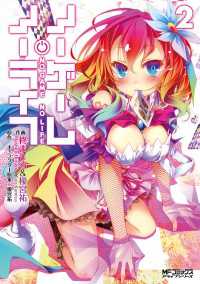
- 電子書籍
- ノーゲーム・ノーライフ 2 MFコミッ…
-
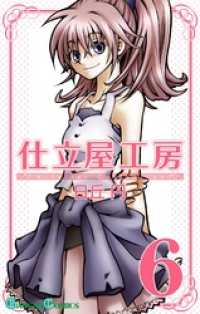
- 電子書籍
- 仕立屋工房 Artelier Coll…
-
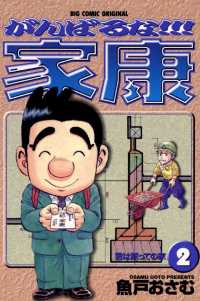
- 電子書籍
- がんばるな!!!家康(2) ビッグコミ…



