内容説明
歴史には時代の流れを決定づけたターニングポイントがあり、それが起こった原因を探っていくことで「日本が来た道」が見えてくる。「二大政党」の時代に入ったとされる今日の日本。第一回普通選挙実施(1928年)→原敬内閣成立(1918年)→日比谷焼打ち事件(1905年)→第一次大隈内閣成立(1898年)の政党政治の“失敗”から、いま見えてくるものとは。
■著作権上の契約により、印刷版に掲載されている図版は、掲載しておりません。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
向う岸
7
藩閥政治に対抗して政党政治が生まれたが、政党政治はその誕生からすでに党利党略(主導権争い、大臣ポストの奪い合い)で活動していた。その利己的な性格は現在も続いている。与党が政権維持するためには 多数の議席を確保することが至上命題となり、良い政治をするために政権を取ることが目的であるはずなのに、手段であるはずの選挙で勝つことや与党で在り続けることが目的化する。こうした互いの足の引っ張り合いが政党政治に対する国民の不満と不信を招き、遂には軍部の台頭へと結びつく。そして軍部を支持したのは国民だ。2012/03/12
takizawa
6
自民党と官僚の癒着や自民党と民主党のネガティブ・キャンペーン合戦,民主党の内紛に飽き飽きしている国民にとっては既視感のある記述ばかりだろう。立憲民政党と政友会によるネガティブ・キャンペーン合戦,利益誘導型政治システムのはしりとなった原敬内閣,政党と藩閥が相互にもたれ合う桂園体制などいずれも現代に引き継がれているような見慣れた光景が続く。歴史ってこんなに面白く学べるのかーと思わせてくれる一冊でした。2011/10/29
鯖
4
初の本格的政党内閣の成立から既に汚職まみれで、腐りきってて、原敬も一番最初くらいもうちょっと夢見させてくれてもいいじゃんかよーと失笑するしかない。地方に鉄道を延伸させる等、政党が支持基盤の利益を優先させるのは仕方ないことではあるんだけど。進歩ないなあ 進歩しようがないんじゃろかなあ…。どうすれば変わるのかなあ。じっと東を見る。2017/07/22
のぶさん
4
政党政治が長続きしなかった理由をその成り立ちまでさかのぼって探っている。政治的主張に大差のない政党は、権力闘争に明け暮れ、そのために利益誘導型の政治を行い、国民の失望を招いた。ここまで、今と一緒じゃん。その結果、現状を打破してくれる勢力として、軍部を選び、戦争に突入していった。現状に失望している今の国民は何を選ぶ? どんなにひどくても失望しちゃいかんのだと思う。2014/02/25
takuchan
3
政党政治というものが自然発生的に生まれるものではなく、また同時に、その基盤となる選挙による信任=民意の反映という基本原則を守り続けなければ、やがて崩壊に至ってしまう/ パラドックスの連続…。「さかのぼり」で読んでよくわからず、もう一度さかのぼらずに読んでみての繰り返し。政友会と藩閥の出来レース「桂園時代」に政治が安定していたというのも…。大隈政権誕生ももっとセンセーショナルなものと思っていたが…。政党政治がいいものなのか正解かわからなくなる。是非オンデマンドでの再放送を希望したい。2014/10/26
-

- 洋書電子書籍
- The Federalist Pape…
-
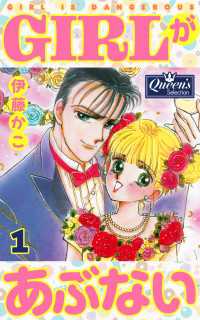
- 電子書籍
- GIRLがあぶない 1 クイーンズセレ…
-

- 電子書籍
- クランツ竜騎士家の箱入り令嬢: 5 箱…
-
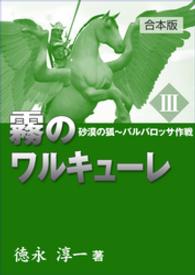
- 電子書籍
- 霧のワルキューレ(3)砂漠の狐~バルバ…
-
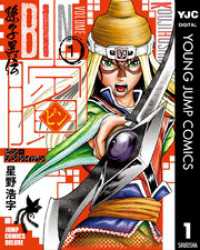
- 電子書籍
- ビン~孫子異伝~ 1 ヤングジャンプコ…




