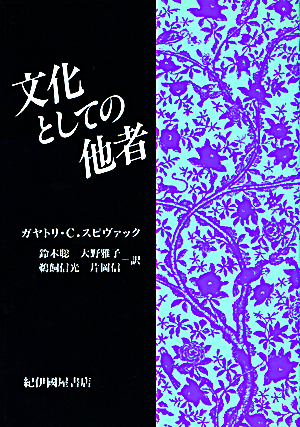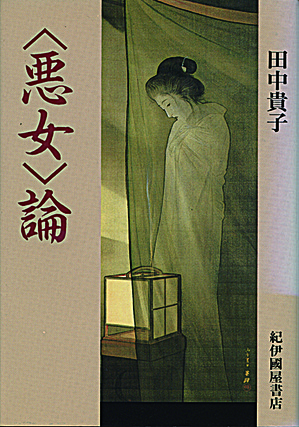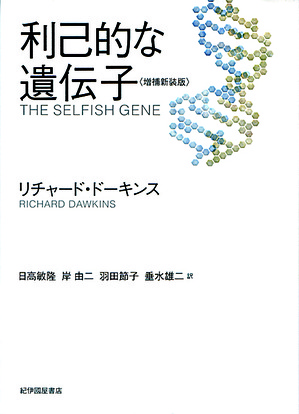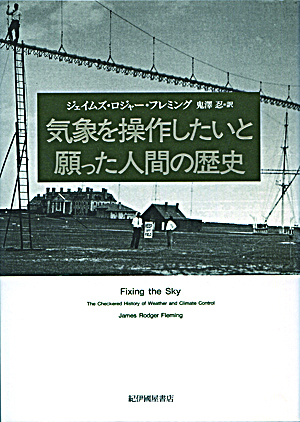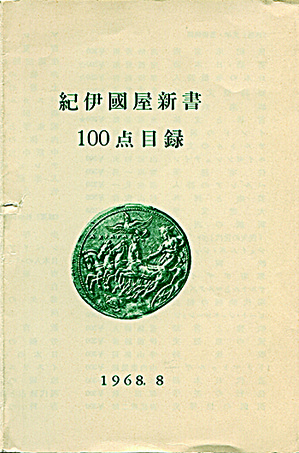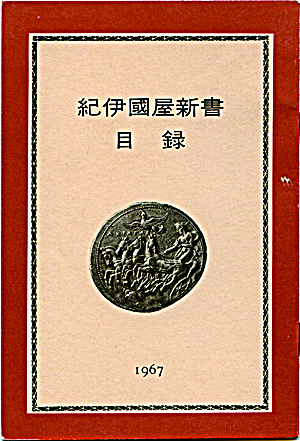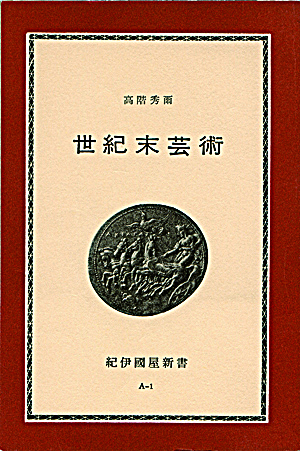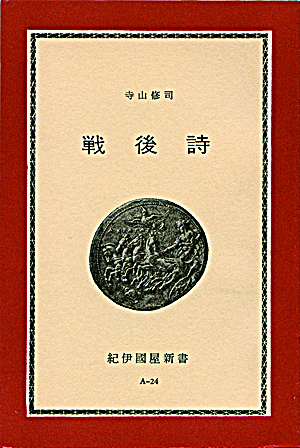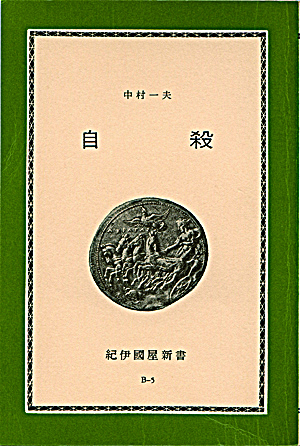紀伊國屋書店出版部は60周年を迎えました。 - essay -

2015年11月、紀伊國屋書店出版部は60周年を迎えます。
紀伊國屋書店は1927年に創業、戦前から『文藝都市』『行動』といった雑誌や単行本を刊行しておりましたが、現在に続く出版部は1955年に創設され、テンジン『ヒマラヤの男』で本格的に出版活動を開始しました。
この秋、全国の紀伊國屋書店とご協力書店で記念フェアを開催を予定しておりますので、ぜひ足をお運びください。
|
essay
文化産業としての出版と書店
上野千鶴子(社会学者)その昔、書物が文化の精華であり、書店が文化の発信地である時代があった......といえば、ノスタルジックにすぎるだろうか?
六〇年代から七〇年代にかけての紀伊國屋書店新宿本店は、その意味でとくべつな地位を占めていた。書店内に喫茶店があり、劇場があった。名物店主の田辺茂一さんには『わが町新宿』などを含むいくつもの著作があり、蝶ネクタイの似合うダンディな風貌で「文化人」のシンボルだった。ヒッピーのたまり場として有名な風月堂、そして相馬黒光(こっこう)らアジアの民族解放運動のパトロンがいたことで歴史的に由緒ある中村屋などと並んで、わいざつな街である新宿を、文化の薫りのある街にしていた。デートのまちあわせ場所は紀伊國屋で、といえば、遅れても許されることになっていた。店内には新刊や美術書など、見たこともないおびただしい書物にあふれていて、それを手にとるだけでいくらでも時間がつぶせたからだ。まだ携帯電話などというものがなかった頃の話である。
紀伊國屋はたんにできあがった商品を販売するだけの末端には甘んじなかった。みずから売りたい本をつくるべく出版部をつくった。その出版部が六〇周年を迎えるという。また著名人が選書するコーナーを期間限定で作ったりしたのも、あとから多くの書店が追随したが、紀伊國屋が先駆けのひとつではなかっただろうか。わたしも依頼を受けて「近代ニッポンの下半身」コーナーを引き受けたことがある。担当はやる気じゅうぶんの吉田敏恵さんという若い女性の店員さんだった。書物と読者の最初の接点である書店で、書店員のモチベーションがどれほど大事かは、「本屋大賞」の影響力の大きさからもわかる。
書物の書き手としては、編集者と出版社の貢献もなくてはならないことが身に沁みる。わたしのいくつかの書物は、編集者の執拗な(と言ってよい)慫慂(しょうよう)がなければ書かれなかったものだ。そのひとつが、『女ぎらい――ニッポンのミソジニー』(二〇一〇年)である。営業から編集畑に転身したばかりの女性編集者、有馬由起子さんに、ほとんど「コーナー際に追いつめ」られて書かされたようなものだ。本書は彼女が読みたい本、そして読者に届けたい本として編集者人生の記念すべき第一号となり、この本のおかげでそれまで「三十路に」としか漢字変換しなかった「ミソジニー(女性嫌悪)」というフェミニズムの用語は、日本社会に定着するようになった。ただちに韓国語訳と中国語訳も刊行され、このことばが東アジア圏に普及する効果を持った。
書物の著者を顕彰する賞はあまたあるが、編集者と出版社を顕彰する賞もあってよい、と思う。前者については新人物往来社が「青い麦編集者賞」というのを実施していた。いつも著者の黒衣(くろこ)の立場にいる編集者が顕彰を受ける機会があってもよいと思うが、一九九二年から二〇〇〇年まで九年間続いて、なくなってしまった。後者については、梓会出版文化賞という創設以来すでに三〇年を数える中小の良心的な出版社を顕彰する賞があって、斎藤美奈子さんなどと並んでわたしはその選考委員を務めている。二〇一〇年には紀伊國屋書店出版部も受賞した。年に一回の授賞式は、長年賞などに縁のなかった零細・中小の版元の経営者が、涙ながらに苦労話を披露する感動的な場である。彼らのスピーチに接するたびに、日本の文化水準は、こういう志あるひとたちの綱渡りのような努力で、ようやく成り立っているのだと感慨を深くする。
紀伊國屋刊とは意識していなかったが、大きな影響を受けていたのが、シオランの『生誕の災厄』(一九七六年)だった。母語を失って外国語で自己表現しなければならない亡命者の嘆きを呪詛しつづけたシオランの立場は、男言葉しか自己表現の手段がなかった頃の、フェミニズム以前の高学歴女たちの嘆きとそのまま重なった。その後、九〇年にはスピヴァクの『文化としての他者』がいちはやく訳され、この本も手にとっていた。スピヴァクは「服従が抵抗になり、抵抗が服従になる」ポストコロニアルな状況のもとで、「敵の武器をとって闘う」ことを教えてくれた。
感心したのが田中貴子の『〈悪女〉論』(一九九二年)と川村邦光の『オトメの祈り』三部作(一九九三~二〇〇三年)である。前者は男性社会が脅威に感じる女が歴史的に「悪女」とレッテルを貼られ、そこにはつねに性的過剰がつきまとうことを明快に論じて、フェミニズム批評の切れ味を中世文学の分野で示した快著、後者は戦前女性誌の「読者のお便り」コーナーに目をつけて「女の近代」を論じるという着眼点のよい怪著。男だてらに、と「してやられた!」感があった読後感を、そのまま書評に書いた。
たしかに出版は文化だ、と言いたいが、その文化産業が大きな転機を迎えている。わたし自身が「女性のためのプラットフォーム」ウィメンズアクションネットワーク(WAN)というウェブ事業に乗りだしてみて、印刷メディアの時代が終わりつつあることを肌で感じている。紀伊國屋書店は日本近代の「産業遺産」のひとつ、になるのだろうか。
essay
ポピュラーサイエンスのいろいろ
池内 了(宇宙物理学者)私がポピュラーサイエンスものとして最初に書いた本は『泡宇宙論』(海鳴社、一九八八年)である。宇宙は銀河でできた泡が連なっているという空想的な理論を出したのだが、実際の観測と比べて圧倒的にサイズが小さいため、まさに「泡と消えた」理論になってしまった。しかし、「泡」というキーワードで宇宙の森羅万象を議論すれば面白いだろうと思い直して書いた本である。 泡は「うたかた(泡沫)」と言われるように寿命の短い「あぶく」に過ぎないのだが、実は内部に逞(たくま)しさを秘めているという、矛盾を孕(はら)んだ危うい存在であることを地上のシャボン玉から宇宙全体に広がる泡まで見渡してまとめたものである。『泡のサイエンス』(シドニー・パーコウィッツ著)が翻訳出版されたのが二〇〇一年で、世界には同じようなことを考える人間がいると思ったものである。
これは物理現象としての自然の姿だから、東洋でも西洋でも同じように宇宙を泡の形として描くのだが、宇宙そのものの成り立ちや運動・来し方の歴史についての見方となると東洋と西洋で大いに異なる。そして、それをはっきりと意識するのは、自分たちの理論が標準となっている西洋の人間ではなく、亜流として無視されがちな東洋の人間であるのは確かだろう。その代表が宇宙観で、荒川紘が書いた『東と西の宇宙観 西洋篇』『東と西の宇宙観 東洋篇』(ともに二〇〇五年)に見るように、西洋の時計仕掛けの機械的宇宙に対し天行不斉(天は気まぐれに変化する)の変動的宇宙と考えたのが東洋であった。時間論で言えば、一直線に進む時間の西洋に対して循環する時間を生きるのが東洋で、それらは哲学思想にも大きな影響を与えてきた。
そういえば西村三郎の『文明のなかの博物学』(上下巻、一九九九年)でも、日本人であるからこそ見える東洋と西洋の博物学の歩みの違いが読み取れる。一八世紀後半からブームになった西洋の博物学はリンネの分類学を基礎とした「自然の体系化」とビュフォンの人間の自然認識を基礎にした「自然の歴史化」という壮大な二大潮流から出発した。他方、日本では薬物に関わる中国から輸入された本草学から出発し、江戸時代において動植物の品種改良ブームから名物学や物産学に広がったのだが、それはあくまで博物趣味に終始しており博物学にまで進展しなかったという歴史がある。
宇宙論や博物学だけでなく、科学の発展におけるこのような西洋と東洋の差をどう考えるべきなのだろうか。私は今、比較文化論の立場で、学問の過去と未来を考えてみたいと思っている。
とはいえ、私の見方では、現在の科学を描いたポピュラーサイエンスの分野では圧倒的に日本人より西洋の作家に軍配が上がるのは確かなようである。科学の分野ではもはや西洋・東洋の区別なく普遍化の道を歩んでいるのだが、それを噛(か)み砕いて易しく語って社会に伝えるという伝統は西洋がずっと卓越しているためだろう。日本でもあちこちで開かれるようになったサイエンス・カフェはイギリス発祥だし、日本では売れ行き不振で休刊になったサイエンス・マガジンはアメリカの空港の売店で今も売られている。西洋では科学が市民の対話の話題となる光景は珍しくないのである。そこにポピュラーサイエンスが重要な役割を果たしているのだ。それらの素晴らしい著作の翻訳が出版されるのは喜ばしいことである。
なかでも、『利己的な遺伝子』(増補新装版、二〇〇六年)のリチャード・ドーキンスや『やわらかな遺伝子』(二〇〇四年)のマッド・リドレーなど、生物学関係の優れた文才を持つプロの科学者の作品は印象深く、専門を越えて読もうという気にさせる。科学者らしく現象の本質を捉えた記述をしているからだろう。他方、私の専門に近い物理学関係ではいわゆるサイエンス・ライターの秀作が多い。その理由の一つは、ライターたちは長い学問の歴史を含めて幅広く勉強しており、取り上げたテーマについて過不足なく語り尽くしているためではないだろうか。例えば、リチャード・ローズの『原子爆弾の誕生』(上下巻、一九九五年)は、原爆の原理やそれらの開発過程だけでなくヒロシマの惨状やナチスドイツの原子力研究の実態まで著者の推測を交えて描き切っていて、ほとんど古典となっていると言えよう。同著者による『原爆から水爆へ』(上下巻、二〇〇一年)も力作である。
もう一つの理由は、ライターたちの嗅覚の鋭さで、今後大きな論争になりそうな問題や注目を浴びそうな事柄を世間に先駆けて取り上げ、考えるべき点を鋭く指摘していることである。『気象を操作したいと願った人間の歴史』(ジェイムズ・フレミング著、二〇一二年)では、呪術師やペテン師が暗躍した雨乞いの歴史を振り返りつつ、現在地球温暖化を解決すると喧伝している「地球工学」と呼ばれる研究を取り上げ、その倫理的問題点を告発している。また『オープンサイエンス革命』(マイケル・ニールセン著、二〇一三年)では、インターネットが普及した現代、誰でもオンラインネットワークで研究に参加できる「開かれた科学」の可能性を検証しており、私が主張する「等身大の科学」とも相性がよい。
科学がより広く市民のものになるため、ポピュラーサイエンス本出版の重要性は揺るがない。今後も良い本を提供して欲しいものである。
essay
ユニークなテーマ、若い書き手による紀伊國屋新書
岡崎武志(ライター、書評家)紀伊國屋書店は一九二七年の創業以来、ずっと出版も手がけてきた。戦前に出版部を一時立ち上げるが、その後解散。戦後になって、五五年より再び、出版に力を入れるようになる。
そんな中で生まれたのが「紀伊國屋新書」であった。創刊は一九六三年。新書は、三八年に岩波書店が創刊し、五四年の伊藤整『女性に関する十二章』のベストセラーにより出版界に領地を拡大していく。同じ年にカッパ・ブックスも創刊された。新時代に求められた知識と教養を、廉価でスマートな判型で供給する「新書」は、学生やサラリーマンを中心に大いに受け入れられたのである。
ただし、『女性に』は判型こそ「新書」だが、中央公論社刊で、中公新書とは名乗っていない。中公新書は一九六二年に、六四年には講談社現代新書が創刊され、常時百種ほどが乱立する新書ブームが起こり、以後現状に至る。この波に乗って生まれたのが紀伊國屋新書であった。前後して出てきた中公新書、講談社現代新書と似た印象を持つのは、いずれもビニールカバーがかかっていたからだ(のち、カバー装に)。
紀伊國屋新書の記念すべき第一号は高階秀爾(たかしなしゅうじ)の『世紀末芸術』だ。これはよほどよく売れたのか、昭和五十年代に京都の大学生だった私も、古本屋の棚でしばしば見かけたものだ。手元にあるのは、その初版で、古本屋で買ったものに違いない。当時、接着剤ではなく糸綴じであったためか、半世紀経たいまも、ページははずれずビクともしない。灰色の帯がかかり、久しぶりに見ると青春時代の古本屋の棚を思い出す。
「発刊のことば」には「大きな変革と危機が併存する現代。そこに生きるわれわれがもつ共通の意識をたずねて紀伊國屋新書はスタートする(以下、略)」とある。一九六三年は日本初の高速道路、名神(栗東~尼崎)の開通、新千円札(伊藤博文肖像)の発行、ケネディ暗殺と、たしかに「変革と危機」の時代だった。ベストセラーは山岡荘八『徳川家康』、岩波書店『日本の歴史』など。人々が求める「本の力」も生きていた。
奥付を見ると、発所所(ママ)「紀伊國屋書店」の住所は「東京都新宿区角筈(つのはず)1の826」となっている。現在、紀伊國屋書店本店のある新宿三丁目、及び広大な淀橋浄水場のあった西新宿のあたりは、当時「角筈」という町名だった。なお、出版部の住所は「千代田区五番町12番地」。いまのJR市ヶ谷駅近くか。定価は二百五十円。一九六三年の公務員初任給が一万七一〇〇円。日本橋「たいめいけん」のカレーライスが百二十円。そう考えると、いやに高い気がする。むしろ本の値段が上がっていないと考えるべきか。「分類」は当初、A(赤)が文学・芸術、B(緑)が社会、C(茶)が自然と分けられていた。わが本棚から、紀伊國屋新書を何冊かかき集めてみたが、ほとんどが「A」の分類だ。学生時代は純情な文学小僧だったから、これは仕方がない。目立つのは福田定良『娯楽映画』(一九六三年)、山田和夫『エイゼンシュテイン』(六四年)、冨士田元彦『現代映画の起点』(六五年)と、「映画」本があること。いまでは、映画、ポピュラー音楽、マンガ、鉄道などについて、新書が扱うのは珍しくないが、一九六〇年代、いわゆるサブ・カルチャーの世界は、新書からは遠ざけられていた。
紀伊國屋書店出版部は、後発の若い編集部だったはずだったから、先行する岩波新書が牙城とする「教養主義」から自由でいられた。書き手の方も、若い表現者、少壮の学者などをどしどし起用し、彼らが執筆に奮起するようなテーマを与えたことで生きのいい叢書ができあがったのである。
のちに、講談社文芸文庫から復刊される寺山修司『戦後詩』(一九六五年)も、そんな生きの良さを感じる企画だ。寺山はこの時、まだ三十歳に手が届かず、短歌や詩、ラジオドラマでようやく名前が知られ始めた頃だ。高階秀爾だって、『世紀末芸術』を出した時、まだ三十一歳で、国立西洋美術館に勤務する傍ら、東京大学で講師をしていた。全体に、三十代前半で、まだ著作の数もそんなに多くない執筆者が多かった、という印象が紀伊國屋新書にある。
文学・芸術以外でも、中村一夫『自殺』、石川元助『毒矢の歴史』、伊藤彊自(きょうじ)『スモッグ』(六三年)、岡野恒也『オラン・ウータンの島』(六五年)、なだいなだ『アルコール中毒』(六六年)など、異色かつ先駆的なテーマが、紀伊國屋書店出版部により世に押し出されていった。『斎藤茂吉』(一九七〇年)の著者・梶木剛が、本名・佐藤春夫と知ったのも、この新書であった。
※「紀伊國屋書店出版部60周年記念小冊子」(2015年10月1日発行、紀伊國屋書店出版部)より転載。書評は著者と掲載紙誌の許諾を得て転載、無断転載・複写を禁じます。