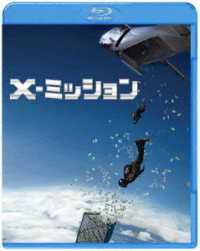内容説明
小学校低学年からの早期英語教育。譲歩に譲歩を重ねる外交。ポリティカリー・コレクトという「きれいごと」――すべて無駄! 流暢な英語と豊かな教養は決して両立しないし、外交での謙虚さは、弱みの裏返しとしか取られない。大切なのは、論理的思考力や教養力である。一見正しい定説を、軽やかに覆す「週刊新潮」人気コラム。(解説・金美齢)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mayumi
29
シリーズ第8作目。今作でも藤原氏は早期英語教育なんて無駄!と吠えております。ただ、藤原氏自身は英語ペラペラで、海外で多くの国の人と話すエピソードを読むたびに羨ましいなあ、と何度英語を勉強しても挫折する私は思うのです。あと今作は学術会議に言及あり。この本の内容は3〜4年前のものなのだけれど、今でもタイムリーな話題。「平和を高らかに唱える人は自らを高邁な人道主義者とみなし自己陶酔すると同時に、そうでない人を軍国主義者と見下す傾向がある」と、なかなか痛烈です。2021/02/14
さきん
25
久々の藤原本。文芸春秋でも冒頭の方に載っているので元気なのは間違いないのだが、奥さんの露出度が上がってきている気もする。経済観は大いに当たっている。本書はユーモアの大切さ特に強調されていた。空港での何かシャープなものはお持ちでないですかに対して、頭を指さすというのが、一番笑えた。2020/12/25
tomo
14
☆☆☆☆☆ 国語能力も?のうちから早期英語教育に疑問、日本学術会議の浅慮で無邪気な声明に落胆…etc。2017年の執筆とはいえ、古臭さを感じさせないのは、筆者の力量のせいか変化の遅い日本社会のせいか。話題も欧州旅行から、身近な信州での幼少体験と多岐に渡って、やっぱり看板エッセイですね! そもそも英語教育(というか英会話教育)は最低限知っておいたほうがいいけど、筆者のように外国人と会話する機会もそんなにないヒトに必要?2023/01/16
かりんとー
6
(図書館)ハードカバー版を読みました。時にユーモラス、時に辛辣な藤原先生。内容のひとつひとつは忘れても、藤原先生の生き方、考え方は私の心にずっと残るだろう。2020/12/05
CEJZ_
3
1P15行。元の本は2018年刊。「週刊新潮」の人気コラムをまとめた本で、2016年〜2017年のものを収録。藤原正彦の書籍は書店でよく見かけるような気がする。数学者、藤原正彦は新田次郎の次男なのか、知らなかった。このエッセイ集は面白かった。海外から見た日本、政治経済世相、郷里の信州のことなどなど。週刊新潮での連載は終了しているようだが、もっと早く知っていれば良かった。読みやすくなるほどなあと思う。人気があるわけだ。さかのぼって管見妄語シリーズや他の著作も読んでみたくなった。2020/10/26
-
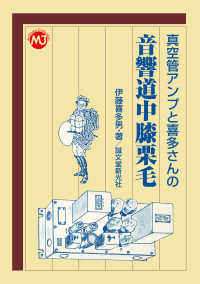
- 電子書籍
- 真空管アンプと喜多さんの 音響道中膝栗…
-
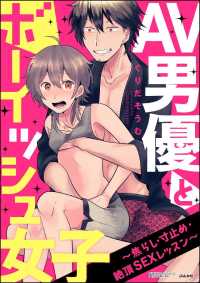
- 電子書籍
- AV男優とボーイッシュ女子~焦らし・寸…