内容説明
原書は昭和44(1969)年刊。「何を一番やりたかったのかというと、それは瀬戸内海の研究だったのです」――大学退職記念講演で語った宮本常一にとって、ふるさとの海=瀬戸内海は、日本を知る旅への原風景であり生涯の研究テーマであった。本巻では、矢野から福山・靹までの山陽地の沿岸と蒲刈島から田島まで広島県と愛媛県にまたがる芸予諸島の島々をたどる。かつて海賊も出た瀬戸内海の中でもっとも島の多いこの海域沿岸・島嶼社会がどのように現代へ展開してきたか、開拓・定住の歴史と生活手段の変遷、島と島外社会とのつながりを語る。地割に棲みつき方の特徴が映る空撮もふくむ写真277枚。
目次
1 呉線
2 三原
3 尾道
4 福山付近
5 靹
6 蒲刈島
7 豊島
8 大崎下島・大崎上島
9 大三島
10 伯方島から生名島まで
11 弓削島
12 生口島
13 因島
14 百島
15 田島・横島
あとがき
解説 海辺の街の長屋での日々(香月洋一郎)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
26
呉の東南の蒲刈島から大三島・伯方島など今のしまなみ海道の島々、そして鞆、尾道、因島までの瀬戸内海中央部をたどる。このエリア、頭の中に全然地図が入ってなくて、一つ一つ場所をたしかめながら読んでいくのがとても楽しい。◇塩、イモ、除虫菊、ミカン…この巻の中心は意外にも、漁業よりも「陸上がり」した人々の営み。近くの島の土地を海岸から山のてっぺんまで開き、船で耕しにいく農船などはじめて知った。僕らがみたら同じ船にしか見えないものも、宮本が見れば用途や来歴、造られた経緯などなど豊かな言葉があふれだす。今訪れたくなる。2016/06/30
KAZOO
19
日本の原風景を自分の脚と写真で書きつづったシリーズの、瀬戸内海の島々が中心となっています。1950年代の写真が多く、もう今は見られなくなってしまった景色が多いと思われます。貴重な写真が多くあると感じています。三原、尾道、鞆や大三島などを訪れた記録を多く残してくれた宮本さんの業績を少しづつチャレンジしていきたいと思っています。2014/07/19
HANA
12
芸予の海、ということで主に広島の瀬戸内海沿岸や島の暮しが描かれている。沿岸部は呉から三原、福山まで。福山、尾道は一度行った事があるので懐かしく読んだ。ラーメン食べるだけじゃなく草戸千軒くらい見てきたらよかった。島の部分はうって変わって人々の営みが中心。漁業や農業の変遷が中心だが、やはり一番に挙げられているのは過疎の問題。当時でこうだから現在は一体どうなっているのか。いつもにも増して考えさせられる事の多い巻であった。2012/03/08
takeapple
10
高度経済成長以前の貴重な姿が、博識の宮本常一の視点で描かれる。本当に民衆のためを思い、民衆の姿を記録しているんだなあ。日本は海の民のつくった国だと言えるなあ。現在どうなっているかみてみたい。2023/07/30
えいとうっど
1
極めて個人的なお気に入り度合い:★★★★☆4点 今はもう見ることができない美しい風景や民衆の暮らしを心に思い起こさせてくれる、素晴らしい著作。2018/05/04
-
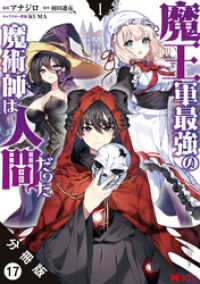
- 電子書籍
- 魔王軍最強の魔術師は人間だった(コミッ…
-
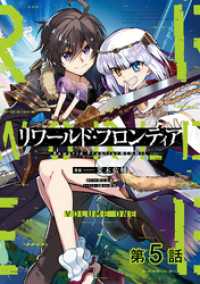
- 電子書籍
- 【単話版】リワールド・フロンティア@C…
-
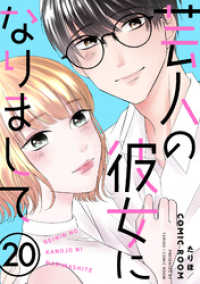
- 電子書籍
- 芸人の彼女になりまして 20 COMI…
-
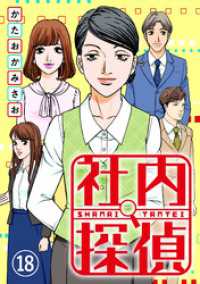
- 電子書籍
- 社内探偵(18) コミックなにとぞ
-

- 電子書籍
- 誰にも知られたくない 大人の心理図鑑




