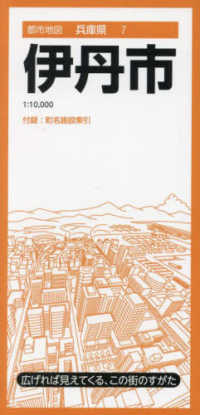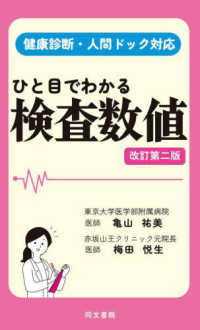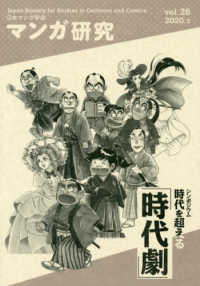内容説明
原書は昭和46年(1971年)11月刊。昭和36年、宮本常一は東京都府中市に家をもとめ、三田の渋沢敬三邸から居を移した。以後ほぼ20年、生涯を終えるまでの住処となったが、旅から戻りこの家にいるあいだに、時間があれば周辺を見てまわっている。一鍬一鍬おこして田畑にし、上水をつくり、道をひらき、ケヤキを植え、ほとんど人の住むことのなかった野を拓いて住み着いた人々がつくりだした武蔵野の風景の中をあるきながら、市に祭に集い寺社に詣でた人々のこころに思いをよせる。景観に映る往時の武蔵野の秩序とその後の変容の姿を写真308枚とともに語りつつ、宮本は言う「武蔵野人の心はいま失われようとしている」。
目次
1 府中付近の景観
2 武蔵野の開墾
3 道
4 庭木・生垣
5 すまい
6 農業
7 林業
8 民具など
9 墓
10 石の祈念碑
11 信仰
12 大国魂神社
13 府中祭
14 府中付近の社寺
15 青梅の町
16 青梅の寺
17 青梅祭
18 獅子舞
19 武蔵野と博物館
20 武蔵野開発に寄せて
あとがき
解説(香月洋一郎)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
33
宮本が東京で住んだ府中を拠点に歩き回った50年前の武蔵野。欅も楢も宮本好みの人の手の入った自然。作付けや家並みの景観から集落の成立過程や中世の人の動きを読み解いてくさまはやはりハンパない。不思議なのはそれがどこまでも旅人視点なこと。ほぼ同エリアでもきだみのるの内側からの目線とはまるで違ってそれもおもしろい。◇自分も今住んでる地域なのだが、しっかり見るとただの住宅地の無個性な街並みにも庚申さんや屋敷林の名残りがあって、道の向きやら整地の具合などに、宮本が見た歴史が残って見えるような思いがするのもおもしろい。2017/02/14
KAZOO
18
この写真集を見ると昔の面影など今はないように感じます。田舎の中の道や家並みなどが私もなつかしく思い出されます。農家の人の働く姿なども今とは異なっています。この宮本さんの本は、写真が大半を占めており貴重な資料ともなっています。2014/08/06
rouningyou
5
墓にも道具にも家の向きにも、書かれざる人々の歴史が反映している。失われつつある武蔵野の風景にため息をつきながら宮本常一はシャッターを押したのだろうと思いが伝わってくる。満州で死んだ少年たちをまつる石碑に憤りを覚え、死者の名を一人ずつ読み続けたという。武蔵野の旧来の秩序を壊したのは米軍の進駐、無計画な工場誘致だとしそれを砂漠化と呼んでいる。もう少し良い住み方があるはずだと言っているがそれも50年前。2014/10/21
HANA
4
武蔵野、特に青梅に関する紀行文であるが、随所に民俗学者らしい視点が見受けられる。武蔵野の風景とは人間が手を加えることによって作られてきたものであって、人が変ると風景もまた変らざるを得ないという一文にははっとさせられた。我々は何を得て何を失ったのか、ふと考えさせられる一冊。2010/08/09
かわかみ
3
二十年余前の転勤を機に、私も今では一端の武蔵野の住人となり、興味深く読んだ。水利に乏しかった武蔵野で江戸時代から開墾が進んだのは玉川上水の寄与するところが大きいという。宮本常一自身が府中に居をかまえるようになり、武蔵野を開いて来た民衆の知恵と努力を探る暖かい視線だけでなく、戦後のモータリゼーション等により武蔵野のよさが失われつつあった状況に注ぐ惜別の念も感じられる(本書の原本は1971年出版)。大國魂神社の存在感と青梅の豪族、三田氏の滅亡など印象深い歴史も語られている。江戸東京たてもの園にも行きたい。2021/05/16
-

- 電子書籍
- 女王陛下のペット5 MEQLME