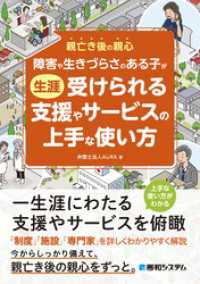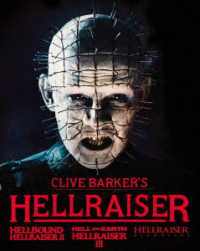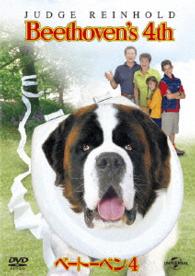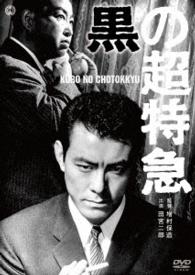内容説明
本書は聴覚理論の中心であるピッチ知覚の研究の19世紀から現在までの発展を,生理学的な背景を含めて解説した。音律の理論や音楽心理に関する章も含まれている。扱う分野は理工学,心理学,生理学,音楽教育学等にわたっている。
目次
1. 音の物理的性質
1.1 音と音波
1.2 音の時間波形
1.3 音のスペクトル
1.4 音圧と音圧レベル
2. 聴覚系の構造と機能
2.1 聴覚系の構成
2.2 外耳
2.3 中耳
2.4 蝸牛
2.4.1 蝸牛の構造
2.4.2 基底膜
2.4.3 有毛細胞
2.5 聴神経
2.5.1 聴神経の構造と機能
2.5.2 静的特性
2.5.3 動的特性
2.6 蝸牛神経核から内側膝状体までにおける神経核の構造と応答特性
2.6.1 蝸牛神経核
2.6.2 上オリーブ複合体
2.6.3 下丘
2.6.4 内側膝状体
2.7 純音刺激に対する応答の位相固定
2.8 変調伝達関数(MTF)
2.9 大脳皮質聴覚野
2.9.1 ヒトとサルのピッチ知覚特性
2.9.2 サルの聴覚皮質
2.9.3 ヒトの聴覚皮質
2.9.4 聴覚皮質ニューロンの特性
2.9.5 ピッチセンター
3. ピッチとは何か
3.1 ピッチの定義
3.2 ピッチの構造
3.2.1 ピッチのらせん構造モデル
3.2.2 ピッチと音色
3.2.3 ピッチの時間情報と場所情報
3.3 音楽的ピッチの諸特性
3.3.1 オクターブ類似性
3.3.2 音楽的ピッチの周波数範囲
3.3.3 音楽的ピッチを伝送する情報
3.4 無限音階
3.4.1 無限音階構成音のスペクトル
3.4.2 無限音階構成音に対する聴神経の反応
3.4.3 ピッチ比較判断の個人差とその要因
3.4.4 無限音階構成音を用いた旋律
3.5 オクターブ伸長現象
3.5.1 オクターブ伸長現象の実験データ
3.5.2 オクターブ伸長を説明する理論
3.5.3 多重オクターブの伸長幅
3.6 ピッチの音色的側面(音色的ピッチ)の特性
3.7 ピッチの単位「メル」とその問題点
3.8 周波数と空間的高さとの関係
4. 純音のピッチ
4.1 純音の可聴周波数範囲
4.2 周波数弁別閾
4.3 持続時間とピッチ
4.4 ピッチに及ぼす音圧レベルの影響
4.5 他音の存在によるピッチシフト
4.5.1 雑音によるピッチシフト
4.5.2 先行音によるピッチシフト
5. 複合音のピッチ
5.1 初期の聴覚理論‐時間説と場所説の論争‐
5.2 レジデュー理論の出現
5.2.1 Schoutenの実験
5.2.2 レジデュー理論
5.2.3 複合音の成分の周波数シフト実験
5.2.4 マスキング実験による場所説の否定
5.2.5 振幅変調音によるピッチ知覚実験
5.2.6 ピッチシフトの第1効果と第2効果
5.2.7 レジデューピッチの存在領域
5.2.8 結合音によるピッチシフトの第2効果の説明
5.3 差音と結合音
5.3.1 聴覚の非線形特性による結合音の発生
5.3.2 結合音の可聴性
5.3.3 結合音の大きさ
5.4 総合的聴取と分析的聴取
5.4.1 総合的聴取と分析的聴取の区別
5.4.2 聴覚フィルタ
5.4.3 部分音の分解性
5.4.4 総合的聴取か分析的聴取か?
5.4.5 聴取モードに及ぼす白色雑音の影響
5.4.6 純音の低調波ピッチ
5.4.7 部分音のピッチシフト問題
5.4.8 両極性周期的パルス列音のピッチ
5.5 総合的聴取によるピッチ
5.5.1 複合音の多重ピッチ‐純音とのピッチマッチング‐
5.5.2 ピッチの支配領域
5.5.3 基本周波数からのピッチシフト
5.5.4 音程判断における正答率
5.5.5 周波数成分間の位相効果
5.5.6 基本周波数の弁別閾
5.5.7 変調周波数の弁別閾
5.5.8 持続時間による周波数弁別閾の変化
5.5.9 ダイコティック聴取によるピッチ
5.5.10 分解されない倍音群の弁別
5.5.11 ピッチ知覚に及ぼす異なる周波数領域での干渉効果
5.6 雑音のピッチ知覚
5.6.1 雑音の断続と振幅変調の効果
5.6.2 くし形フィルタを通した雑音のピッチ
5.6.3 雑音による両耳ピッチ
6. ピッチ知覚モデル
6.1 自己相関モデル
6.2 パターン認識モデル
6.2.1 Wightmanのパターン変換モデル
6.2.2 Goldsteinの最適処理理論
6.2.3 Terhardtの周波数分析と学習の理論
6.2.4 パターン認識モデルへの批判
6.3 Mooreのモデル
7. 西洋音楽におけるピッチ問題
7.1 音高と音程
7.2 基準ピッチ
7.2.1 歴史的変遷
7.2.2 演奏における基準ピッチ
7.3 音律とは何か
7.3.1 平均律
7.3.2 ピタゴラス音律
7.3.3 純正律
7.3.4 その他のおもな音律
7.3.5 音程の数値化‐セントの計算法
7.3.6 ピアノの調律曲線と心理的評価
7.3.7 音階演奏における音程の測定
7.3.8 音律の心理的評価
7.3.9 平均律クラヴィーア曲集は平均律で演奏されたか?
7.4 絶対音感
7.4.1 絶対音感とは
7.4.2 絶対音感と年齢
7.4.3 絶対音感に関する実験的研究
7.4.4 絶対音感の問題点
7.4.5 移動ド唱法と固定ド唱法
7.4.6 高齢化に伴う音高の変化
8. 補遺と今後の課題
8.1 ピッチの定義の変遷
8.2 ピッチ知覚研究の今後の課題
8.2.1 時間情報の多様性
8.2.2 周波数の高い純音および複合音の音楽的ピッチ
8.2.3 上位ニューロンの神経インパルスの同期性の低下
8.2.4 最終的なピッチ判断
引用・参考文献
索引