内容説明
文部省唱歌という「新しき伝統」はいかにして生まれたのか。明治の「夢」を追う。
収録作『唱歌誕生』(1990年6月日本放送出版協会刊、1994年5月文春文庫、2013年5月中公文庫)は、明治期に志を抱いて上京した、あるいは大陸に渡った人々の絢爛たる群像の中に、唱歌「故郷」誕生のドラマを描き出した抒情的手法が光る作品。
長野県の小学校教師だった国文学者・高野辰之と、鳥取県の没落士族の家に生まれた作曲家・岡野貞一。この二人の偶然の出会いから、「故郷」をはじめ、「春がきた」「春の小川」「朧月夜」など多くの名曲が生み出されていった。文部省唱歌という「新しき伝統」はいかにして生まれたのか。人々を衝き動かした明治の「夢」とは何だったのか。二人の生涯をたどる旅を通して、明治という時代を浮き彫りにし、日本人の心に迫る一作。
本書には巻末に文庫にはない、猪瀬が郷里・長野の母校で行なった講演で、同郷の高野辰之にも触れた「国際化時代と日本人の生き方」(1996年10月12日「信州大学教育学部附属長野中学校五十周年記念講演」)のほか、本書の登場人物、大谷光瑞について語った「アジアという夢に取り憑かれた男」(『太陽』1991年6月号初出)を収録。作品解説としては、船曳建夫氏「ものを語る猪瀬直樹」(2002年刊『猪瀬直樹著作集第9巻』解説)と、高橋秀夫氏「作家的幸運と天分との融合」(文春文庫版解説)を収め、また、単行本刊行時に各紙誌に掲載された、井上章一、河村湊、池田満寿夫、音楽評論家・細川周平、作曲家・柴田南雄の各氏による書評も収録する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
41
前回取り上げた『やまと言葉で…』の著者竹内さんと猪瀬さんは同じ高校の同窓・同学年という。本を読むことの楽しみの一つに、そんな奇縁とも言う事柄がひょこっと顔を覗かせては、その意外な広がりに気づかされることがある。本書は、猪瀬さんが自分の故郷でもある北信濃を唱った島崎藤村の「千曲川旅情の歌」にある「濁り酒」の背景を探るところからスタートする。物語は、藤村、高野辰之、井上武子等の信州に繋がりのある人々から、大谷光瑞、岡野貞一といった明治から昭和に掛けて我が国の文化・芸術活動を支えた人々の足跡にまで、説き及ぶ。→2021/07/28
へくとぱすかる
27
「ふるさと」をはじめ、今も歌い継がれている唱歌のかなり多くを作詞した高野辰之、作曲の岡野貞一の生涯を中心に、大谷光瑞、島崎藤村の若かった時代が複雑にからんでいく。高野の姪にあたる人のロングインタビューが軸で、音楽関係の記述は少なめだが、清濁とりまぜての伝記が興味深い。この本が出たころは、まだ明治の人物を直接知る人が健在だった時代だったのか、と意外な思いがした。2017/01/17
-

- 電子書籍
- そばギャルとおじさん 分冊版(13)
-

- 電子書籍
- 男装騎士はエリート騎士団長から離れられ…
-

- 電子書籍
- 聖女は罪を赦さない 4話「王妃パリスの…
-
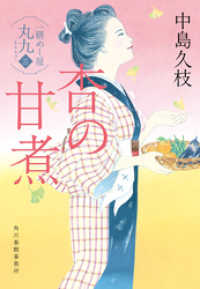
- 電子書籍
- 杏の甘煮 一膳めし屋丸九(三) 時代小…





