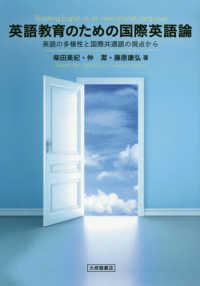- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
マルクスが自ら生涯の事業と呼んだ『資本論』.レーニンが“現世紀最大の政治経済学上の著作”と呼んだように,近代資本主義社会の経済的運動法則を徹底的に究明して,経済学を“革命”し,また人間社会に対する見解に完全な変革をもたらして,社会主義を科学的軌道に乗せた不朽の名著.ディーツ版による改訳.
目次
目 次
第三巻 資本主義的生産の総過程<sparenb/>続<sparene/>
第五篇 利子と企業者利得とへの利潤の分割。利子付資本
第二一章 利子付資本
第二二章 利潤の分割。利子率。利子率の「自然的」な率
第二三章 利子と企業者利得
第二四章 利子付資本の形態における資本関係の外在化
第二五章 信用と空資本
第二六章 貨幣資本の蓄積、その利子率に及ぼす影響
第二七章 資本主義的生産における信用の役割
第二八章 流通手段と資本。トゥックおよびフラートンの見解
第二九章 銀行資本の構成部分
第三〇章 貨幣資本と現実資本 Ⅰ
第三一章 貨幣資本と現実資本 Ⅱ<sparenb/>続<sparene/>
第一節 貸付資本への貨幣の転化
第二節 貸付資本に転化される貨幣への、資本または収 入の転化
第三二章 貨幣資本と現実資本 Ⅲ<sparenb/>結<sparene/>
第三三章 信用制度のもとにおける流通手段
第三四章 通貨主義と一八四四年のイギリス銀行立法
第三五章 貴金属と為替相場
第一節 金準備の運動
第二節 為替相場
第三六章 資本主義以前
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
逆丸カツハ
26
ああ、マルクス、あなたはなぜマルクスなの?って叫びたくなるレベルでわからない。自分で何を言っているかもよくわからない。2024/06/23
非日常口
18
「尊敬する人物は?」と問われれば「萬田銀次郎」と答えている。本書は利潤から利子付資本、銀行や信用の問題へと進むが「ミナミの帝王」や「闇金ウシジマくん」もおさえるべきだろう。貧困家庭とその子供の問題など、裏の世界は表が平和ボケたキレイゴトでクレンジングされるほど、黒く染まっていく。お金のニーズはそのままでサラ金規制法を行った世界も知るべきだ。ビットコインのようなデータのみで一般的等価物が成立するなら、インターネットによる実体なき友情・関係性も擬制資本の一部に取り込まれるのではないかというのが私の仮説だ。2014/12/24
またの名
14
「めっちゃ経営陣だって働いてるんだから加害者じゃないし対価は高くて当然」という幼稚な反論に資本主義システムの非人称性を示して訂正するのとはまた別の方法で、搾取構造を証明。労働者にとっての搾取される労働と労働者から搾取する労働が異なり、金を貸す貨幣資本家からすれば借りて経営する産業資本家は一種の労働者になる複雑な各要素の諸関係を読み解くため、一見よく似た利潤と利子の概念が調べ上げられる。金貸し業によって資本は再帰的に自分を創って自己増殖するかのような特別な商品へ昇格し、資本フェティシズムの幻影がここに完成。2019/11/08
中年サラリーマン
14
この巻は個人的には興味深かった。基本原則G-W-Gを使って話題はさらに深化する。貨幣資本家が登場。貨幣に対する多面的な視点を要求する。つまり「貨幣」を単に貨幣としてみるかそれとも資本としてみるかだ。これによって資本としての貨幣が余剰価値を生み出す。なんとなく金本位体制の崩壊を暗示するような内容に読めてしまったなぁ。2014/03/14
浅香山三郎
10
第3分冊の第5篇「利子と企業者利得とへの利潤の分割。利子付資本」を収める。銀行・金融・為替といふ、いまとさして変はらぬシステムのなかでの資本のうごきを分析する。第3分冊は、第2分冊よりも分かりやすい。これは草稿の整理度合にもよるのだらうが、第3分冊の扱ふ内容のイメージし易さからも来てゐるのだらうと思ふ。2024/06/23
-
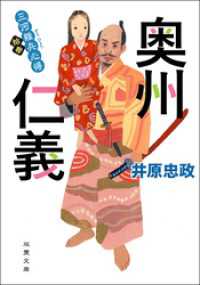
- 電子書籍
- 三河雑兵心得 : 13 奥州仁義 双葉…
-

- 電子書籍
- 気のきいた手紙が書ける本 - 「おつき…