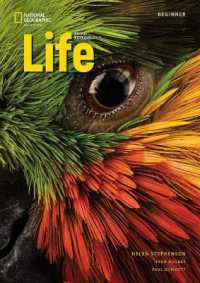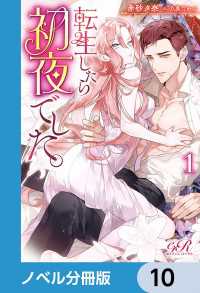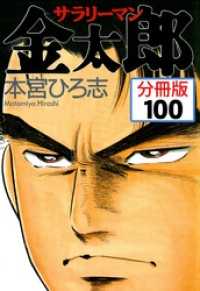内容説明
そういえば、あの本のこと、なんにも知らずに生きてきた。
一度は読みたいと思いながらも手に取らなかったり、途中で挫折してしまったりした古今東西の「名著」を25分間×4回=100分で読み解きます。各界の第一線で活躍する講師がわかりやすく解説。年譜や図版、脚注なども掲載し、奥深くて深遠な「名著の世界」をひもときます。
■ご注意ください■
※NHKテキスト電子版では権利処理の都合上、一部コンテンツやコーナーを掲載していない場合があります。ご了承ください。
■今月のテーマ
100の和歌に込められた日本人の心を、現代的な解釈でたのしむ!
勅撰和歌集の中から百人の歌を収めた『百人一首』は、私たちの中に最も広まり定着した古典の一つ。その魅力を『百人一首』や『万葉集』の英訳で知られる講師が、古典文学の基礎を踏まえ、自然や恋愛を詠み込んだ歌がどのように解釈・受容され今に至ったかをわかりやすく解説する。
■講師:ピーター・J・マクミラン
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
れみ
29
NHK-Eテレ「100分de名著」2024年11月のテキスト。飛鳥時代から鎌倉時代までの百人の歌を集めた和歌集「百人一首」について解説。学校の授業で和歌を勉強したときは、掛詞とかそういうのが難しくて苦手意識があったけど、久々に学び直して、限られた文字数で多くのものを描こうとする奥深さに触れることができて良かった。解説のピーター・マクミランさんが、もともと英語で詩を作る方だからこそ和歌の世界に惹かれ、百人一首を英語で楽しもうというところまでたどり着いているのがまた凄いなあと思った。2024/11/30
もえ
17
『百人一首』は遥か昔の高校生の頃かるた部に入って百首全て覚えたが、和歌の中身までじっくり味わうことは殆ど無かった。ピーター・j・マクミランさんは、西洋の詩との比較で外から見た和歌の魅力や、枕詞・序詞・掛詞・縁語・歌枕等の和歌の持つ技法的な魅力をわかりやすく解説していて、『百人一首』をあらためて読み返してみたくなった。『百人一首』は様々な形でリメイクもされていて、「超訳」も新しい試みとして面白いと思う。「日本人のアイデンティティ」としての『百人一首』はこれからも愛されながら新しい形で受け継がれていくだろう。2024/11/29
どりーむとら 本を読むことでよりよく生きたい
15
詩というものと散文の違いが分かったような気がした。詩とは言葉の美しさとリズムによって、文字を超えてさらに深い味わいを呼び起こすものだという説明は腑に落ちた。枕言詞、序詞、掛詞、縁語、本歌取りなどの技法を使いわずか31文字の中に世界を描いていることが説明されていた。恋の歌が多いけれども、わびしさなどを感じる歌、情景を鮮やかに描く歌などがある。私は、「大江山いく野の道の遠ければまだふみもみず天橋立」が才気あふれて好きです。日本語の素晴らしさを感じた。2024/11/12
GELC
13
源氏物語の回でも感じられた、古語を英語訳することで、改めて歌に込められた意味を認識できる体験が今回もあってワクワクした。超訳はすごく大胆な読み替え。番組も興味深く視聴できそうで楽しみだ。2024/10/31
さとまる
9
放送の第1回を観て購入。中一の時にカルタとして初めて百人一首に触れ、その後も正月によくやっていたけどそれぞれの歌をしっかり味わったことはなかった。放送を見て、この本を読んで、和歌はあくまでも「歌」であり文字ではなく耳で楽しみ味わうものであり、そのための枕詞であり序詞であり縁語であることを初めて理解した。現代のリメイクとして「超訳」が出てきたが、これが面白い。自分でもやってみたいな。2024/11/25