- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「本論を読み解く上で、これ以上に優れたシリーズは他に存在しない」(安藤礼二)
折口にとって「古代」とは単に歴史の時代区分を示すものではなかった。熊野への旅で光輝く大王崎を眼前にし、その波路の果てに「わが魂のふるさと」を感じたことを「かつては祖々の胸を煽り立てた懐郷心(のすたるじい)の、間歇遺伝(あたいずむ)として、現れたものではなかろうか」と記す。「古代研究」はまさに彼が実感を通して捉えた、古代的要素の探求なのである。全論文を完全収録する決定版!
解説・池田弥三郎/安藤礼二
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
49
全編興味深い所ばかり。著者の初の出版書籍。にもかかわらずその後の全てが収められている。全編是詩ともいえる「妣が国へ常世へ」から始まり、常世やまれびと、琉球神道に依代と、折口民俗学の必須ともいえるものが、全て詰まっているのは何とも凄まじい。解説によると最初に書かれたのは「髯籠の話」であるというが、そこにはもう神が依代によって降臨するという思想の骨格が出来上がっているしなあ。あと各編の書き出しが何とも言えず味わいがある。「妣が国へ常世へ」はいうに及ばず「若水の話」もまた。歌人、詩人の面目躍如といった所か。2017/08/04
ほうすう
12
難しい。読んでいてこんなになかなか頭に入ってこない文章も珍しい。特に最初の二編「妣が国、常世へ」「古代生活の研究」の常世論は抽象的な観念を語っていることもあり、もはやこれは奇書といっても良いのではないかとすら思った。 中盤以降の具体的な事象に絞って述べている方がまだ理解はしやすい。特に「髯籠の話」は興味のあることに対する熱量の強さを感じてどこか微笑ましさすら感じた。一応論文に属すると思うのだが文学的表現が多いものもいくつかあって、それもまた驚いた。2024/09/30
roughfractus02
7
言葉の意味が作る記憶は歴史となり(意味記憶)、情調の記憶は物語化されて個々人の記憶となる(エピソード記憶)。「言語情調論」を卒論とした著者は歴史を超えた「古代」を熊野の大王崎で直観する。「妣が国へ 常世へ」に始まる本書は「古代」の異郷意識を琉球のシャーマニズム、神道、各地方の民俗に見出す。他の部族社会との交流がこの世界と異なる長寿と豊かさに満ちた「常世」の観念を生み、その音韻から「常夜」へ共示化して時空の異なる世界へ変容するという過程を仮説する著者は、一方その世界を伝える媒介として水や貴種の探究に向かう。2025/03/08
∃.狂茶党
7
「史外」そう言った言葉も折口は検討してたそうですが、このサイコダイヴ的な、あるいは『賢者の石』で用いられた、精神的な時間旅行で、書物や、儀礼などから、神の問題に向かっていく行為は、詩的直感も相まって、学術的には微妙かもしれない。 (けど吉野裕子の方が大胆ですね) 「理会」竹中労の用いるこの言葉を、折口も使う。 理解よりも宗教的というか精神的な言葉、ロマンティックな意識だ。 ところで、依代って、折口が作った言葉なの? 歴史浅すぎる。2022/03/17
takeapple
6
折口信夫の民俗学は、柳田と比べるとカミ、巫女といった日本古来の信仰や呪術という側面が強い感じがする。ここでもやっぱり沖縄に行ったことが大きな天気になっているんだ。2024/10/26
-

- 電子書籍
- 後宮妃の管理人【分冊版】 74 FLO…
-
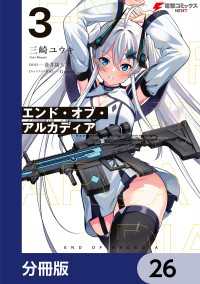
- 電子書籍
- エンド・オブ・アルカディア【分冊版】 …
-

- 電子書籍
- 第27話 50過ぎても、恋で変われる …
-
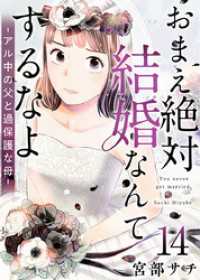
- 電子書籍
- おまえ絶対結婚なんてするなよーアル中の…





