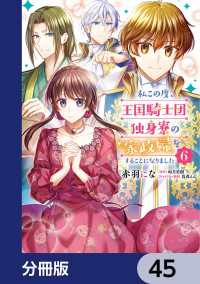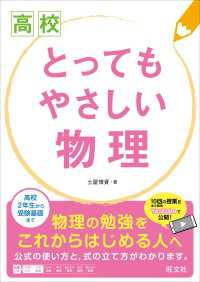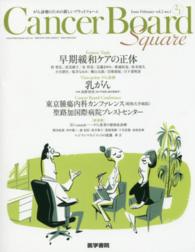内容説明
■調和力、象徴力、尊敬力。この三つの力が、日本人が教養によって培ってきた日本の文化力である。文化力で今こそ心の力をとりもどそう。すべての日本人に贈る珠玉のエッセイ第二集。
[目次]
第1章 営み
第2章 自然
第3章 生活
<著者略歴>
中西進(なかにし・すすむ)
一般社団法人日本学基金理事長。文学博士、文化功労者。平成25年度文化勲章受章。日本文化、精神史の研究・評論活動で知られる。日本学士院賞、菊池寛賞、大佛次郎賞、読売文学賞、和辻哲郎文化賞ほか受賞多数。著書に『「旅ことば」の旅』、『文学の胎盤』、『万葉を旅する』、『中西進と読む「東海道中膝栗毛」』、『国家を築いたしなやかな日本知』、『日本人意思の力』、『情に生きる日本人』(以上ウェッジ)、『うたう天皇』、『楕円の江戸文化』(ともに白水社)、 『日本人の祈り こころの風景』(冨山房インターナショナル)、『こころの日本文化史』(岩波書店)、『ことばのこころ』(東京書籍)、『中西進著作集』(全36巻/四季社)ほか多数。
※この電子書籍は株式会社ウェッジが刊行した『日本人の忘れもの 2』(2017年2月7日 文庫版第5刷)に基づいて制作されました。
※この電子書籍の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
neimu
35
学生の頃、卒論の参考に著者の本を読んで以来、殺伐とした仕事の合間に学術書など読むことはできなかった。だから、こういう軽いエッセイなら大丈夫だろうと。何故か1巻が見つからず2巻から読んでいるのだが、20年以上前の内容にも可からわず、普遍的な事柄、世界の古典から引用される様々な内容、先生の想いに触れて、しみじみとさせられる。こう、懐かしく語り合っているような、講義ではなく気軽に雑談をしているような、そんな語り口に引き込まれ、2時間ほどで読んでしまった。久々に暖かくくつろげる読書空間、蘊蓄に漂う心地よさ。2025/01/23
ひよピパパ
7
『万葉集』研究の大家、中西進先生が綴るエッセイ集。身の回りの生活や自然の中で何気なく使われている言葉を手がかりに、先人たちが培ってきた日本の文化力とは何であるかを問い直してくれる一書だ。氏の言葉に対する眼差しは実に鋭い。もう読んでいて唸りっぱなし。本書では「あめ」の項が面白い。「お下がり」には正月に降る雨の意があること。そしてそれは天の神様が人間への贈り物であること。また「五月雨」は「さ乱れ」であり、古典の中で、人の心をかき乱すものとして、物語の設定に用いられていること。とても勉強になった。2020/05/20
廊下とんび
5
この本は教えているのではなく自分自身で考える糸口を教えてくれているような気がした。『忘れもの』まさに普段気づかないこと、思いもしなかったこと・・・それに気づく目線、眼差しが『日本人の忘れもの』なのだと思う。目線、眼差しを変えれば見えてくるものも違って来る、当然気配りの仕方も違って来るだろう。『忘れもの』となってしまった気配り=思いやりについて考えたい2015/01/09
れいまん
3
人間の価値観はまず感動するところにある。感動出来るから良いのだという判断を日本人の特質としたのが本居宣長だった。この心情は古代人がごくふつうに持っているもの。儒学の建前につぶされそうになっている日本人の心情。宣長の提言は今なお充分に考えなおされるに値する。 まさに日本人の忘れ物を奥深いところから考察していていちいちが感動する2021/07/26
はまい
1
男尊女卑は最近の話で、古代では夫婦同伴で晩餐会出席を 命じていた話など新鮮。2018/10/07