- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
文明の誕生から現代まで、人類5000年の歴史をまとめる著者のライフワークの第三巻。1001年から1500年までを概観する。ヨーロッパでの十字軍の遠征、中国での宋の繁栄、モンゴル帝国の成立により、人類はグローバリゼーションを謳歌した。しかし、直後の気候不順、ペスト流行などによりモンゴル帝国は崩壊、明が中国を支配した。ヨーロッパではフィレンツェを中心にルネサンスが花開いた。
目次
第八章 第五千年紀前半の世界(一〇〇一年から一五〇〇年まで)
(1)宋と東ローマ帝国の繁栄(一〇〇一年~一一〇〇年)
宋の近代性
淵システムの誕生
さまざまな変化を生んだ唐宋革命
中国の周辺諸国の動き
聞き入れられた提言「万言書」──王安石の登場
整合性のとれた王安石の改革
イスラームのインド、アフリカ浸透とセルジューク朝の台頭
レプブリケ・マリナーレ(海の共和国)
ヴァイキングのイングランドへの侵入
東ローマ帝国の最盛期とノルマン人の南イタリア征服
叙任権闘争
カノッサの屈辱
東ローマ皇帝の救援依頼
(2)十字軍の時代(一一〇一年~一二〇〇年)
第一回十字軍あるいはフランクの侵略
中世の春
第二回十字軍
二つの王冠を被った王妃アリエノール
ホーエンシュタウフェン家の台頭
第三回十字軍
フェデリーコ二世の誕生
アリエノールの最期
宋の南遷
日本と中国の交易
第四回十字軍
ローマ皇帝フェデリーコ二世
第五回十字軍
ホーエンシュタウフェン家の終焉
フランス王妃ブランシュ
商人の誕生
(3)モンゴル世界帝国(一二〇一年~一三〇〇年)
モンゴルの勃興
インドのムスリム化
モンゴル世界帝国
モンケの即位
クビライの即位
銀の大循環
ヨーロッパの調停者、聖ルイ九世の十字軍出立
「真珠の木」シャジャル
イスラームの英雄、バイバルス
シチリアの晩鐘
クビライによる大都の建設
クビライの外交政策
クビライの死とその後のモンゴル帝国
(4)ペストの大流行と明の建国、百年戦争の始まり(一三〇一年~一四〇〇年)
ローマ教皇のアヴィニヨン捕囚
百年戦争の始まり
ペストの猛威
明の建国
暗黒政権、明
カール四世の金員勅書
相次ぐ農民反乱とハンザ同盟の成立
ティムールの進軍
(5)ルネサンスの世紀(一四〇一年~一五〇〇年)
鄭和の大航海
シスマの終結
百年戦争の再開
ジャンヌ・ダルクの登場
メディチ家の春
薔薇戦争
春の戴冠
一四九二年
一五〇〇年の世界のGDP
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Emkay
coolflat
こちょうのユメ
こちょうのユメ
井上裕紀男
-
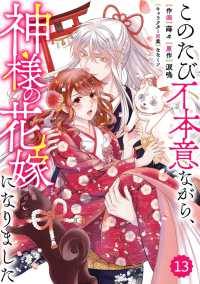
- 電子書籍
- Berry's Fantasy このた…








