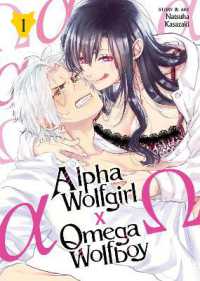内容説明
揺籠期を過ぎた西洋哲学は、ストア派、新プラトン派を経て中世へと進む。エピクロス、フィロン、トマス・アクィナス……。哲学者たちの苦闘の軌跡をたどる感動的名著・名訳の第三巻。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
44
読んだというよりも調べた。他レビューでトマス・アクィナスに割かれていないことが言及されているが、アウグスティヌスはそもそも哲学者として認識していないためわずかに触れる程度。アンセルムスやアベラール、スコトゥスやオッカムもおおむね均等に割かれているが、概略程度。イスラム教圏の医学との接点が言及されていて、アヴィセンナには一カ所だけ触れている。検索するためには電子書籍の方が使い勝手が良い。2025/12/29
またの名
12
ソクラテスが新しい原理を持ち込んでから、個人の主観に頼るストア派や万物は様々な原子の偶然的な結びつきにより構成されると論じるエピクロス派、確信を持って事物を突き崩す懐疑派が現れるも、ヘーゲルの目には食い違う信念同士の虚しい言葉遊びデュエルとは映らない。むしろそれら思考のすべてが全体として哲学そのものだと議論。全体論の偏重にも見えるけど、東洋思想やスピノザが求める自然実体への融即を断固拒否し、あるがままの自然な自分を肯定するのでなく逆に破棄する精神の否定の威力にこそ自由な人間が生まれるダイナミズムを認める。2017/09/04
tieckP(ティークP)
3
想像通り、ヘレニズムと中世・ルネサンスへの評価は高くなく、その意味で本書と1巻の後半は哲学を論じるためというよりは歴史を論じるために存在する巻。すでに他の方の感想で述べられているとおり、トマス・アクイナスなんて1頁ちょっとしかない。一方、ジョルダーノ・ブルーノなんかはヤコービが紹介したのを引いてそれなりに重視していて興味深い。キリスト教や新プラトン主義の三位一体を哲学に不可欠の要素とするあたりは僕にはその必然性が感じられないが、個性としては面白い。ともあれ力強くしかし虚勢のない素晴らしい講義だと思う。2018/04/13
植岡藍
2
ヘーゲルは歴史を一つの哲学の流れとしているようで、個々の哲学者は人間精神の哲学的な深化を反映して登場してきているような印象を受けた。だから懐疑主義などもその時点で人類にとって必要な思考の精神の過程のようで、その捉え方自体が面白い。2023/01/22
かっさん
2
ヘーゲル哲学史講義3やっと読み終わったー ギリシャ哲学から、キリスト教の関わりあたりまで。難しいけど流れがなんとなくつかめて、かつキリスト教の思想史上の関わりが見えてよかった #読書 #哲学 #めちゃ時間かかった https://t.co/TSlGupab552021/05/13
-
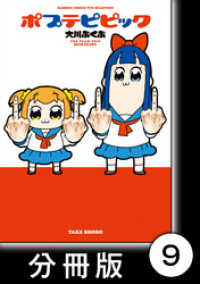
- 電子書籍
- ポプテピピック【分冊版】 (9) バン…