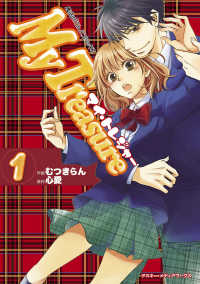内容説明
大学存立の危機が叫ばれる今日的課題をまえに、気鋭の論者が人文科学の未来を探る。いま〈大学〉は可能なのか。哲学・思想史に屹立する先哲の大学論を読みとき、現代の高等教育における制度的矛盾を炙りだす画期的論集。学問の歴史と現在がわかる文献リストを付す。
目次
はじめに――大学において私たちは何を希望することを許されているのか
第1部
第1章 秘密への権利としての哲学と大学――カント『諸学部の争い』における大学論(宮﨑裕助)
第2章 フンボルトにおける大学と教養(斉藤 渉)
第3章 世俗化された日曜日の場所――ヘーゲルにおける「哲学」と「大学」(大河内泰樹)
第4章 求道と啓蒙――ニーチェにおける哲学と大学(竹内綱史)
第5章 比較と責任――マックス・ウェーバーの学問論(野口雅弘)
第6章 ハイデガーの大学論(北川東子)
第7章 「ユダヤ人国家」の普遍性を追求したヘブライ大学の哲学者たち(早尾貴紀)
第8章 ジャック・デリダにおける哲学と大学(西山雄二)
第2部
第9章 欧州高等教育再編と人文科学への影響(大場 淳)
第10章 条件付きの大学――フランスにおける哲学と大学(藤田尚志)
第11章 高学歴ワーキングプア――人文系大学院の未来(水月昭道)
編者あとがき
「哲学と大学」に関する参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hika
4
カントからデリダまでの西洋哲学と大学について、そして新自由主義、グローバリゼーションと人文学について。人文学の「有用性」の議論はカント、ヘーゲルから繰り返され、最近の文科省通知にまでいたるということは、大学という制度と不可分なんだろうと思う。ただ、意識、人間に対する新たな視点が明確になっている今再考するあらたな余地、余白が産まれているのではないだろうか。あと、文脈まったく無視するけどヘーゲルの「人間が平日働き通すのは日曜日のためであり、日曜日をもつのは平日の仕事のためではありません」とある。味わい深い2017/01/03
鑑真@本の虫
0
印象として、短めの論文を集めた大学と哲学の関係性を知るための入門書という感じ。 個人的に興味を引いたのは、ユダヤに関することが書かれた第7章である。 ユダヤ的哲学解釈とユダヤ哲学の同一視は、哲学を知る障壁であると思う。 バイナショナリズムに関しての見解も興味深かった。2013/07/09