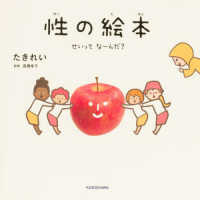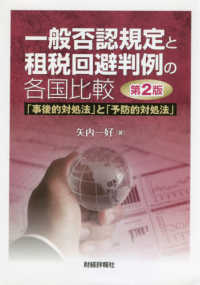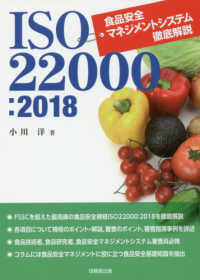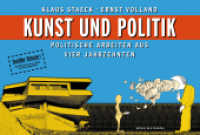内容説明
長年“きもの”三昧を尽してきた社会学者と、植物染料のみを使って“色”の真髄を追究してきた人間国宝の染織家。植物のいのちの顕現としての“色”の思想と、魂の依代としての“きもの”の思想とが火花を散らし、失われつつある日本のきもの文化を、最高の水準で未来へと拓く道を照らす。
目次
1 織ること/着ること(はじめに―展覧会の感想から;志村ふくみの前史;きものの喜び)
2 色の思想/きものの思想(色の思想;きものの思想)
著者等紹介
志村ふくみ[シムラフクミ]
1924年生まれ。紬織の重要無形文化財保持者(人間国宝)。1941年、母より初めて機織を習う。42年、文化学院卒業。55年、郷里の近江八幡にて植物染料による染織を始める。57年、第四回日本伝統工芸展に初出品で入選。翌第五回展から第八回展まで、紬織着物により連続四回の特選を受賞、65年の第九回展からは特待出品者となる。以後、染織作家として自然の恩恵を大切にした創作活動を行ない、日本の伝統技術である紬織を芸術作品に発展させてきた。86年、紫綬褒章受章。90年、紬織の優れた染織技術により国の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定。93年、文化功労者。著書も数多く、『一色一生』(求龍堂、大佛次郎賞)『語りかける花』(人文書院、エッセイストクラブ賞)ほか
鶴見和子[ツルミカズコ]
1918年生まれ。上智大学名誉教授。専攻・比較社会学。1939年津田英学塾卒業後、41年ヴァッサー大学哲学修士号取得。66年プリンストン大学社会学博士号を取得。論文名Social Change and the Individual:Japan before and after Defeat in World War 2(Princeton Univ.Press,1970)。69年より上智大学外国語学部教授、同大学国際関係研究所員(82‐84年、同所長)。95年南方熊楠賞受賞。99年度朝日賞受賞。十五歳より佐佐木信綱門下で短歌を学び、花柳徳太郎のもとで踊りを習う(二十歳で花柳徳和子を名取り)。1995年12月24日、自宅にて脳出血に倒れ、左片麻痺となる。2001年9月には、その生涯と思想を再現した映像作品『回生 鶴見和子の遺言』を藤原書店から刊行(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
双海(ふたみ)
Y
もあ
AnoA
koz
-

- 和書
- 本のちょっとの話