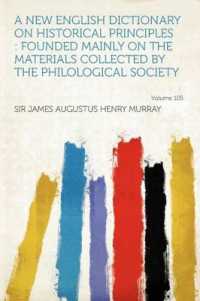内容説明
いま、日本の農業を取り巻く問題とはいかなるものか。本書は、研究者、実務家、ジャーナリストという多彩な執筆陣がユニークな視座に立ち、理論と実践の両面から解説するとともに、世界の多様な事例に照らし、農業の過去・現在・未来を考える。
目次
第1章 文化としての農業を考える―社会の大転換期に(食から社会を考える;農耕の誕生 ほか)
第2章 農業とはそもそも何であったのか―アグロフォレストリ、焼畑、水田漁撈が語るもの(「遅れた農業」への再評価;農耕を支えた森林―アグロフォレストリの考え方 ほか)
第3章 日本農業の地平線はどこへ―農業への基本的誤解を解く(大変化期の農業をコンサルタントとして見る;私の農業へのきっかけ ほか)
第4章 日本農業の未来を世界から考える―ジャーナリズムからの報告(ニューヨークとキエフで見たもの;食料高騰と政治 ほか)
著者等紹介
末原達郎[スエハラタツロウ]
1951年、京都府生まれ。龍谷大学農学部教授。同、農業研究所所長。京都大学名誉教授。京都大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士。専門は、生物資源経済学、農学原論、比較農業論。日本各地や、アフリカを積極的にフィールドワークし、文明論的視点から農業を考察する
佐藤洋一郎[サトウヨウイチロウ]
1952年、和歌山県生まれ。京都産業大学教授。総合地球環境学研究所名誉教授。京都大学大学院農学研究科修士課程修了。農学博士(1986年京都大学)。専門は、植物遺伝学。総合地球環境学研究所副所長をへて、現職
岡本信一[オカモトシンイチ]
1961年、東京都生まれ。農業コンサルタント。日本大学文理学部卒業。専攻は心理学。日本の農家や派米農業研修制度によるアメリカでの農業研修を経て帰国。種苗会社など農業関連企業を経て農業コンサルタントとして独立。鹿児島県を拠点にコンサルタント活動を続けている
山田優[ヤマダマサル]
1955年、東京生まれ。日本農業新聞専門編集委員。明治大学農学部兼任講師。同客員研究員。名古屋大学農学部卒業。東京農工大学連合農学研究科生物生産学専攻(博士課程後期)修了。1977年日本農業新聞報道部入社。2009年農業情報学会賞論文賞(農業情報学会総会)。フロリダ大学、テキサスA&M大学客員研究員(フルブライト奨学金)、環境ジャーナリストの会会員、日本農業経営学会会員。2009年6月1日第24回農業ジャーナリスト賞(共同受賞)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ようへい
葉
S.J.
-
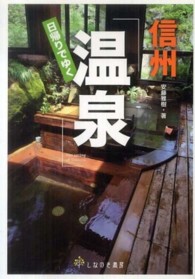
- 和書
- 信州日帰りでゆく温泉