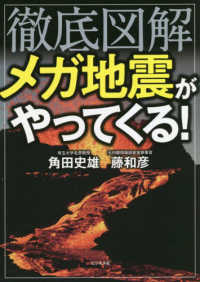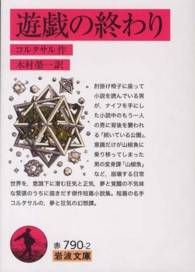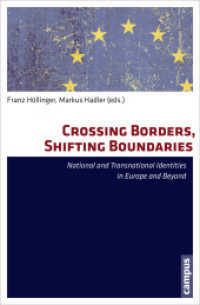出版社内容情報
北海道探検に明け暮れた日々とアイヌ民族との交流、道名・郡名制定に至るまで、武四郎の足跡と生涯を北海道の詩人の視点で探る。「北海道150年」の今、注目される幕末期の探険家・松浦武四郎〉
〈北海道を代表する詩人・更科源藏が描いた武四郎の生きざま〉
外交問題で緊迫した幕末期、未知の地であった北海道各地の探検を行い、数多の著作・地図を著して北方の現状を紹介した松浦武四郎(1818 ~88)。探検の中で多くのアイヌ民族と交流、明治維新後は道名・郡名制定にかかわり、「北海道の名付け親」として知られています。「北海道150年」の今年、注目される武四郎の偉業と生涯について、北海道を代表する詩人・アイヌ文化研究家の著者が、独自の視点で描き出した一冊です。※昭和48(1973)年7月に淡交社から発刊の『日本の旅人14 松浦武四郎』を復刻、リニューアルするもの。山本命氏が解説を執筆します。
更科源藏[サラシナゲンゾウ]
著・文・その他
内容説明
外交問題で緊迫した幕末期、北海道探検に明け暮れる日々とアイヌ民族との交流、そして明治維新後の道名や郡名の選定に至るまで、探検家であり、志士であった武四郎の足跡と生涯を、著者ならではの視点で探る。
目次
諸国遍歴の末、蝦夷地に渡る(幼少時代;放浪の青年時代 ほか)
目撃した未知の大地とアイヌの悲劇(『初航蝦夷日誌』―渡航の背後に水戸など諸侯の庇護;『再航蝦夷日誌』―北海道一周の壮挙を達成 ほか)
北方探検の日々とアイヌとの交流(『西蝦夷日誌』―幕吏として調査、探検に従事;カラフト・オホーツク紀行―激烈な探検行と向山源太夫の死 ほか)
探検の終結から開拓判官辞任まで(『東蝦夷日誌』初篇・二篇―念仏を唱えるアイヌたち;『東蝦夷日誌』三篇・四篇―アイヌの歴史と精神を偲ぶ ほか)
著者等紹介
更科源藏[サラシナゲンゾウ]
詩人・作家、アイヌ文化研究家。1904年、北海道川上郡弟子屈町に生まれる。麻布獣医学校中退。高村光太郎、尾崎喜八らに私淑し詩作を始める。1930年、詩集『種薯』を刊行。また代用教員をしながらアイヌ文化研究を進める。1951年、北海道文化賞を受賞。1966年北海学園大学教授、1967年『アイヌの伝統音楽』でNHK放送文化賞を受賞。北海道立文学館の初代理事長を務めた。1985年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。