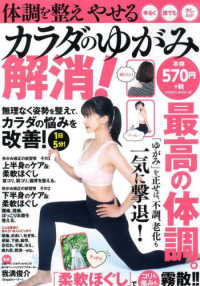出版社内容情報
2006年から2012年まで、朝日新聞に好評連載されたエッセイの単行本化。ノーベル賞作家は、中学生時代から老年の今日にいたるまで、人生の習慣としてさまざまな言葉を読み、そして書き写してきた。本書は、なかでも忘れがたい言葉の数々を、もう一度読み直す。
たとえば、フランスの哲学者であるシモーヌ=ヴェイユの「どこかお苦しいのですか?」。知的障害のある息子との暮らしのなかで、著者は常にこの言葉に支えられてきた。不幸な人間に対して、好奇心ではなく、注意深く問いかける。何気ないけれど重みのある一言。
あるいは、徳永進医師との対話で、鶴見俊輔が語った「まなびほぐす」。知識は覚えただけでは身につかず、それをまなびほぐしたものが血となり肉となる。小説家も「学び返す」「教え返す」という同じ作業をしているのだ。
ほかに『カラマーゾフの兄弟』でアリョーシャが病気で亡くなったイリューシャの埋葬において発した「しっかり憶えていましょう」、ヴァレリーの「精神の自由と、せんさいな教養が、子供への押しつけで壊される」、魯迅の「不明不暗『虚妄』のうちに命ながらえる」、そして源氏物語の一節から、チェルノブイリ原発事故の小説まで――六十数年、言葉を手がかりにして思索を積み上げてきた作家の、評論的エッセイの到達点。
内容説明
敬愛する言葉を書き写し、読み直し、自前の定義をする。源氏物語、ドストエフスキー、魯迅、レヴィ=ストロース、井上ひさし、人生のさまざまな場面で出会った忘れがたい言葉をもういちど読み直す。ノーベル賞作家の評論的エッセイの到達点。
目次
注意深いまなざしと好奇心
軌道修正を促した友人の目
滑稽を受容することとその反対
子供じみた態度と倫理的想像力
民族は個人と同じく失敗し過つ
読み直すことは全身運動になる
私らが繰り返してならぬこと
日本人が議論するということ
後知恵の少しでも有効な使い方
「学び返す」と「教え返す」〔ほか〕
著者等紹介
大江健三郎[オオエケンザブロウ]
1935年愛媛県生まれ。作家。東京大学仏文科卒。大学在学中の58年、「飼育」で芥川賞受賞。以降、現在まで常に現代文学をリードし続け、『万延元年のフットボール』(谷崎潤一郎賞)、『洪水はわが魂に及び』(野間文芸賞)、『「雨の木」を聴く女たち』(読売文学賞)、『新しい人よ眼ざめよ』(大佛次郎賞)など数多くの賞を受賞、94年ノーベル文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
寛生
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
味読太郎
壱萬参仟縁
梟をめぐる読書
-

- 和書
- ペンギン村に陽は昇る