内容説明
「デジタルファブリケーション」というデジタルデータをもとに制作を行う技術は製造からメディア,アートまで多岐にわたる領域で革新的な変化をもたらしている。本書では,その起源や技術,背景にある思想や今後の可能性を解説する。電子版ではカラー図面を豊富に掲載。
目次
第1章 ものの離散化とディスクリート離散的設計の可能性
1.1 デジタルファブリケーションとは何か
1.1.1 「デジタル」を捉え直す
1.1.2 広義のデジタルファブリケーション
1.1.3 ものづくりの民主化と分散型製造
コラム:オープンデザインの成熟
1.1.4 デジタルファブリケーションの拡張
1.1.5 狭義のデジタルファブリケーションへ向けて
1.2 「離散性」の意味と意義
1.2.1 クロード・シャノンによる「通信のデジタル化」
1.2.2 「製造のデジタル化」とは何か
1.2.3 最小単位を基本としたものづくりの歴史
コラム:東京2020オリンピック・パラリンピック表彰台
1.2.4 デジタルマテリアル
1.2.5 アーキテクテッドマテリアル
コラム:ボクセルモデリングとセルラーアーキテクテッドマテリアル
1.2.6 セルフアセンブリシステム
1.3 「地球環境問題」に向き合うためのデジタルファブリケーション
1.3.1 サンゴ着生具のデザイン
1.3.2 菌糸ユニットを用いた森のドーム
1.3.3 ジャイラングル構造体による都市冷却
1.3.4 「環境メタマテリアル」の可能性
1.4 デジタルファブリケーションと呼応する思想・美学
1.4.1 オープンシステムサイエンス
1.4.2 ハーネス計算
1.5 むすびに
第2章 出力物体の機能性に着目したコンピュテーショナルデザイン
2.1 コンピュテーショナルデザイン
2.1.1 コンピュテーショナルデザインとは
2.1.2 最適化問題とは
2.1.3 設計問題と最適化問題
2.2 デジタルファブリケーションにおけるコンピュテーショナルデザイン
2.2.1 デジタルファブリケーションにおける設計変数
2.2.2 機能性を最適化問題に組み込む方法
2.3 出力物体の機能性の種類と研究事例
2.3.1 出力物体の壊れにくさ
2.3.2 特定の用途で使う際の性能
2.3.3 利用時の使い心地
2.4 最適化の対象となる設計変数の種類
2.4.13 次元形状
2.4.2 物体表面の凹凸
2.4.3 部品の配置
2.4.4 微細構造・パターン
2.5 発展的な話題
2.5.1 機能性以外の設計指針
2.5.2 コンピュテーショナルファブリケーション
2.6 むすびに
第3章 インタラクティブなものづくり
3.1 身近になるものづくり
3.2 デジタルファブリケーションを取り巻くインタフェース
3.2.1 デジタルファブリケーションのプロセス
3.2.2 対話的なファブリケーション
3.2.3 デジタルファブリケーション装置の直接操作
3.2.4 対話的な3Dプリント:設計と造形の作業空間を重ねる
3.2.5 手作業を支援・拡張する道具
3.3 即興的なファブリケーション
3.3.1 高速化する3Dプリンタ
3.3.2 「プレビュー・プレタッチ」のためのファブリケーション
3.3.3 大きさや重さに着目したプロトタイピング
3.3.4 素材を使い回せる即興的造形手法
3.4 造形後に姿・形を変えるもののファブリケーション
3.4.14 Dプリンティング
3.4.2 造形後に膨らみ形を変える4Dプリント
3.4.3 「食べられる」4Dプリント
3.4.4 Unmakingと素材の経時変化を取り込むデザイン
3.5 ものの造形から変形を操るインタフェースへ
3.5.1 形状変化インタフェースとは
3.5.2 形状変化インタフェースのデザインスペース
3.5.3 形状変化インタフェースの現状と課題
3.5.4 ユーザー体験の設計と応用に向けて
コラム:エラーから広がる?デジタルファブリケーション表現
3.6 むすびに
第4章 パーソナルファブリケーション
4.1 初心者がデザインをすることは簡単か
4.2 プリンタ
4.3 3Dプリンタ
4.4 レーザーカッター
4.5 カッティングプロッタ
4.6 切削加工機(ミリングマシン)
4.7 刺繍ミシン
4.8 編み機
4.9 ヒューマンハンド
コラム:自分でデザインしてみたいものを身の回りで探してみよう
4.10 むすびに
引用・参考文献
索引
感想・レビュー
-
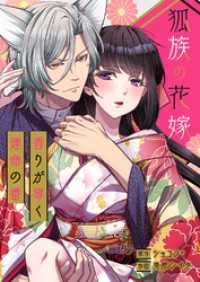
- 電子書籍
- 狐族の花嫁~香りが導く運命の番~【タテ…
-
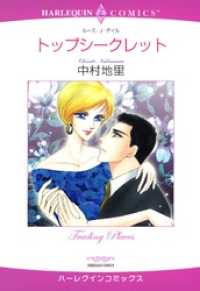
- 電子書籍
- トップシークレット【分冊】 5巻 ハー…
-

- 電子書籍
- ゲーセン少女と異文化交流【分冊版】 2…
-

- 電子書籍
- ちゃおデラックスホラー 2020年9月…
-
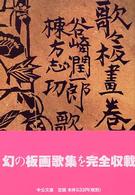
- 和書
- 歌々板画巻 中公文庫




