- ホーム
- > 電子書籍
- > 絵本・児童書・YA・学習
内容説明
日本人にとってお米とは、何なのでしょう? お米は、いのちのもとでした。お金のかわりでもありました。財産のかわりでもありました。お米をとる暮らしから、日本の田園風景が生まれました。お米がたくさんとれるよう、神様に祈り、祭りが生まれました。そして、水田は、小さなダムでもありました。水田の水は、ゆっくりと地面にしみこんで地下水となり、やがて下流で川に注ぎこんでいるからです。お米は日本の文化の土台でもあったのです。
ロングセラーノンフィクション、「生きている」シリーズの第4弾で、産経児童出版文化賞大賞を受賞した作品を、青い鳥文庫に初めて収録。自然や、人間のくらしの見え方がきっと変わる、小中学生から大人まで、必読の1冊!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
糜竺(びじく)
32
自分の家の近くにも田んぼがあるのですが、ありふれたものにしか感じていませんでした。しかし、非常に歴史があり、色々と緻密に考えて田んぼが存在している事を知った時には驚きでした。引用「用水は何キロ何十キロも、何百キロものびました。古い野川の後を利用した所もあれば、新しく掘った所もありました。何十年、何百年の間には、農民達は失敗の経験を生かしながら、水路をつくりかえていきました。小高い所にも水が流れるよう様々な工夫を重ねました。いつか水路は網の目のように大地を走り、金色の稲穂の波打つ平野が出現したのでした。」2017/08/29
mazda
21
縄文時代から弥生時代に変わった頃、稲作が盛んになったと考えられています。「これを主食に」と、天照大神がニニギノミコトに送ったのも稲穂でした。米は日本人の食生活はもとより、生活そのものに大きな影響を与えています。例えば、お祭り、祝日、寺社仏閣、日常生活そのものが稲作と共にあったと言えます。その大切さを知りながら、これからどうあるべきかをみんなが考えていく必要があるのではないでしょうか。2017/05/04
けいこん
14
「川は生きている」「森は生きている」に続いて読んだ。前2冊と重複箇所が多く、繰り返される「米が◎◎を作った。」にはちょっと強引でないの?と思われる記述もありましたが、大筋間違いはなく、良い本でした。”文明には農作物が不可欠”と絵本「ウェズレーの国」にもありましたが、日本に稲作が根付いたのは、先人たちの叡智と並並ならぬ努力の賜物であり、森と川と米はその全てが水で繋がり、森があるから川があり川を治めて米が獲れ、米を作る為に森を維持管理し川を治め、、、その流れの全てが文明を育て、今日の日本がある。・つづく2019/06/25
joyjoy
9
コメ関連。稲作が日本の自然風景や文化を作る土台となってきたことがよく分かる。あとがきのなかの「食糧輸入大国。それは地球環境問題からみれば、他国の土壌の略奪者であります。」という言葉にハッとする。食糧自給率の低さは、自国の問題だけではない。他国の土と水という資源を奪っているという見方を自分はしてこなかった。2025コメ問題も、地球規模の環境問題を含めたもっと大きな視点で考えていけたらいいな。2025/08/08
奏
9
江戸時代の字引きには「いねとは、いのちの根なり」とあるそうだ。米を作るために、人が動き、国ができ、文化が育ち、森や川も作られてきた日本の歴史。田んぼ一面のれんげの花、霜のおりた冬の田んぼを踏み歩いた感触、そして祖父母と一緒に田植えや稲刈りをした子どもの頃をたくさん思い出し、私の原風景も田んぼにあると感じる。簡潔でわかりやすい文章は、中学年から読めそう。2023/08/06
-
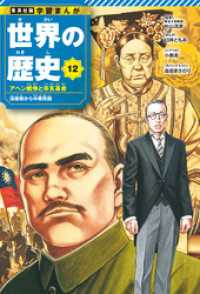
- 電子書籍
- 学習まんが 世界の歴史 12 アヘン戦…
-
![能なしと罵られた巫女は氷の王子に求愛される[1話売り] story01 異世界転生LaLa](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1860506.jpg)
- 電子書籍
- 能なしと罵られた巫女は氷の王子に求愛さ…
-
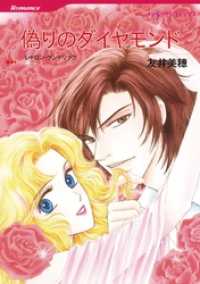
- 電子書籍
- 偽りのダイヤモンド【分冊】 8巻 ハー…
-
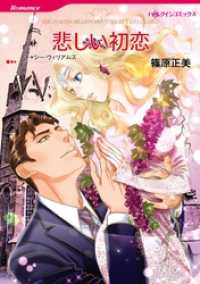
- 電子書籍
- 悲しい初恋【分冊】 12巻 ハーレクイ…
-
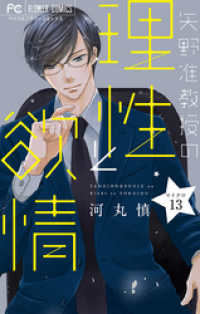
- 電子書籍
- 矢野准教授の理性と欲情【マイクロ】(1…




