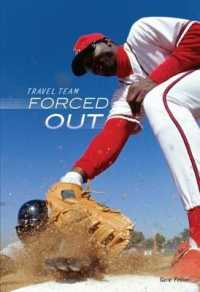内容説明
13万年前、ヒトはすでに死後の世界に関心をもっていた
ヒンドゥー教 、仏教、ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教──。世界の名だたる宗教が、どのように生まれ、広がってきたのかには、政治、人の移動、階級や奴隷制度など、歴史的事情との深い関わりがある。
5大宗教の紆余曲折をはじめ、古代の宗教、ジャイナ教やゾロアスター教、中国の儒教や道教、日本の神道、そして現代の新しい宗教などについても論理的に解説する本書は、世界を理解するための礎となる。
目次
1/誰かいるのか? 2/それぞれのドア 3/輪廻 4/唯一から多数へ 5/王子から仏陀へ 6/不殺生 7/放浪者 8/パピルスの籠のなか 9/十戒 10/預言者 11/終末 12/異端者 13/最後の戦い 14/世俗的宗教 15/行く道 16/泥土をかき上げる 17/個人的な宗教へ 18/改宗者 19/メシア 20/イエスがローマに至る 21/教会による支配 22/最後の預言者 23/帰依 24/奮闘 25/地獄 26/キリストの代理 27/抗議 28/大分裂 29/ナーナクの宗教改革 30/中道 31/獣の首をはねる 32/フレンド 33/アメリカ製 34/ボーン・イン・ザ・USA 35/大いなる失望 36/神秘論者と映画スター 37/門戸を開く 38/怒れる宗教 39/聖戦 40/宗教の終わり?
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サアベドラ
22
イェール大学が出している小史シリーズの一冊。著者はスコットランドの聖職者(元エディンバラ司教)で、宗教と現代社会に関する一般向けの本を書いている人物。ユダヤ教、キリスト教、イスラーム、仏教にヒンドゥー教など、東西の主だった宗教の興りと歩みを平易な言葉で記している。聖職者が書いているものの記述自体はかなり中立的で、モルモンやエホバの証人、サイエントロジーなどアメリカのキリスト教系新宗教も取り上げられている。内容が西欧に偏っている感は否めないが、入門書としては悪くないのでは。2019/10/20
ヒナコ
15
本書の約三分の二が古代から近世までの宗教史の解説が占められているのもあって、古代の仏教やユダヤ教、初期キリスト教の宗教の黎明期から、イスラム教勢力が勃興するのを経てキリスト教の宗教改革に至るまでの基本的な歴史が復習できた。キリスト教以外のさまざまな宗派が紹介されてはいたが、著者がスコットランド聖公会の関係者ということもあって、特にユダヤ教―キリスト教の記述が詳しく、世界史をおさらいするのにはちょうどよかった。→2022/11/05
まめ
8
宗教ごとの起源や歴史、特徴を非常にわかりやすくまとめている良書。特徴を挙げて終わりの本も多い中、カルト的な宗教まで取り扱いつつ冷静に批評されている。著者の宗教に対する造詣の深さに敬服。2022/05/09
makio37
8
三大宗教を中心にモルモン教やエホバの証人まで広く言及され、かつ40ある各章がそれぞれ面白く、飽きない。特に参考になったのは、アブラハム→イサク→ヤコブ(イスラエル)→12人の息子→エジプト移住、からのエジプト王家に拾われたモーセ…の流れを再認識できたこと。加えて、ヘンリー8世が兄アーサーの妻キャサリンと結婚→その侍女アンブーリンと結婚…からの、キャサリンとの娘メアリーとともにカトリック教会が復権し復讐(ブラッディ・メアリー)→アンブーリンとの娘エリザベスが継ぎ平和と安定…の流れを知れたこと。2019/07/07
雲
6
アブラハムからのユダヤ、キリスト、イスラムと繋がる宗教の流れを始め、仏教、ヒンドゥー教などの宗教的な思想が何故生まれ広まっていったのか書いた本。 死後の人はどうなるのかの不安、奴隷の解放、人の不満、エゴ、政治、巡り合いによって宗教は生まれ、分裂し続けた。宗教は虚構でありつつも救い、麻酔、幻にもなり得る。良い悪いでは無く、人はそれを求めるのだ。ただ、宗教を拠り所にしつつも、盲信してはいけない。立ち止まってその概念が意図していることは何か、自分なりに考えよう。世界で起こっている宗教を俯瞰して見る一冊。2022/03/20
-

- 電子書籍
- ライブダンジョン!【分冊版】 115 …