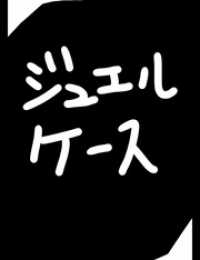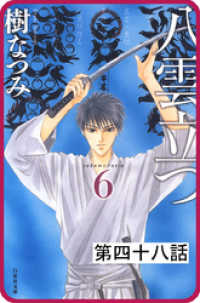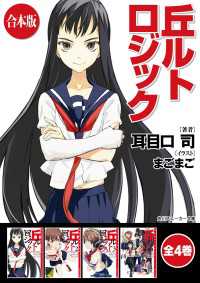内容説明
【和辻哲郎文化賞受賞作】城館にこもったモンテーニュはどのように思索の日々をおくったのか。想像を絶する冬の寒さ、夜の暗さの中、孤独を愛し、病に悩まされつつも、「エセー」初版を刊行する。自然、理性、運命の三要素と正面から向き合う彼の内面劇を緻密に描きつつ、中世ヨーロッパを読者の目の前に現出させる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NAO
46
サント・バルテルミーの大虐殺で多くのプロテスタントが殺され、王室の周囲では陰謀が渦巻き、騒乱は止みそうにない。だが、『エセー』からは、ボルドオの高等法院審議官の職を辞し、地の城館に戻ったモンテーニュが、フランスの政界でどのような役割を果たしたかをうかがい知ることではできない。当時の人は、彼のことをよく知っていたから、わざわざ書く必要もなかったのだ。そういった時代背景や彼の言動をが詳細に描かれたこの本は、何百年も後の世の他国の読者にとっては、本当にありがたい『エセー』を読み解くための手引書となっている。2016/04/23
風に吹かれて
13
1572年8月24日、フランスのカトリックがプロテスタントを大量虐殺。聖バンテルミーの虐殺と呼ばれる事件である。権力争いの構図が詳しく説明される。第二部の肝のひとつであろう。政治に宗教が利用されると、おそらく、確実に残酷で醜い争いが生まれるのだろう。そういった争乱の時代にミシェル・ド・モンテーニュは生きた。人間は理性を過信してはならない。長い人間の営みによって出来上がった社会の規の内に理性をとどめ、運命を強引に動かすことをしてはならぬ。懐疑主義者ミシェルの精神性が伝わってくる。2018/11/22
呼戯人
13
ボルドー市長など公職から30歳代で引退し、城館にこもってエセーを書き続けるミシェル。このような孤独な営みを人はどのようにして為しうるのか?ギリシア・ローマの古典を読み、それを縦横に引用しつつ書かれてゆくエセー。クセジュ、私は何をどの様に知るのかを繊細に書き綴ってゆく。信仰よりも理性の働きや思考の動きを捉えることに重きをおいた文章。モンテーニュの後からは、モラリスト文学やデカルトの合理論が生み出された。私たちの運命もこの良識や理性をどのように使うかという点に懸っている。2017/02/14
湿原
10
第二部の前半は16世紀フランスの日常生活の紹介、モンテーニュ家の状況について(ミシェルと妻・母との確執)。後半はヴァロワ朝末期の王朝内部と、悪名高い聖バルテルミー虐殺事件を詳しく描き、ミシェルが懐疑主義に到達した経緯を説明している。懐疑主義の記載については、『エセー』再読時に大いに役立ちそうである。第一部よりもミシェルの思想を深堀りするので、なかなか追いつくのが大変だったが、人間の判断というものが、哲学のように小難しい形からではなく、人間の習慣と日常から生み出されているものであることがよく理解できた。2023/11/14
Fumoh
8
第二部では主に悪名高い「サン・バルテルミの虐殺」の経緯が描かれ、モンテーニュの登場は序盤と終盤部分に限られます。ちょうど彼が著作を描き始めた頃であり、モンテーニュは世の動向とは関わっていなかったんですね。ここでも堀田氏の緻密な研究の成果が出ていて、さまざまな示唆を与えるものとなっています。虐殺事件の経緯に関しては、数世紀も前ということもあって紹介する本がなかなか手に入りづらく、また遠いヨーロッパの出来事というのもあり(宗教とかわけわからないし)、深く掘り下げようとする動機も我々には芽生えがたいものです。2025/02/19