内容説明
19世紀初め、20代の若い学者の兄弟が、ドイツ語圏に伝わるメルヒェンを広く蒐集してまとめた『グリム童話集』は、半世紀近い歳月、兄弟自身の手で改版が重ねられ、1857年、最後の第7版が刊行された。それは、国境を越え、時代を超え、今も生き続ける、他に類をみない新しい文芸の誕生であった。池田香代子の生命感溢れる翻訳による完訳決定版。第1巻には、「灰まみれ」「赤ずきん」「白雪姫」等、56話収録。〈全3巻〉
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Pustota
7
童話や民話には興味がありながらなかなか触れてこなかった。読んでみると、教訓が含まれていたりなんだか理不尽に感じられたりして面白い。有名な落語の元ネタらしきものがあったり。あと、悪者の処刑が軒並みえぐい。本当は残酷な…とか言われるゆえんか。繰り返されるモチーフやパターンがあるのも面白いし、キリスト教と関係ありそうな部分も興味深い。解説でグリム兄弟と童話、そしてドイツという国について触れられていたのも嬉しい。情景が浮かびやすいのも童話の良いところ。物語というものを考えるうえで、色々な示唆を与えてくれる。2020/01/26
ハチアカデミー
5
C 様々に形を変え、今なお語り継がれる民話の原典。勧善懲悪の物語が多いが、何を善・悪とするのかを知ることが面白い。人間の欲望や感情がはっきり表にでている。すぐに怨むし復讐するし殺すし。一方で、安易な解釈を拒む話も多い。KHM1蛙の王様や、56のルンペンシュティルツヒェンとか。また、「名付け親」や「取り替え子」といったモチーフに興味を持った。訳者による解説も秀逸。グリム兄弟が民話を集めた背景に、ナショナリズムがあるという指摘は、日本における柳田国男を考えると、納得が出来る。2012/01/14
鳩羽
2
本当は怖いグリム〜というのが昔流行ったけど、「本当は」なんてつけなくても普通に怖い。首やら腕やら胴体やら簡単にばらばらにしすぎ!しかもひょいひょい生き返りすぎ!という意味で怖かったです。似たような話が既にちらほら。類型化したパターンもちらほら。一つ一つは面白いけど、やっぱし「グリム童話」ってまとめられたのを読むといつも飽きてくる。一度にたくさん読むものではないのかもしれない。2010/10/03
なかち
0
継母は継娘をいじめる。美しい娘は王か王子と結婚する。賢い兄、馬鹿な弟みたいな対比。いい結果を羨んで真似するとひどい結果になるという対比。小人は手助けしてくれる。〇〇を見てはいけない。醜い人間がいいことをすると美しくなる。短所が長所に転化する。2011/05/28
楓
0
有名所が多くてすごく良かった
-
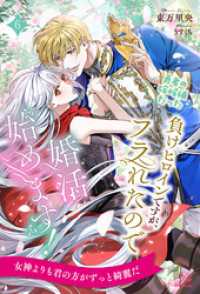
- 電子書籍
- 勇者の嫁候補だった負けヒロインですが、…
-

- 電子書籍
- ハズレ判定から始まったチート魔術士生活…
-
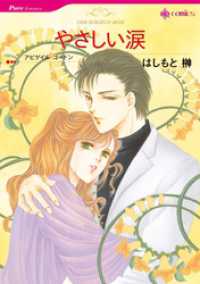
- 電子書籍
- やさしい涙【分冊】 8巻 ハーレクイン…
-

- 電子書籍
- 生徒会長の歪んだ愛情【マイクロ】【電子…
-
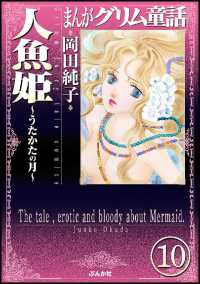
- 電子書籍
- まんがグリム童話 人魚姫~うたかたの月…




