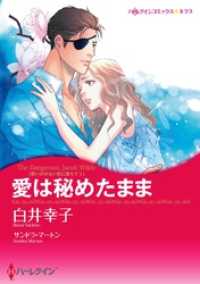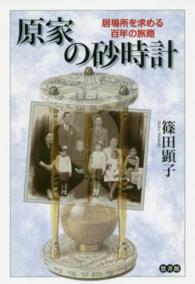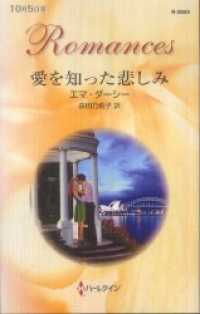- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
韓国では今日も、儒教の「教え」が日常生活の隅ずみまで深く浸透している。朝鮮・韓国で朱子学の受容を担ったのは両班階層であった。両班は官僚・知識人として李朝時代を通じ京師と地方の支配エリートであった。しかし両班は法制的手続きを経て制定された特権階層ではない。彼らは社会的慣習を通じ周囲から両班としての資格を認定された、相対的で主観的な階層であった。ではその資格とは? 両班の形成過程と儒教的伝統の実態を描く。
目次
序 現代に生きる儒教的伝統
第1章 両班―朱子学のにない手たち
第2章 在地両班層の形成過程
第3章 在地両班層の経済基盤
第4章 開発の時代
第5章 両班の日常生活
第6章 両班支配体制の成立
第7章 在地両班層の保守化と同族結合の強化
第8章 両班志向社会の成立
結び 伝統と近代
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shoji
38
朝鮮王朝は身分社会であった。 支配階級と被支配階級の身分の違いは天と地の開きだったそうだ。 支配階級を両班といった。知的官僚集団である。 そのため、民は両班になることに、そして両班一族は地位と権力を維持することに心血を注いだようだ。 その両班は単なる特権階級だけでなかった。 今日韓国の根底にある「儒教の教え」を根付かせたのもまた、両班である。 官僚が最も官僚らしくあったのは李朝時代かもしれないなと思った。2016/06/19
Tomoichi
22
韓国社会を理解する上で両班の存在は欠かせない。日本とも中国とも相違する李朝社会の特権階級両班をその成立と発展・衰退、社会に与えた朱子学と両班との関係など安東権氏を例に解説。考察する。本書でも指摘している通り、日本同様韓国も伝統と思われていることがそれほど昔から伝統ではないって事が面白い。韓国が伝統的儒教の国っていうイメージも覆されます。オススメです。2018/10/24
崩紫サロメ
20
朝鮮半島の「伝統」と思われがちな両班的価値観・生活理念が朝鮮半島の歴史としては極めて新しい18世紀以降の産物であるということを、在地両班・酉谷権氏に関する史料を通して解き明かしていく。両班が閉鎖的な特権集団と変わっていくのは17世紀後半以降、彼らの経済的地位が低下し始めてからで、同時に郷吏層が両班的な生活スタイルを自らのものとして取り入れていく。これは却って支配体制の安定をもたらし、儒教理念が農村部まで浸透していく。伝統と近代について考えさせられる名著。イギリスのジェントリとも比較してみたい。2021/11/22
おらひらお
4
1995年初版。奴婢層が人口の三割も占めている社会ではなかなか発展はないだろうと感じましたね。基礎的な両班の本だろうと思いますが、このレベルから結構難しかったです。2014/05/10
かずら
1
朝鮮半島の特権階級だった「両班(ヤンパン)」彼らがどのように暮らしていたのかを解説する本。特権階級と聞いて、なんとなく封建制度的なものをイメージしていたんですがだいぶ違いますね。当たり前ですが、「貴族的な存在」というものも国によってシステムが大きく違うんですよね。庶子への扱いの悪さはこの間見た韓国時代劇で表現されていたので思い出しながら読みました。しかし側室の子の扱いも時代によって変わってるんですね。つい昔の社会の仕組みはずっと変わらないものと考えがちですが、結構短いスパンで変わっているのだと思いました。2014/12/23