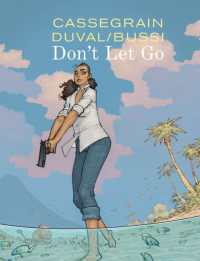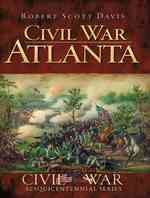目次
第1章 基礎編―訪問薬剤管理指導と保険請求(在宅医療に取り組む;在宅医療点数算定の実際とレセプト記載例;介護保険の要点)
第2章 実践編―在宅医療Q&A(在宅医療を始める;地域にPRする;患者・家族とのコミュニケーション;多職種連携・チーム医療)
第3章 応用編―主要な疾患・処置の対応(総論 特定保険医療材料、衛生材料の基礎知識;各論 主な疾患と処置の実際)
著者等紹介
串田一樹[クシダカズキ]
昭和薬科大学地域連携薬局イノベーション講座特任教授。高齢社会の到来によって薬局は在宅医療への参画が求められ、慢性疾患の高齢者から、がんの緩和ケアの患者まで、薬剤師は様々な状況にある在宅療養者を支えている。しかしながら、一方で、処方せんを断る薬局があるため、HIP(Home Infusion Pharmacy)研究会を立ち上げて、「処方せんを断らない」薬局の支援をしている
鈴木順子[スズキジュンコ]
北里大学薬学部社会薬学部門教授。1953年生。1990年、社会人から北里大学薬学部に入学。在学当時から、へき地(過疎地)の医療保健体系構築に関心を持っていたが、大学に残ったため、以後、患者のQOL向上を目的とした地域医療体系の再構築を検討してきた。ジェネラリスト薬剤師の視点を保つため、多領域の学科教育に携わっている。日本緩和医療薬学会理事、日本社会薬学会幹事、全国薬剤師・在宅療養支援連絡会監事、港区在宅緩和ケア支援推進協議会委員等
高橋眞生[タカハシマナブ]
株式会社カネマタカネマタ薬局代表取締役。東邦大学薬学部卒業後、数年の会社勤務等を経てカネマタ薬局に入社。2000年の介護保険制度発足に伴い、病院と連携して在宅訪問を開始するとともに無菌室を整備し、がん患者など在宅での療養が困難な患者の受け入れを進めてきた。現在、千葉県薬剤師会医療・介護保険委員として、社会保険支払基金・国保連合会で診療報酬審査委員。全国薬剤師・在宅療養支援連絡会理事・研修委員会委員長、日本緩和医療薬学会評議員、HIP研究会理事として、在宅医療関連の執筆や研修会講師を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
- 洋書
- Don't Let Go