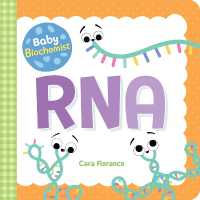出版社内容情報
本書の特色
1.地球レベルでの物質循環、エネルギー利用による環境破壊がバイオマス資源を中心に詳細に解説。
2.地球レベルでのバイオマス資源の現状と課題、さらにここ数年の日本におけるバイオマスとその廃棄物の発生量および利用可能量の推定量が掲載。
3.バイオマスと社会環境の関わりの中での有害物質について詳細に解説。
4.バイオマス変換技術とバイオマスエネルギー燃料について、その両面から超臨界流体技術などの未来技術も含めた形で詳細に解説。
5.バイオマスエネルギー燃料の研究動向と利用例がわかりやすく解説。
編著者
坂 志朗(京都大学 大学院 エネルギー科学研究科 教授)
執筆者
河本 晴雄(京都大学大学院エネルギー科学研究科 助教授)
笠原三紀夫(京都大学大学院エネルギー科学研究科 教授)
東野 達(京都大学大学院エネルギー科学研究科 助教授)
南 英治(京都大学大学院エネルギー科学研究科)
野渕 正(京都大学大学院農学研究科森林科学専攻 教授)
佐藤 卓司(ブラジル永大木材株式会社 原木・植林部長)
林 勇夫(京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻 教授)
上野 正博(京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻 助手)
羽生 直人(宇都宮大学農学部生物生産科学科 助教授)
上田 一義(横浜国立大学工学部物質工学科 助教授)
牧野 圭祐(京都大学国際融合創造センター 教授)
橘 燦郎(愛媛大学農学部生物資源学科 教授)
吉原 福全(立命館大学理工学部機械制御工学科 教授)
江原 克信(京都大学大学院エネルギー科学研究科)
鮫島 正浩(東京大学大学院農学生命科学研究科 助教授)
小木 知子(独立行政法人 産業技術総合研究所 グループリーダー)
宮藤 久士(京都大学大学院エネルギー科学研究科 助手)
木田 建次(熊本大学工学部物質生命化学科 教授)
益田 光信(株式会社タクマ 環境計画2部 部長)
斉木 隆(社団法人アルコール協会 研究開発部長)
坂井 正康(長崎総合科学大学工学部機械工学科 教授)
大野陽太郎(日本鋼管株式会社 環境ソリューションセンター主席)
Kusdiana, Dadan(インドネシア共和国 エネルギー資源省)
福田 秀樹(神戸大学大学院自然科学研究科分子集合科学専攻 教授)
中薗 豊(株式会社ロンフォード 常務取締役)
池上 詢(福井工業大学工学部機械工学科 教授(京大名誉教授))
山崎 稔(近畿大学生物理工学部機械制御工学科 教授(京大名誉教授))
発刊にあたり
我々の現代社会は、資源・エネルギーに大きく依存する大量生産、大量消費、大量廃棄の使い捨て消費社会である。このもの消費社会は大量のエネルギー消費によって支えられ、快適さのみを追い求めながら高度の経済成長と高い生活水準を作り上げてきた。その結果、いつしか"消費は美徳"の贅沢指向が定着した。そんな中で、地球規模での環境破壊が徐々に進み、温暖化現象や熱帯林の減少、酸性雨による被害やオゾン層破壊など、地球の環境は今や人類の生存をも脅かしかねない状況になりつつある。今後、世界 のエネルギー消費は人口増加と経済成長により、さらに拡大、膨張を続け、環境の悪化がさらに進むことが危惧される。
これらのエネルギー・環境問題を軽減し、子孫に負の遺産を残すことなく「持続可能な人類の発展」を成し遂げるため、本書では循環型、更新型資源であるバイオマスを取り上げ、その分野の第一線で活躍中の方々に執筆を依頼した。バイオマスを取り巻く現状を整理しながら未来社会を展望し、問題点を明らかにすることによって、読者がエネルギー・環境問題に関心を持ち、自らもそれらの改善に努めていただける座右の書となることを期待している。(坂)
目次
【第1章】地球環境とエネルギー
1.1 生態環境とバイオマス資源
1.1.1 地球の温暖化
1.1.2 地球の温暖化の生態系への影響
1.1.3 蝶の来る木
1.1.4 生態系の保護
1.2 物質循環とバイオマス資源
1.2.1 植物が創った地球生態系
1.2.2 地球上でのエネルギー・物質循環
1) 炭素循環の中でのバイオマス
2) 陸、海におけるバイオマス循環の相違
3) 森林生態系における物質循環
1.2.3 持続可能なバイオマス生産
1) 熱帯林の破壊とアグロフォレストリー
2) エネルギープランテーション
1.3 エネルギー利用による地球環境破壊
1.3.1 エネルギー利用と環境
1) エネルギー需給と大気環境破壊の推移
2) 各種エネルギーの環境破壊
1.3.2 地域規模での環境破壊
1) 大気汚染に関わる環境基準
2) 我が国における大気汚染の状況
1.3.3 地球規模での環境破壊
1) オゾン層の破壊
2) 地球温暖化
3) 酸性雨
1.3.4 エネルギー削減と環境の保全
1) エネルギー・環境改善のための基本理念
2) 身近な問題としての環境保全
引用文献
【第2章】バイオマス資源
2.1 地球上のバイオマス資源量
2.1.1 バイオマスとは
2.1.2 地球上のバイオマス量
2.1.3 世界のバイオマスの利用量
2.1.4 森林における炭素固定量
2.2 日本でのバイオマス資源量
2.2.1 陸地資源
1) 糖質資源
2) でんぷん資源
3) 森林資源
4) 炭化水素資源
5) 油脂資源
6) その他
2.2.2 水域資源
1) 淡水資源
2) 海洋資源
3) 微生物資源
2.2.3 農林水産資源
1) 林産資源
2) 農産資源(稲作副産物、その他農産残渣)
3) 畜産資源(家畜ふん尿)
4) 水産資源
2.2.4 廃棄物資源
1) 産業資源
2) 生活資源
3) 廃プラスチック資源
2.2.5 日本でのバイオマス資源の総利用可能量の推定
2.3 東南アジアでのバイオマス資源の現状と課題
2.3.1 天然林の維持造成と木材利用
1) 天然林からの木材利用と残廃材問題
2) 天然林の持続的管理の現状
2.3.2 造林および造林木利用の現状と問題点
1) マレーシアにおける植林の歴史
2) 造林および造林木の現状と問題点
3) 組織培養からの苗木による植林
4) 今後に向けて
2.3.3 農作物残廃材としてのゴムノキ、オイルパームの利用
1) ゴムノキ
2) オイルパーム
2.4 ブラジルでのバイオマス資源の現状と課題
2.4.1 アマゾン河流域における森林減少とその背景
1) 土地の権利確保と森林破壊
2) 牧場への転換
3) 大農プロジェクト
2.4.2 荒廃地化
1) 牧草地の荒廃地化
2) 零細農民の焼畑と荒廃地化
2.4.3 アマゾン河流域での植林活動
1) 早生樹造林
2) 採鉱跡地の環境復元造林
3) 製材、合板用材向け植林
4) 農牧場主による植林
2.4.4 ブラジル永大木材株式会社の植林事例
1) 天然林地帯での植林
2) 農牧場跡荒廃地での植林
3) 二、三の植林木の特徴
2.5 水圏バイオマス資源
2.5.1 水圏バイオマス資源量の現状と課題
2.5.2 水圏バイオマス資源
1) キチン・キトサン資源
2) 海藻資源
3) 魚油資源
4) 淡水バイオマス資源
2.6 バイオマス廃棄物
2.6.1 廃棄物中のバイオマス
1) 産業廃棄物
2) 一般廃棄物
2.6.2 バイオマス廃棄物の現状と課題
1) 木質廃棄物
2) 古紙
3) 食品廃棄物
2.7 再利用資源としての廃プラスチック
2.7.1 プラスチックの生産量と廃プラスチック量
2.7.2 廃プラスチック再利用の現状と課題
1) PETの超臨界分解
2) PEの超臨界分解
3) その他の廃プラスチックの超臨界分解
引用文献
【第3章】バイオマスと社会環境
3.1 バイオマスからの環境ホルモン
3.1.1 環境ホルモン
1) 環境ホルモンへの注目
2) 環境ホルモンとは
3.1.2 環境ホルモンの定義
3.1.3 環境ホルモンの種類と特徴
1) 環境ホルモンとその構造
2) 内分泌系とホルモン
3) 環境ホルモンの作用機序
4) 環境ホルモン問題に対する国内外の取り組み
5) 今後に向けて
3.1.4 バイオマスからの環境ホルモン
3.2 バイオマスからの有害物質
3.2.1 有害物質
1) 有害物質の分類
2) 有害物質の毒性の現れ方
3) 天然毒と人工有毒物質
3.2.2 有害物質の種類と特徴
1) 有害物質の種類
2) 人工有害物質、ダイオキシン類
3.2.3 バイオマスからの有害物質
1) バイオマス燃焼によるダイオキシン類の生成
2) 紙パルプの漂白によるダイオキシン類の生成
3) 塩素殺菌によるダイオキシ類の生成
3.3 バイオマス系廃棄物の処理
3.3.1 バイオマスの燃焼とダイオキシンの生成
1) 熱力学平衡解析
2) 有機系および無機系塩素からのダイオキシンの生成
3.3.2 バイオマス系廃棄物処理の現状と課題
1) 有機性汚泥
2) 古紙
3) 木屑、廃木材
4) 廃食用油
3.4 環境浄化型TiO2複合木質炭化物
3.4.1 TiO2複合木質炭化物の調製
3.4.2 TiO2複合木質炭化物の光触媒活性のトポ化学
3.4.3 TiO2結晶におけるホルムアルデヒド分解の光触媒反応機構
3.4.4 大気および水質汚染物質への応用
引用文献
【第4章】バイオマスのエネルギー変換技術
4.1 熱分解
4.1.1 直接燃焼
1) 木材の燃焼理論
2) 燃焼炉の方式
4.1.2 熱分解によるガス化および液化
1) 木材の熱分解機構
2) ガス化プロセス
3) 急速熱分解による液体製造プロセス
4.1.3 高度に生成物の選択性を高めた熱分解法の可能性
4.2 酸加水分解
4.2.1 バイオマス資源の酸加水分解反応
4.2.2 酸加水分解プロセス
1) 希酸法
2) 濃酸法
4.2.3 変換物質の利用
4.2.4 近年の動き
4.3 酵素糖化
4.3.1 酵素糖化とは
4.3.2 好気的糸状菌が生産するセルラーゼとその構造
4.3.3 セルラーゼによるセルロース分子鎖の加水分解
4.3.4 セルラーゼによるセルロースミクロフィブリルの分解
4.3.5 セルラーゼのセルロース表面への吸着と加水分解速度
4.3.6 セルラーゼの相乗作用
4.3.7 遺伝子組換え技術の導入
4.4 加圧熱水反応
4.4.1 加圧熱水反応の概要
4.4.2 液化(油化)
1) 木材の液化
2) 下水汚泥の液化(油化)
3) アルコール発酵残渣や微細藻類その他のバイオマスの液化
4.4.3 低温ガス化
4.4.4 その他の反応-流動化(可溶化)と加圧熱水抽出-
4.5 超臨界流体
4.5.1 超臨界流体とは
4.5.2 超臨界流体バイオマス処理装置
4.5.3 超臨界水によるセルロースの分解機構
4.5.4 超臨界水による木材の化学変換
4.5.5 他のバイオマス変換技術との比較
4.5.6 今後に向けて
引用文献
【第5章】バイオマスエネルギー燃料
5.1 薪
5.1.1 薪の生産量および消費量
5.1.2 薪の特性
5.1.3 開発途上国での薪利用
5.1.4 先進国での薪利用
5.2 木炭
5.2.1 生産量および消費量
5.2.2 製炭法および木炭の種類
5.2.3 エネルギーとしての木炭
5.2.4 様々な利用方法
5.2.5 環境浄化への利用
1) 水質浄化
2) 大気浄化
5.2.6 今後に向けて
5.3 ペレット化燃料
5.3.1 ペレット化燃料とは
5.3.2 RDF(Refuse Derived Fuel)
5.3.3 RDFの利用
5.3.4 RDF利用と排ガス問題
5.4 バイオマス発電
5.4.1 バイオマス発電の原料
5.4.2 バイオマス発電の方式
1) 直接燃焼-水蒸気タービン発電
2) コーファイアリング
3) ガス化-ガスタービン発電
4) メタン発酵-ガスエンジン発電
5) ランドフィルガス-ガスエンジン発電
6) エネルギー作物の利用
5.5 メタン
5.5.1 メタン発酵に用いられる種々のバイオマス資源
5.5.2 メタン発酵のメカニズムと条件
1) 有機物の分解機構
2) メタン発酵に関与する微生物
3) メタン生成機構
4) 反応速度の向上
5) 酢酸資化性メタン生成細菌の能力制御と代謝変換
5.5.3 メタン発酵装置
1) 下水汚泥消化のメタン発酵装置
2) し尿処理のメタン発酵装置
3) 廃液処理のメタン発酵装置
4) 畜産糞尿処理のメタン発酵装置
5) 固形有機物のメタン発酵装置
5.5.4 ごみ埋立地からのメタン回収
1) 埋立地バイオガスの捕集利用
5.6 エタノール
5.6.1 エタノールの物性および一般的性質
5.6.2 燃料としてのエタノールの性質
5.6.3 エタノール燃料の製造と利用
1) 米国
2) ブラジル
3) カナダ
4) フランス
5) スウェーデン
5.6.4 エタノール製造技術
1) 糖質およびでんぷん質の発酵技術
2) 各種エタノール発酵プロセス
3) 比較的最近開発された発酵プロセス
4) その他のプロセス
5) 木質系バイオマス原料からのエタノール製造(従来法)
6) セルロース系バイオマスの新しいエタノール変換技術
7) バイオマスをガス化後、エタノールを発酵生産する方法
8) 酵母の育種
5.6.5 エタノールの濃縮精製技術
5.6.6 エタノールの燃料以外の用途
5.7 メタノール
5.7.1 バイオマスからのメタノール製造
5.7.2 現状のメタノール製法
1) メタノール製造の基本工程
2) 合成ガス製造工程
3) メタノールの合成工程
4) 粗メタノールの精製
5.7.3 バイオマスからのメタノール製造技術の現状
1) バイオマスガス化技術の現状と課題
2) バイオマスからの生成ガス組成とメタノー
3) メタノール合成および粗メタノールの精製について
5.7.4 新しいバイオメタノール製法
5.7.5 メタノール燃料の特性
5.7.6 バイオメタノール燃料の利点
1) 太陽エネルギーを蓄えた燃料
2) 自然界を乱さない無限循環の再生可能エネルギー
3) 豊富な賦存量
4) CO2排出量削減への貢献
5) 石油同様の可搬性
6) 石油代替可能な液体燃料
7) クリーン燃料
5.8 ジメチルエーテル
5.8.1 ジメチルエーテルとは
1) DMEの基本物性
2) 安全性・環境特性・健康への影響
5.8.2 DMEの燃料特性と用途
5.8.3 DME合成製造技術
1) DME合成反応の特徴
2) 反応装置形式の選択
3) DME直接合成プロセス開発の経緯
4) NKKプロセス
5.8.4 多様な原料からのDME製造とDMEエネルギーフローシステム
1) 天然ガスを原料としたDME製造
2) 木質系バイオマスからのDME製造
5.9 MTBE、ETBE、TAME、TBA
5.9.1 ガソリンのオクタン価
5.9.2 オクタン価向上基材
1) MTBE
2) ETBE
3) TAME
4) TBA
5.9.3 バイオマス起源のオクタン価向上基材によるCO2排出量の削減
5.10 バイオディーゼル燃料
5.10.1 アルカリ触媒法
5.10.2 超臨界メタノール法
1) 超臨界メタノールバイオマス変換装置
2) 超臨界メタノールによる植物油のメチルエステル化
5.10.3 固定化微生物法
1) 固定化菌体-Whole Cell Biocatalyst
2) 固定化の培養条
3) 固定化菌体を用いた反応条件
5.10.4 植物油からのバイオディーゼル燃料の製造
引用文献
【第6章】バイオマス燃料の研究動向と利用例
6.1 燃焼装置用およびエンジン用としてのバイオマス燃料
6.1.1 固体バイオマス燃料とその利用
6.1.2 気体バイオマス燃料とその利用
6.1.3 液体バイオマス燃料とその利用
6.1.4 火花点火エンジンの燃料要件とバイオマス燃料
6.1.5 ディーゼルエンジンの燃料要件とバイオマス燃料
6.2 バイオマスのエネルギー利用の研究動向
6.2.1 バイオマス利用の概要
6.2.2 バイオマス有効利用の手順
6.2.3 LCA手法
6.2.4 エネルギー分析
6.2.5 バイオ燃料ライフサイクル
6.2.6 今後に向けて
6.3 バイオマス燃料の利用例
6.3.1 薪・木炭自動車
6.3.2 エタノール燃料車
6.3.3 メタノール車
6.3.4 ジメチルエーテル車
6.3.5 バイオディーゼル車
6.3.6 メタンガス
1) 電力への変換と熱利用
2) CNG自動車燃料への利用
3) 天然ガスラインへの接続
引用文献