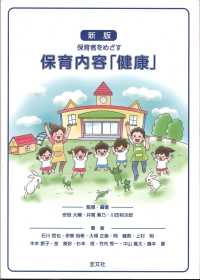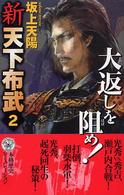- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
昭和初期の著者自身の体験をもとに、野の植物・虫・魚などでの遊び60余種を季節ごとに綴る。江戸時代からの伝承遊びもあれば、今日では見られなくなった懐かしい遊び、また現代に引き継がれているものもあり、まさに自然遊びの玉手箱のような本!高度成長期以前の子どもの野遊び生活史である。
目次
春の自然遊び(草人形;草笛;ネコヤナギの綿毛 ほか)
夏の自然遊び(オオバコとカエル;オオバコの草遊び;ヤエムグラの勲章 ほか)
秋・冬の自然遊び(イヌタデとママゴト;ホオズキ遊び;藁鉄砲 ほか)
著者等紹介
中田幸平[ナカダコウヘイ]
1926年栃木県栃木市に生まれる。1946年戦後、演劇を志し上京、新協劇団に加わる。1949年劇団俳優座に属し、ステージ・コスチュームデザイナーとなる。1955年俳優座を退き、以来フリーとなり、演劇・舞踊のデザイン、時代考証、原稿執筆、傍ら桑沢デザイン研究所の講師を務める。1960年NHK大河ドラマ『春の波涛』の風俗考証担当を最後に退く。児童文化の研究に専念。現在、日本ペンクラブ会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のん@絵本童話専門
2
昭和の子ども達の遊びについて、一つ一つの自然遊びを取り上げながら季節ごとに書かれている本です。自然遊びの説明・やり方ももちろん書かれていますが、文章メインの読み物です。それよりも、昭和の子ども達における「遊び」の意義、社会性、大人と子供の在り方など、今と比較して色々と考えさせられます。ヘビやカエルとの遊びなど良い意味でも大人の目が届いていなかったのだと思う。危険や事故ももちろん多かったことだろう。自然遊びには想像力も必要だし、子どもの社会性も養われる。外遊び・自然遊びについては今後も勉強していく予定。2021/05/01