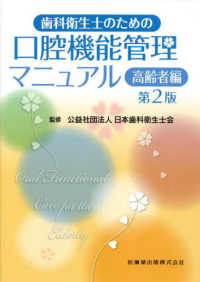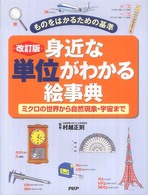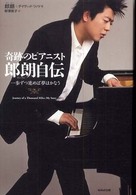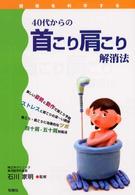目次
第1部 基礎篇―これからコピーライターになる人へ。(新人コピーライター物語)
第2部 応用篇―コピーライター、コピーを語る。(あの人は、こんな風に、コピーを。;「思い出の小箱」に残る言葉;表現は氷山の一角だ。;めざせ、企画エンタテインメント。;それも、これも、コピーライターの仕事。)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
雪野きずな
3
半分、頭で考えて半分手で考えるから初めは手書きがお勧めと書かれてあった。創作全般に言えそう。2020/05/19
かりん
3
【思い出本再読1804-1】「改めてちゃんとコピーの勉強しようかなぁ…」と思い、10年くらい前に読んだこちらを引っ張り出す。→コピーが絵と同じこと言ってる。“なぞり”といって、よくないコピーの典型/後世になって評価された画家や作家はいますが、時代に背を向けた孤高のコピーライター、なんてものは存在しない/(公共広告はおせっかいだから)目線を変えて、聞いてもらえる声の大きさで、言葉を発する/主観で書き、客観で見る/いいコピーって、原稿用紙が立って見えるんだよね。1枚の紙に収まらない、広がりを感じるっていうか…2018/04/23
ぷりん
3
新人コピーライターでもこれから目指すわけでもないけど読んでみた。これはコピーだけに限らずコミュニケーションの本だと思う。どの言葉を使いどう伝えるか。そもそも何を伝えたいのか。人前で話すときにいつも悩むこと。もっと普段からこだわってみよう。2011/02/15
にゃーごん
2
2000年代の本なので実例の広告が懐かしい。コピーを書く視点、方法論が分かりやすく紹介されているけど、真似は容易ではない。普段から情報収集したり想像力を働かせたりと、泥くさい努力の積み重ねで言葉を生み出したいるんだな。普段は漢字で表記するところをひらがなにすることで、強調したいポイントにかかわる漢字が目に飛び込んできやすくなる。時代の変化に敏感であり、独りよがりにならないこと。消費者目線を意識して、どうすれば読んでもらえるか考える。あと、良し悪しは抜きにして当時の企業体質(電通)もチラ見える一冊。2021/03/02
コジターレ
1
読メ登録前に読了。