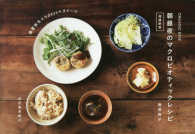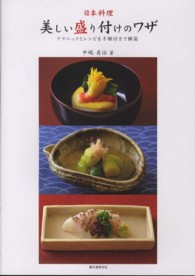目次
第1部 序話(江戸時代における科学の歴史の研究手法;江戸時代の日本における「人口」の変遷;江戸時代における「小判の改鋳と品位」の変遷;享保改革における江戸の町の「上水道」廃止の事情)
第2部 江戸時代の日本における近代科学の萌芽と挫折(江戸時代における「浮力の原理」と「密度・比重」の概念;日本の数学「和算」の成立と円周率の算出方法を巡る数学的「証明」の概念;江戸時代における「てこの原理」と「モーメント」の概念)
第3部 従来の日本科学史上における誤解の事例(享保改革における「禁書緩和」は本当か―一七~一八世紀の漢訳西洋科学書(漢文科学書)の場合
「蘭学」とその評価の変遷―廣川晴軒の『三元素略説』(一八六五)の場合)
第4部 江戸から明治への過渡期における科学史上の出来事の事例(日本における「熱運動説」の受容過程と「火・熱」の概念の変遷;一九世紀末の東日本における「養蚕地域」の農民の特性と「和算」文化;日本における西欧近代科学の受容と「訳語」の選定)
著者等紹介
中村邦光[ナカムラクニミツ]
1934年(昭和9年)3月、長野県埴科郡(現千曲市)に生まれる。1957年東京理科大学理学部物理学科卒業。1970年日本大学農獣医学部専任講師。1978年国立教育研究所・板倉研究室共同研究員。1985年日本大学教授。1988年学術博士(Ph.D)の学位を取得。1990年中国・遼寧師範大学客員教授。1995年日本科学史学会和文誌編集委員、財政委員会委員長、科学史教育委員会委員長。1997年日本学術会議第17~18期科学史研究連絡委員。1999年日本大学生物資源科学部図書館長。日本大学名誉教授。国立科学博物館「日本の科学者・技術者展」企画委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
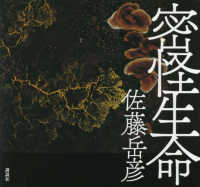
- 和書
- 密怪生命

![全国重伝建紀行 [重要伝統的建造物群保存地区]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/40653/4065350727.jpg)