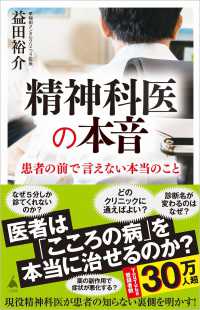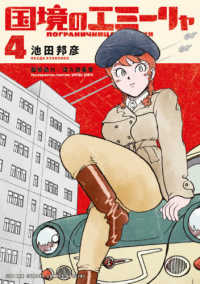出版社内容情報
★抗酸化,免疫,ストレス,ゲノムといった注目キーワードを解説!
★海外での健康表示,身体への作用を解説!健康食品データベースを紹介!
★注目される食品素材73品目について詳述!
--------------------------------------------------------------------------------
太田明一 キリンビール(株)
大濱宏文 日本健康食品規格協会 理事長
信川益明 杏林大学 医学部 総合医療学教室 助教授
宮澤陽夫 東北大学 大学院農学研究科 機能分子解析学 教授
南野昌信 (株)ヤクルト本社 中央研究所 応用研究II部免疫研究室 副主席研究員
山本佳弘 武田食品工業(株) 研究開発部 開発第二グループ グループマネージャー
上野川修一 日本大学 生物資源科学部 食品科学工学科 食品機能化学研究室 教授
二木鋭雄 (独)産業技術総合研究所 ヒューマンストレスシグナル研究センター センター長
武田英二 徳島大学 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 臨床栄養学分野 教授
香川靖雄 女子栄養大学 副学長;医化学教室 教授
牧浦啓輔 サンブライト(株) 営業課 主任
佐藤俊郎 (株)J-オイルミルズ ファイン・フーズ研究所 ファイン研究室 課長
末木一夫 日本国際生命科学協会 事務局次長
久保田浩敬 日清ファルマ(株) 開発部 部長代理
王堂哲 ロンザジャパン(株) 微生物工学受託事業部 事業部長
糸川嘉則 京都大学;福井県立大学 名誉教授;仁愛女子短期大学 教授
藤田裕之 日本サプリメント(株) 研究開発部 部長
阿部秀一 日本油脂(株) 食品研究所 主任研究員
菅野道廣 九州大学;熊本県立大学 名誉教授
園良治 辻製油(株) 機能性事業本部 営業部 部長
坂口裕之 キユーピー(株) 健康・医療R&Dセンター ファインケミカルグループ チームリーダー
日比野英彦 日本油脂(株) 食品事業部 学術担当次長
森口覚 山口県立大学 大学院健康福祉学研究科 生活健康科学専攻 教授
大野智弘 (株)ファンケル 中央研究所 基盤探索部門 新素材探索グループ 研究員
竹山喜盛 理研化学工業(株) 研究所 取締役研究所長
小野佳子 サントリー(株) 健康科学研究所 主任研究員
有井雅幸 キッコーマン(株) バイオケミカル事業部 機能性食品グループ グループ長
佐本将彦 不二製油(株) フードサイエンス研究所 主任研究員
鈴木良雄 日清ファルマ(株) 開発部 担当課長
畠 修一 タマ生化学(株) 営業部開発担当 主任
大澤俊彦 名古屋大学 大学院生命農学研究科 教授
田中一平 (株)常磐植物化学研究所 植物機能科学ラボラトリー
高柿了士 丸善製薬(株) 総合研究所 研究開発本部 副部長
虎田英之 日本油脂(株) 食品事業部 食品研究所 主任研究員
岩井和夫 京都大学;神戸女子大学 名誉教授
渡辺達夫 静岡県立大学 食品栄養科学部 助教授
深谷幸隆 松浦薬業(株) 薬・食企画部門 薬理・機能室 室長
服部英里 松浦薬業(株) 薬務学術部門
千田信子 松浦薬業(株) 薬務学術部門 室長代理
村上太郎 研光通商(株) フードサイエンス事業部 課長
内藤宏一 花王(株) ヘルスケア第1研究所 主任研究員
光永俊郎 TOWA CORPORATION(株) 顧問;近畿大学 名誉教授
家森幸男 循環器疾患予防国際共同研究センター;(財)生産開発科学研究所 予防栄養医学研究室;京都大学 名誉教授
森真理 (財)生産開発科学研究所 予防栄養医学研究室
森英樹 (株)健康再生研究所
舟橋敏彦 松浦漢方(株) 薬事学術部 部長
下田博司 オリザ油化(株) 研究開発部 部長
菊池美香 アスク薬品(株) 企画管理部門
柿澤雄輔 メイプロインダストリーズ(株) 営業部 アカウントマネージャー
伊原一秋 メイプロインダストリーズ(株) 取締役 営業部長
白崎友美 オリザ油化(株) 研究開発部
坂上宏 明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 薬理学分野 教授
山内健 (株)ニュートリションアクト 研究開発部 部長
市川剛士 サンブライト(株) 営業課 主任
松下昌史 (株)トレードピア 企画開発
李征 (株)栄進商事 代表取締役
金谷由美 築野食品工業(株) 企画開発室
三輪尚克 (株)林原生物化学研究所 開発センター アシスタントディレクター
馬渡一徳 味の素(株) アミノ酸部 専任部長
三島敏 アピ(株) 長良川リサーチセンター 取締役所長
武藤泰章 ゼリアヘルスウエイ(株) 学術部 統括学術部長
前崎祐二 日本化薬フードテクノ(株) 研究所 研究開発担当
本田真樹 ハイライフ(株) 代表取締役
坂本廣司 甲陽ケミカル(株) 企画開発部 部長
勝呂栞 甲陽ケミカル(株) 企画開発部 課長
西川正純 宮城大学 食産業学部 フードビジネス学科 教授
村井陽介 (株)ニチロ バイオ事業部
斉藤真人 明治乳業(株) 食品開発研究所 栄養食品研究部 機能性食品グループ
土田博 明治乳業(株) 食品開発研究所 栄養食品研究部 部長
山内恒治 森永乳業(株) 栄養科学研究所 基礎研究室 室長
菊池誠 Dr.Kikuchi研究所 所長;インペリアル南東京クリニック 院長
平本茂 日清ファルマ(株) 健康科学研究所 所長代理
木村修武 日清ファルマ(株) 健康科学研究所 研究主幹
香川恭一 エムジーファーマ(株) 代表取締役社長
福浜千津子 エムジーファーマ(株) 開発部
飯田浩明 (株)ヤクルト本社 中央研究所 研究管理部 研究企画課 指導研究員
若林英行 キリンビール(株) フロンティア技術研究所 研究員
福島洋一 ネスレ日本(株) 製造サービス部 ビジネスサポート課
熊谷武久 亀田製菓(株) お米科学研究室 アシスタントマネージャー
家森正志 京都大学 大学院医学研究科
家森百合子 聖ヨゼフ整肢園
小池泰介 (株)応微研
堀内勲 (株)応微研 代表取締役
川口正人 (株)応微研
栗原昭一 (株)リコム 新素材開発部 部長
佐藤拓 キリンビール(株) 機能食品カンパニー 開発研究所 主任研究員
須賀哲也 味の素(株) 医薬カンパニー 医薬事業戦略部 高機能食品領域長 専任部長
芳田美智子 キリンビール(株) 機能食品カンパニー 開発研究所
高岡晋作 (株)日本生物.科学研究所 R&Dセクション 主任研究員
柴崎剛 協和発酵工業(株) ヘルスケア研究所 主任研究員
湊貞正 富士化学工業(株) ライフサイエンス事業部 顧問
梅垣敬三 (独)国立健康・栄養研究所 食品表示分析・規格研究部 室長
廣田晃一 (独)国立健康・栄養研究所 健康栄養情報・教育研究部 室長
--------------------------------------------------------------------------------
第?T編 総論
食の機能の理解が深まり活用されることを願って~『食品機能素材?V』の序論にかえて~(太田明一)
1. はじめに
2. 消費者を取り巻く環境
3. 行政の動き
3.1 現況
3.2 やればできることの一例
4. 遅々とした歩みながら前進 ~「健康食品」に関する主な動き~
5. 本書の企画に当たって
6. おわりにあたって
第1章 海外における食品の健康強調表示(大濱宏文)
1. はじめに
2. 強調表示
3. コーデックスによる健康強調表示
4. EU(ヨーロッパ連合)
5. 米国の制度
5.1 ヘルスクレーム
5.2 構造/機能表示
6. おわりに
第2章 食品の身体に対する作用(信川益明)
1. はじめに
2. 脳
3. 胃
4. 免疫細胞
5. 腸
6. 肝臓,胆汁酸
7. 活性酸素,フリーラジカル(遊離基),過酸化脂質
8. 酵素,補酵素
8.1 ATPクエン酸リアーゼ
8.2 α-グルコシダーゼ(糖分解酵素)
8.3 エストロゲン
8.4 シクロオキシゲナーゼ
8.5 5α-リダクターゼ
8.6 アンギオテンシン?T変換酵素
8.7 消化酵素
8.8 HMG-CoA還元酵素
8.9 SOD(スーパーオキシドジムターゼ)
8.10 コエンザイムQ10
9. 細菌
10. 血栓,ロイコトリエン(炎症物質),塩素(Cl),ビタミンB1
11. 骨格
12. 軟骨
13. 筋肉
14. 皮膚
15. 健康増進のための適切な情報提供・利用と環境整備並びに連携の重要性
第3章 抗酸化(宮澤陽夫)
1. 「抗酸化」とは?
2. 酸素の必須性と毒性
3. 体には抗酸化の仕組みが備わっている
4. 抗酸化のメカニズム
5. 抗酸化の概念は食品の酸化劣化防止から始まった
6. 抗酸化力の測定法
7. 「抗酸化物質」の体内での効能評価は難しい
8. 「抗酸化物質」の代謝と効能の関係
9. 抗酸化物質の良い面と悪い面
10. おわりに
第4章 腸管免疫(南野昌信,山本佳弘,上野川修一)
1. 腸管の生理的機能
2. 腸管のリンパ球
2.1 腸管粘膜のB細胞
2.2 腸管粘膜のT細胞
2.3 腸管粘膜へのリンパ球のホーミング
3. 腸管免疫の特性
4. おわりに
第5章 ストレス(二木鋭雄)
1. ストレスとは
2. ストレスに対する生体の応答
3. 酸化ストレス
4. おわりに
第6章 ストレス制御をめざす栄養科学(武田英二)
1. はじめに
2. ストレスと生体反応
2.1 ストレスと神経系,内分泌・代謝,免疫反応
2.2 ストレスと食欲
2.3 炎症性サイトカインを介したストレスによる代謝障害
3. ストレスと栄養・食事
3.1 食事とストレス
3.2 ストレスと脳中セロトニン代謝
3.3 ヒトでのストレス評価システム
3.4 ヒトでの食品機能評価システム
第7章 遺伝子多型と健康食品の効果の個人差(香川靖雄)
1. 食品の効果の個人差は大きい:一升酒の栄養学
2. 健康食品・特保の機能有効性の個人差
3. オーダーメイド栄養
4. 生活習慣病の遺伝子多型と長期効果
5. 試行されている個人対応栄養学
6. 個人対応栄養学が実現する条件
7. おわりに
第II編 各論
第1章 ビタミン
1. リコピン (牧浦啓輔)
1.1 はじめに
1.2 リコピンの性質とカロチノイドの構造と代謝
1.3 リコピンの分布
1.4 リコピンの吸収性
1.5 リコピンの抗酸化力
1.6 おわりに
2. ビタミンK (佐藤俊郎)
2.1 はじめに
2.2 ビタミンKの構造
2.3 ビタミンK依存性タンパク質の活性化
2.4 ビタミンK2と動脈硬化
2.5 ビタミンK2と心臓病予防
2.6 ビタミンK2と骨粗鬆症
2.7 ビタミンK2の骨代謝への作用(メカニズム)
2.8 ビタミンK2とがん
2.9 活性が持続する納豆菌由来のビタミンK2
3. 葉酸(プテロイルグルタミン酸) (末木一夫)
3.1 はじめに
3.2 葉酸(プテロイルグルタミン酸)
3.3 ホモシステイン
3.4 ホモシステインと疾病
3.4.1 心血管系疾病(動脈硬化含む)
3.4.2 認知症
3.4.3 抑うつ症
3.4.4 その他疾病
3.5 市場
3.6 おわりに
4. ルテイン/ゼアキサンチン (末木一夫)
4.1 はじめに
4.2 ルテインとゼアキサンチン
4.3 加齢性網膜黄斑変性症(AMD:Age-related Macular Degeneration)
4.4 ルテイン/ゼアキサンチンの血中動態
4.5 ルテイン/ゼアキサンチンの疾病予防
4.6 市場
5. コエンザイムQ10 (久保田浩敬)
5.1 はじめに
5.2 物理化学的性質
5.3 歴史
5.4 食品中の含有量
5.5 生体内での生合成,吸収,分布,加齢による減少
5.5.1 生合成
5.5.2 吸収
5.5.3 分布
5.5.4 加齢による減少
5.6 生体内での役割
5.6.1 エネルギー産生抑制
5.6.2 抗酸化作用
5.7 ヒトに対する作用・用途
5.8 安全性
5.9 医薬品との相互作用
6. L-カルニチン (王堂哲)
6.1 生理機能
6.2 物性・一般食品中での分布など
6.3 製法
6.4 安全性
6.5 製品例
6.6 市場性
第2章 ミネラル(糸川嘉則)
1. 亜鉛
1.1 亜鉛の概要
1.2 亜鉛欠乏症
1.3 亜鉛の食事摂取基準
1.4 亜鉛の充足状態の推定
1.5 亜鉛と銅の関係
1.6 食品と亜鉛
2. カルシウム
2.1 カルシウムの概要
2.2 カルシウムの必要量
2.3 カルシウム摂取量
2.4 食品とカルシウム
2.5 カルシウムとマグネシウムのバランス
第3章 脂質
1. ボラージオイル (藤田裕之)
1.1 はじめに
1.2 ボラージオイルとは
1.3 アトピー性皮膚炎改善作用
1.4 その他の生理作用
1.5 GLA高含有のボラージオイルの開発
1.6 おわりに
2. 中鎖脂肪酸 (阿部秀一)
2.1 中鎖脂肪酸からなるMCT
2.2 中鎖脂肪酸の由来
2.3 MCTの消化吸収
2.4 中鎖脂肪酸の代謝
2.5 MCTの生理機能
2.5.1 優れた消化吸収性
2.5.2 インスリン分泌促進作用
2.5.3 体重増加抑制作用
2.6 おわりに
3. 共役リノール酸 (菅野道廣)
3.1 はじめに
3.2 組成
3.3 製法
3.4 機能
3.5 安全性
3.6 応用例
3.7 製品例
3.8 市場性
4. 大豆レシチン (園良治)
4.1 組成
4.2 製法
4.3 機能
4.4 安全性
4.5 製品例
4.6 市場性
5. 卵黄レシチン (坂口裕之)
5.1 はじめに
5.2 脂質組成
5.3 脂肪酸組成
5.4 卵黄レシチンの製造方法
5.5 卵黄レシチンの機能と利用
5.6 卵黄リゾレシチンの機能と利用
5.7 おわりに
第4章 植物由来
1. オクタコサノール (日比野英彦)
1.1 発見と開発の経緯
1.2 組成,製法,安全性
1.3 機能
1.3.1 運動機能の向上
1.3.2 脂質代謝の改善
1.3.3 血小板凝集能の抑制効果
1.4 おわりに
2. 大麦若葉 (森口覚)
2.1 はじめに
2.2 大麦若葉とは
2.3 大麦若葉の生理作用
2.3.1 ビタミン・ミネラル
2.3.2 ヘクサコシルアルコール
2.3.3 抗酸化成分
2.3.4 食物繊維
2.4 大麦若葉粉末の飲用における注意
2.5 おわりに
3. ケール・ケ-ルエキス (大野智弘)
3.1 はじめに
3.2 機能性および有効成分に関する知見
3.3 アレルギー疾患(スギ花粉症)に及ぼす有用性
3.4 有効成分の探索および作用機序の解明
3.5 食経験
3.6 製造・加工技術
3.7 おわりに
4. 無臭にんにく末 (竹山喜盛)
4.1 無臭にんにく末のがん予防効果
4.2 無臭にんにく末と既知抗生物質との併用効果
5. 甜茶 (小野佳子)
5.1 はじめに
5.2 組成
5.3 機能
5.3.1 ヒスタミン遊離抑制作用
5.3.2 鼻アレルギー緩和作用
5.3.3 花粉症緩和作用
5.3.4 NCマウス皮膚炎抑制作用
5.3.5 かゆみ抑制作用
5.4 安全性
5.5 製品例・市場性
6. ブドウ種子プロアントシアニジン (有井雅幸)
6.1 ブドウ種子プロアントシアニジの特徴と学術エビデンス
6.2 ヒト体内抗酸化作用
6.3 ヒト美白作用
6.4 おわりに
7. 大豆タンパク質及び大豆ペプチド (佐本将彦)
7.1 はじめに
7.2 大豆タンパク質の機能
7.2.1 血漿コレステロール低下作用
7.2.2 血漿中性脂肪低減作用
7.2.3 前立腺がん罹患リスク低減
7.3 大豆ペプチドの機能
7.3.1 筋肉損傷軽減・筋肉増強
7.3.2 脂質代謝促進効果
7.3.3 疲労への影響
7.3.4 その他
7.4 今後の展望
8. 小麦ペプチド (鈴木良雄)
8.1 はじめに
8.2 グルタミン
8.3 グルタミン源としての小麦ペプチド
8.4 小麦ペプチドに特有の機能
8.4.1 オピオイドペプチド
8.4.2 ACE阻害ペプチド
8.4.3 小麦ペプチドの効果
8.5 安全性
8.6 おわりに
9. イチョウ葉エキス (畠修一)
9.1 はじめに
9.2 有効性成分
9.3 生理的機能
9.4 脳機能とイチョウ葉エキス
9.5 安全性
10. 柑橘類ポリフェノール (大澤俊彦)
10.1 レモンポリフェノールの化学と機能性
10.2 発酵レモンフラボノイドの機能性
10.3 おわりに
11. ビルベリーエキス (田中一平)
11.1 ビルベリー(Vaccinium myrtillus L.)について
11.2 ビルベリー果実のアントシアニンについて
11.3 機能性について
11.4 ビルベリーエキスの臨床使用例
11.5 安定性
11.6 安全性
11.7 ビルベリーエキスの市場
11.8 ビルベリーエキスの利用製品について
12. ウコン (高柿了士)
12.1 ウコン(Curcuma longa L.)について
12.2 有効成分,構造式
12.3 機能・効能・生理活性
12.4 安全性・体内代謝
12.5 性状
12.6 安定性
12.7 応用例・商品例
12.8 メーカー,生産量,価格
13. セラミド (虎田英之)
13.1 はじめに
13.2 セラミドの構造と起源
13.3 皮膚中におけるセラミドの働き
13.4 セラミドの代謝
13.5 小麦セラミドの経口摂取効果
13.5.1 保湿効果
13.5.2 乾燥肌傾向にある方への効果
13.6 おわりに
14. カプサイシンおよび辛味のないカプサイシン同族体 (岩井和夫,渡辺達夫)
14.1 カプサイシン
14.2 辛味のないカプサイシン同族体
14.2.1 カプシエイト
14.2.2 オルバニル
14.2.3 カプシエイトとオルバニルが無辛味である理由
15. パフィア (深谷幸隆,服部英里,千田信子)
15.1 はじめに
15.2 成分
15.3 機能
15.4 安全性
15.5 製品への応用例
15.6 市場性
16. ノコギリヤシ (村上太郎)
16.1 はじめに
16.2 生理活性機能
16.3 臨床試験
16.4 副作用
17. 茶カテキン (内藤宏一)
17.1 茶カテキンとは
17.2 チャの品種と茶カテキン
17.3 緑茶抽出物
17.4 茶カテキンの健康機能
17.5 安全性
17.6 緑茶抽出物の生産量と使用用途
18. マカ (光永俊郎)
18.1 マカとは
18.2 マカの歴史
18.3 マカの成分特性
18.3.1 一般栄養成分
18.3.2 ミネラルとビタミン
18.3.3 特殊成分
18.4 マカの利用
18.5 マカの評価
19. 大豆イソフラボン (森真理,森英樹,家森幸男)
19.1 はじめに
19.2 植物性エストロゲン=大豆イソフラボン
19.3 更年期障害と骨粗鬆症の予防
19.4 高血圧と動脈硬化予防
19.5 ガンを防ぐイソフラボン
19.6 おわりに
20. ゴマリグナン (小野佳子)
20.1 はじめに
20.2 ゴマの組成とリグナン含量
20.3 セサミンの生体内代謝
20.4 セサミンの生理機能
20.4.1 自律神経調節作用
20.4.2 血圧低下作用
20.5 安全性
21. 田七人参 (舟橋敏彦)
21.1 はじめに
21.2 組成
21.3 機能
21.3.1 田七人参の主な機能
21.3.2 田七葉総サポニンの主な機能
21.4 安全性
21.5 製品への応用例
21.6 市場性
22. ココアポリフェノール (下田博司)
22.1 はじめに
22.2 ココアポリフェノールの組成
22.3 ポリフェノールの機能性
22.4 ココアポリフェノール配合製品と原料
23. エキナセア (菊池美香)
23.1 エキナセアとは
23.2 プルプレアの地上部と根,及びパリダの根:公認される3種類のエキナセアについて
23.3 プルプレアの地上部搾汁液について:特徴,薬理・臨床試験と安全性
23.4 エキナセアの利用:国際市場での利用と商品選択における問題と対策
24. ファセオラミン (柿澤雄輔,伊原一秋)
24.1 白いんげん豆抽出物の歴史
24.2 ファセオラミン
24.2.1 ファセオラミン
24.2.2 安全性
24.3 臨床試験(一例)
24.3.1 ヴィンセン博士らによる臨床試験が糖の吸収を抑制
24.3.2 バレリーニ博士による臨床試験
24.3.3 ウダニ博士らによる臨床試験
24.3.4 その他の臨床試験
24.4 日本市場と新たな用途
25. トコトリエノール (白崎友美)
25.1 トコトリエノールとは
25.2 トコトリエノールの機能性
25.3 トコトリエノールの皮膚への作用
25.4 トコトリエノールの利用と応用
26. 松かさエキス (坂上宏)
26.1 はじめに
26.2 抗腫瘍性物質としてのリグニン配糖体の同定
26.3 リグニン配糖体の抗菌・抗寄生虫活性と内因性サイトカインの誘導
26.4 マクロファージ・リンパ球の活性化
26.5 抗ウイルス活性
26.6 アスコルビン酸(ビタミンC)との相乗作用
26.7 リグニン配糖体の安全性
26.8 リグニン配糖体の有用性
27. メロン抽出物・オキシカイン (山内健)
27.1 はじめに
27.2 オキシカインの原料
27.3 オキシカインの作用機構
27.4 生体の抗酸化酵素類の誘導,活性
27.5 酸化ストレス/レドックス制御
27.6 オキシカインの臨床効果
27.6.1 動物による研究
27.6.2 ヒトによる研究
27.7 オキシカインの期待される用途
28. オリーブポリフェノール (市川剛士)
28.1 はじめに
28.2 オリーブに含まれるポリフェノール
28.3 製品例
28.4 オリーブポリフェノールの製法
28.5 オリーブ果実ポリフェノールの定量方法
28.6 安全性
28.7 安定性
28.8 機能
29. ピクノジェノ-ル (松下昌史)
29.1 はじめに
29.2 製造
29.3 特許
29.4 安全性
29.5 機能性
29.6 おわりに
30. カンカ (李征)
30.1 カンカとは
30.2 カンカとニクジュヨウ
30.3 カンカの有効成分と薬理作用
30.3.1 滋養強壮作用
30.3.2 免疫増強作用
30.3.3 抗老化作用
30.3.4 認知障害改善作用
30.4 安全性
30.5 人工栽培と自然保護
30.6 市場性と今後の展望
31. フェルラ酸 (金谷由美)
31.1 はじめに
31.2 性状と物性
31.3 製法
31.4 安全性
31.5 体内動態
31.6 機能性
3.16.1 抗酸化作用
31.6.2 脂質低下作用
31.6.3 血圧低下作用
31.6.4 腎障害予防作用
31.6.5 認知障害予防作用
31.6.6 美白作用
31.7 製品例
31.8 おわりに
32. 酵素処理ヘスペリジン (三輪尚克)
32.1 はじめに
32.2 製法・構造
32.3 規格・表示
32.4 物理化学的特性
32.5 食品への利用・効果
32.6 生理機能
32.7 安全性
32.8 市場性
33. 環状四糖 (三輪尚克)
33.1 はじめに
33.2 構造と大量製造技術
33.3 諸物性
33.4 生体での利用性
33.5 食品加工への可能性
33.6 生理機能
33.7 安全性
33.8 市場性・今後の展望
34. アミノ酸 (馬渡一徳)
34.1 分岐鎖アミノ酸の有用性
34.2 アルギニンの有用性
34.3 グルタミンの有効性
34.4 アラニンとグルタミンの肝障害への効果
35. プロポリス (三島敏)
35.1 はじめに
35.2 成分・起源
35.3 生理活性
35.3.1 抗菌・抗ウイルス活性
35.3.2 抗腫瘍活性
35.3.3 抗酸化活性
35.3.4 抗炎症活性
35.3.5 その他
35.4 おわりに
第5章 動物由来
1. ローヤルゼリー (武藤泰章)
1.1 はじめに
1.2 市場
1.3 組成・成分
1.4 薬理作用
1.5 おわりに
2. キトサン (前崎祐二)
2.1 組成
2.2 製法
2.3 機能
2.3.1 コレステロール調整機能
2.3.2 腸内腐敗産物濃度の減少
2.3.3 血中尿酸値低下
2.4 安全性
2.5 製品例
3. コラーゲンペプチド (本田真樹)
3.1 コラーゲンとは
3.1.1 存在
3.1.2 種類
3.1.3 アミノ酸組成
3.1.4 性質
3.1.5 機能
3.2 コラーゲンペプチド(CP)の生体調節機能
3.3 コラーゲンペプチド(CP)のアレルギー性
3.4 コラーゲンペプチド(CP)の種類
3.5 コラーゲンペプチド(CP)の応用
3.5.1 ビタミンC(VC)
3.5.2 カロチノイド
3.5.3 ビタミンE(VE)
3.5.4 グリシン
3.5.5 プロアントシアニジン(OPC)
3.5.6 エラグ酸
3.5.7 セラミド
3.5.8 ヒアルロン酸
3.5.9 グルコサミン
4. グルコサミン (坂本廣司,勝呂栞)
4.1 グルコサミンとは
4.2 グルコサミンの代謝
4.3 グルコサミンの有用性
4.3.1 変形性膝関節症(OA)に対する最近の臨床成績
4.3.2 グルコサミンのOAに対する作用機序
4.3.3 その他の生理機能
4.4 グルコサミンの安全性
4.5 おわりに
5. スクワレン (西川正純)
5.1 はじめに
5.2 スクワレンの原料,製法及び市場
5.3 スクワレンの生理機能
5.3.1 脂質代謝改善作用
5.3.2 抗酸化作用
5.3.3 外因性内分泌撹乱物質の排泄作用
5.4 おわりに
6. デオキシリボ核酸 (村井陽介)
6.1 はじめに
6.2 製法
6.3 DNAの特徴
6.4 安全性
6.5 市場性
6.6 機能
7. VAAM(ヴァーム) (斎藤真人,土田博)
7.1 VAAMの発明
7.2 持久力の増強
7.3 持久力を裏付けるメカニズム
7.4 製品化
8. ラクトフェリン (山内恒治)
8.1 はじめに
8.2 LFの多機能性
8.3 経口摂取による感染防御・発がん予防効果とその作用機序
8.4 LFの安全性
8.5 LFの工業的生産と応用
9. ヒアルロン酸 (菊池誠)
9.1 はじめに
9.2 ヒアルロン酸の生体での働き
9.3 代謝および安全性
9.4 老化とヒアルロン酸
9.5 各臓器でのヒアルロン酸の働き及び食用による臨床的影響
9.5.1 皮膚
9.5.2 目
9.5.3 関節
9.5.4 子宮・卵巣
9.6 おわりに
10. カゼイン重合物 (平本茂,木村修武,鈴木良雄)
10.1 はじめに
10.2 カゼイン重合物
10.3 安全性
10.4 ヒトでの効果
10.5 おわりに
11. グロビンペプチド (香川恭一,福浜千津子)
11.1 グロビンペプチドとは?
11.2 なぜ食後の中性脂肪を下げなければならないのか?
11.3 グロビンペプチドを長期摂取すれば空腹時中性脂肪値は下がるか?
11.4 おわりに
第6章 微生物由来
1. 乳酸菌 (飯田浩明)
1.1 はじめに
1.2 乳酸菌の利用法
1.2.1 酪農乳酸菌
1.2.2 植物乳酸菌
1.2.3 腸管乳酸菌
1.3 乳酸菌の発酵形式
1.4 市場規模
2. 乳酸菌の抗アレルギー効果 (若林英行)
2.1 プロバイオティクスとバイオジェニックス
2.2 乳酸菌の抗アレルギー効果~乳酸菌KW3110株の発見~
2.3 乳酸菌とアトピー性皮膚炎
2.4 乳酸菌のアレルギー抑制メカニズム
2.5 乳酸菌の有効成分
2.6 おわりに
3. LC1乳酸菌 (福島洋一)
4. 植物性乳酸菌 (熊谷武久)
4.1 はじめに
4.2 植物乳酸菌の分離と利用
4.2.1 乳酸菌の分離
4.2.2 スクリーニング
4.2.3 発酵乳摂取試験
4.3 おわりに
5. カスピ海ヨーグルト (家森正志,森真理,森英樹,家森百合子)
5.1 カスピ海ヨーグルトとは
5.2 カスピ海ヨーグルトの特徴
5.3 カスピ海ヨーグルトの安全性
5.4 カスピ海ヨーグルトの生理機能および生体防御能
5.4.1 整腸作用および腸内細菌叢の改善,腸内腐敗産物の産生抑制作用
5.4.2 免疫賦活作用
5.4.3 ストレスによる機能障害予防効果
5.5 カスピ海ヨーグルトの市場性について
6. アガリクス (小池泰介,堀内勲)
6.1 アガリクスの生態と由来
6.2 日本市場におけるアガリクス
6.3 アガリクスの薬効
6.3.1 抗腫瘍効果
6.3.2 その他の作用
6.4 アガリクス菌糸体の有用性
6.5 今後の課題と展望
7. メシマコブ (川口正人,堀内勲)
7.1 メシマコブの生態と由来
7.2 日本におけるメシマコブの歴史
7.3 メシマコブの成分と薬効
7.4 メシマコブ菌糸体の有用性
7.5 今後の課題と展望
8. シャンピニオンエキス (栗原昭一)
8.1 はじめに
8.2 組成
8.3 製造法
8.4 機能
8.4.1 口臭成分に対する消臭力(GCテスト)
8.4.2 便臭抑制と腸内フローラの改善
8.4.3 血液浄化による体臭抑制
8.4.4 腎不全進行抑制
8.5 安全性
9. ブナハリ茸 (佐藤拓)
9.1 はじめに
9.2 製造方法
9.3 機能・効能
9.3.1 血圧降下作用
9.3.2 血糖値降下作用
9.3.3 脳機能改善作用
9.3.4 発がんプロセス抑制作用
9.3.5 抗炎症作用
9.4 安全性
9.5 製品例
9.6 市場性
10. シイタケ (須賀哲也)
10.1 シイタケ由来の機能(免疫賦活)成分:β‐1,3‐グルカン
10.2 シイタケ由来β‐グルカン(レンチナン)の食品機能素材としての有用性
10.3 シイタケの食品機能素材としての有用性:有用成分の同定と含有量の保証(製品の品質保証)
10.4 食品機能素材のヒトでの安全性・有用性の検証
10.5 おわりに
11. ビール酵母由来食物繊維BYC (芳田美智子)
11.1 はじめに
11.2 製法
11.3 組成および物性
11.4 機能
11.4.1 腸内細菌叢改善効果および便通改善効果
11.4.2 血清コレステロール値低下効果
11.4.3 アレルギー症状抑制効果
11.4.4 カルシウム吸収促進効果
11.4.5 腎保護効果
11.5 安全性
11.6 安定性
11.7 おわりに
12. ナットウキナーゼ (高岡晋作)
12.1 起源および由来
12.2 構造および特性
12.3 ナットウキナーゼ活性測定法
12.4 安全性
12.5 血栓症とナットウキナーゼの生理活性
13. L-オルニチン (柴崎剛)
13.1 はじめに
13.2 製造方法
13.3 生体中・食品中の含量と安全性
13.4 用途
13.5 機能・効能
13.5.1 成長ホルモン分泌促進作用
13.5.2 運動量低下時の筋肉量減少抑制効果
13.5.3 アンモニア解毒促進作用・運動持続作用
13.5.4 免疫賦活作用
13.5.5 細胞増殖促進作用
14. アスタキサンチン (湊貞正)
第7章 「健康食品」の安全性・有効性情報データベース (梅垣敬三,廣田晃一)
1. はじめに
2. 機能性食品・健康食品の現状と問題点
2.1 多様な健康食品・機能性食品の存在
2.2 有効性情報の実情
2.3 安全性に対する基本的な考え方
2.4 国が行っている制度の認識
3. 健康食品の安全性・有効性情報ネットワークの構築
4. おわりに
目次
第1編 総論(食の機能の理解が深まり活用されることを願って―『食品機能素材3』の序論にかえて;海外における食品の健康強調表示;食品の身体に対する作用;抗酸化;腸管免疫 ほか)
第2編 各論(ビタミン;ミネラル;脂質;植物由来;動物由来 ほか)
著者等紹介
太田明一[オオタメイイチ]
キリンビール(株)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。