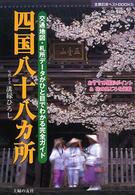内容説明
プラトン、アリストテレスだけがギリシア哲学ではなかった!ヘレニズム哲学再評価の契機となった世界的名著。
目次
第1章 緒論
第2章 エピクロスとエピクロス哲学
第3章 懐疑主義
第4章 ストア哲学
第5章 ヘレニズム哲学のその後の発展
第6章 ヘレニズム哲学と古典の伝統
著者等紹介
ロング,A.A.[ロング,A.A.][Long,Anthony A.]
米国カリフォルニア大学バークレー校西洋古典学教授。1937年英国マンチェスター生まれ。1960年ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン卒業(西洋古典学および古代哲学)。1964年同大学博士号取得。ニュージーランド、オタゴ大学、英国、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、リバプール大学での教歴を経て、1983年より現職
金山弥平[カナヤマヤスヒラ]
名古屋大学大学院文学研究科教授。1955年島根県生まれ。1986年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。日本学術振興会特別研究員、京都大学文学部助手、名古屋大学助教授を経て、2000年より現職
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。