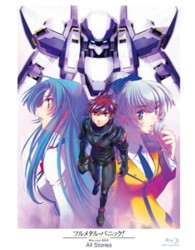内容説明
「死神」は人の命を蝋燭の火で描く。「鰍沢」はお題目を唱えて命がけの危機を脱す。死が身近だった時代、死ぬことすら笑いにかえる。それが落語だ!
目次
い 行き倒れ(粗忽長屋)
ろ 蝋燭の火(死神)
は 墓(お見立て)(安兵衛狐)
に 女房の死(樟脳玉)(三年目)
ほ 本人生還(佃祭)
へ 平家物語(源平盛衰記)
と 溶ける(そば清)
ち 父親の死(インドの落日)(片棒)
り 輪廻転生(地獄八景亡者戯)
ぬ 盗人に殺される(お化け長屋)(新聞記事)〔ほか〕
著者等紹介
稲田和浩[イナダカズヒロ]
1960年東京出身。作家、脚本家、日本脚本家連盟演芸部副部長、文京学院大学講師(芸術学)。落語、講談、浪曲などの脚本、喜劇の脚本・演出、新内、長唄、琵琶などの作詞、小説などを手掛ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さぁとなつ
23
2019.11.22初版 そんなに古い書物ではない 遅いか早いかはあれど人間につきものは“死” 「今は病院で死ぬことが多いから、死は身近ではない。行き倒れも滅多にいないし、家で病気で死ぬこともあまりない。だから、あんまり死の実感がない人も多いかもしれない。でも死ぬんだ。自分も死ぬし、家族や友達も明日死ぬかもしれない。」 死が身近だった江戸時代、落語には死をモチーフにしたネタが多くあった。悲しい死を笑いに転化した。死を知り生きる。それを教えてくれる落語づくし本です。2024/09/17
4fdo4
10
江戸の棺桶屋の話が興味深い。映画などで目にする丸い樽状の棺桶である。作り置きすると置き場に困るから、受注生産。手早く作る粗末な棺桶だから“早桶”。なるほどね。棺桶屋=早桶屋。2023/02/27
kaz
1
どこまできちんと確認されたものかは気をつける必要があるが、落語で取り上げられた死を通じ、江戸の風俗等に接することができる。死が直接出てくるもの、死ぬ話が中に出てくるもの等、落語と死とが意外と近い関係にあることもよくわかる。「死さえも笑いに転化した。いつの時代でも死は悲しい。だが、悲しんでいてもしょうがないよ。生きてゆくのが大変なんだ。悲しんでないで、日々を楽しく生きよう」「死を知ることで、生きる力になる。落語は笑いのうちに、そんなことを教えてくれる」とは、けだし名言。2020/05/14