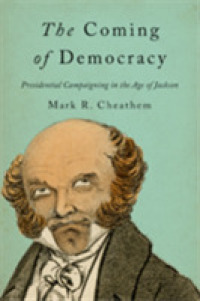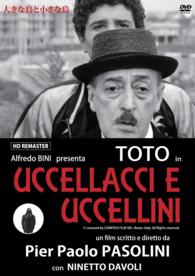内容説明
明治期からの学校教育における作文・綴方や生活綴方教育運動、大正期以降に見られた労働者や農民の自己表現活動としての生活記録、戦時期の生活記録報道運動を経て、戦後の女性の文章表現や生活記録運動に至る、書き合い読み合うことによる学びの系譜を、日本各地の取り組みから検証。自己教育・相互教育の手立てとしての生活記録の実践と理論の展開をひもとき、生活を書く・読むことによる表現や経験を顧みる。
目次
序章
第1章 作文教育と綴方教育
第2章 生活綴方教育と生活教育
第3章 労働者・農民と生活記録
第4章 大日本青少年団の生活記録報道運動
第5章 戦後の生活綴方教育と生活記録
第6章 生活記録の地域的展開―戦後山形県の生活記録を事例として
第7章 日本青年団協議会の生活記録運動
第8章 女性の自己表現と生活記録
第9章 戦後社会教育における生活記録の意味とその課題
終章
著者等紹介
新井浩子[アライヒロコ]
早稲田大学文学学術院講師(任期付)。1970年東京都生まれ。2002年早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得満期退学。2006年公益財団法人日本女性学習財団専門調査員、2012年より聖心女子大学等で非常勤講師を務め、2019年より現職。また公民館で女性学習の講師を務めている。博士(教育学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
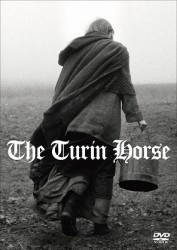
- DVD
- ニーチェの馬