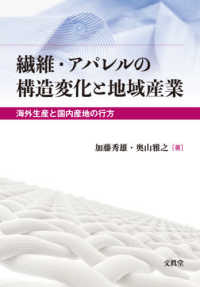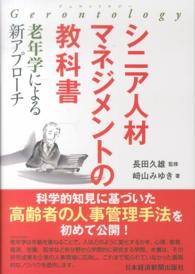- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 雑学文庫
- > 三笠 知的生き方文庫
出版社内容情報
お椀、畳、佃煮、扇……身の回りの「和製のモノ」には、暮らしを楽しく、快適にするための工夫が満載! 先人たちの知恵にせまる!◎心豊かに生きた先人たちの、現代にも通じる斬新な知恵!!
日本人が生んだ、“すごい発想とアイデア”にせまる!
・日本酒――欧米の学者を驚愕させた製法の秘密
・白木――なぜ日本人は白木の家具を好んできた?
・帯――女性の背中をきれいに見せる独創的な知恵
・味付け海苔――江戸商人の知恵から生まれたヒット商品
身の回りで使われている伝統的な「和製のモノ」には、
日本人が昔から培ってきた日々の暮らしを楽しみ、
快適にするための、素晴らしい工夫がなされています。
本書は衣食住に関わる「和製のモノ」を集めて、
その由来や工夫、背景にひそむ日本人の心やセンスについて
わかりやすく解説!
日本人の発想のおもしろさ、柔軟さにビックリ!
藤野 紘[フジノ ヒロシ]
著・文・その他
内容説明
世界に誇れる、「和風の心」を見直す!日本人は春夏秋冬それぞれの美を愛でながら暮らしてきた。一方で、ジメジメした梅雨や凍てつく寒い冬、さらに地震が多いなど厳しい風土の国でもあるため、古代から、自然と上手に共存する工夫をめぐらせてきた。「和製のモノ」は、そんな日本人のセンスと知恵の賜物!
目次
1 資源の乏しい日本だから生まれたエコな暮らしのアイテム―なぜ、寿司屋の湯呑みはあんなに大きいのか?
2 暮らしのなかにいまも息づく信仰厚い先祖の“こころ”―そもそも日本人が箸を使うのにはこんな理由があった!
3 先人たちに学ぶ衣・食・住の健康の知恵―なぜ、くさい糠味噌に新鮮や野菜を漬けたのだろう?
4 ささやかな庶民の暮らしが生んだひとつの道具を二倍に生かす発想法―髪飾りのかんざしの先を耳かきにした理由とは?
5 世界に誇る伝統の逸品に日本人の美的センスが光る―なぜ、平安女性はわざわざ十二枚もの着物を重ね着したのか?
6 ジメジメした梅雨にも負けない島国日本で快適に暮らす知恵とは―なぜ、部屋の間仕切りの障子に薄紙が使われるのか?
7 “洋もの”だってアレンジ次第でれっきとした“和もの”に変身!―シャツがどのように長襦袢に変化していったのか?
著者等紹介
藤野紘[フジノヒロシ]
1958年生まれ。旅行ジャーナリストとして世界各地を訪ね歩き、その土地の文化や風俗、習慣を調査し、書籍や週刊誌等に紹介している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
伊達酔狂
わい
ずず