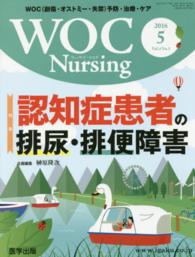内容説明
ものづくりの現場の奥深くから見えてくる日本経済発展の真の力とは何か。神話的理解を超え、一貫した視点で苦闘から隆盛への展開過程を制度やガバナンス、国際環境にも注目して描き出す。今日の停滞局面への示唆にも富む、新たな標準をなす通史決定版。
目次
序章 日本のものづくりを経営史でいかに解きあかすか
第1章 江戸時代の経営
第2章 近代企業の形成―幕末開港から第1次世界大戦まで
第3章 近代企業の変容と大量生産の胎動―戦間期
第4章 日本的経営の形成と展開―日中戦争からバブル期まで
終章 バブル期以降の展望
著者等紹介
粕谷誠[カスヤマコト]
1961年埼玉県に生まれる。1989年東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。東京大学助手、名古屋大学経済学部助教授等を経て、東京大学大学院経済学研究科教授、博士(経済学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
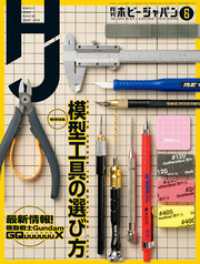
- 電子書籍
- 月刊ホビージャパン2025年6月号
-
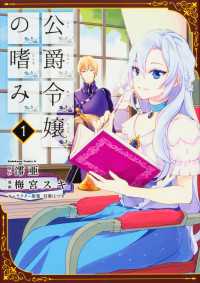
- 電子書籍
- 公爵令嬢の嗜み【タテスク】 Chapt…
-
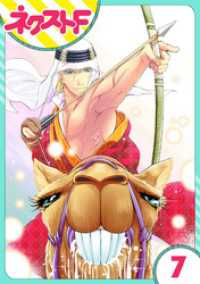
- 電子書籍
- 【単話売】東京スーパーシーク様!! 7…
-

- 電子書籍
- わかさ 2018年6月号 WAKASA…